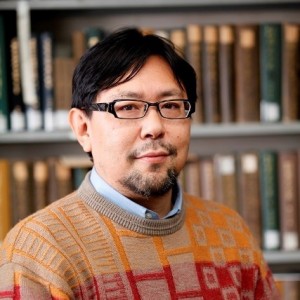書評
『こころはどう捉えられてきたか』(平凡社)
道徳も政治も届かない深層で震えるもの
不倫はほめられた話ではない。だが昨今、ベッキーさんや乙武さんが追い詰められていくさまを見ていて、私は少し異なる感慨を抱いた。それは時代は変わったんだな、ということ。私たち日本人は、恋や愛のあり方にそれなりに寛容だったはずなのだ。不倫が存在を許されぬものであったなら、『源氏物語』は成り立たない。本書の著者によれば、本居宣長(もとおりのりなが)は、人を好きになるというのは、人間の力ではどうにもならないくらいに不思議な振る舞いである、と考えた。心は道徳も政治も届かない深層において、弱く・はかなく・愚かしい。その心が震え、時に倫理や秩序にぶつかりながら立ち現れる、それが恋である。恋をして、弱く・はかなく・愚かしい心と向き合うことが「物の哀れをしる」ということであり、それを体現する光源氏は、単なる漁色家ならざる「よき人」である。そして「よき人」の魂の遍歴をつづるがゆえに『源氏物語』は古典の最高峰と評価できる。
いまは宣長について述べたが、この本は他に熊沢蕃山(ばんざん)や山崎闇斎(あんさい)、伊藤仁斎や荻生徂徠(おぎゆうそらい)などを例に取りながら、「こころ」を縦横に語り尽くす。「こころ」をめぐる思索をたどるにつれ、主として江戸時代の思想家たちの特徴が解き明かされ、さらには儒学(とくに朱子学)・仏教・神道の社会におけるありようが端的に示される。
私も本を書いた経験があるので分かるが、うすい中身を広げて水増しして、本の形にしたものがある。反対に、膨大な学びの成果を凝縮して一冊にまとめることもある。本書はまさに後者の典型である。加えて、本来は難解な内容を実に平易に述べてくれる。すばらしい本である。ぜひ読んでいただきたい(うん、でも不倫はまずいよな)。
ALL REVIEWSをフォローする