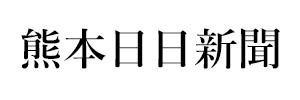書評
『みみずくは黄昏に飛びたつ』(新潮社)
職人芸に徹した作家の自由さ
あるときからマスコミやメディアに滅多に顔を出さなくなった村上春樹は、雑誌などのインタビューに応じることも少ない。本書の後書き「インタビューを終えて」で、彼はヘミングウェイのこんな言葉を引用している。「退屈でつまらない答えで申し訳ないけど、退屈でつまらない質問にはそういう答えしか返ってこないんだよ」
その村上春樹に、川上未映子が4回にわたって長時間インタビューを試みた。「思わず冷や汗をかいてしまうこともしばしばだった」と村上は言い、その質問の鋭さと「矢継ぎ早感」に引きずられて、退屈するどころか、長編小説の技法や、刊行されたばかりの『騎士団長殺し』のキャラクターの作り方について、詳細に解きあかしている。
川上は自分が一度した質問に対して満足のいく答えが得られなかった場合は、後のインタビューの回に、反復して質問する。納得するまで聞こうとするのだ。そのにじり寄り方は、彼女ならではの気迫に満ちている。
川上未映子という作家は(彼女は詩人でもあるのだが)、言葉の音に敏感な人である。それに対して村上春樹もまた、言葉の響きやリズムを大事にする。小説のタイトルも登場人物の名前の付け方にも、そのことが現れている。作家は「目で響きを聞き取れないとダメなんです」と彼は言う。
本書には詩の話はまったく出てこないのだが、詩の書き方とまったく同じ問題が随所に出てくる。これほどまでに詩と近いところに現在の小説の世界はあるのかと、秘(ひそ)かに驚いた。こんなことが話せるのは、お互いが言葉に敏感な作家同士だったからだろう。
しかし、本書での川上未映子はインタビュアーとしての分(ぶ)をどこまでも守り、自分も作家であるというスタンスを極力抑えている。そのことが、村上春樹に答えやすい雰囲気を作らせたと思えるのだが、なにしろ、村上が『風の歌を聴け』で1979年に30歳でデビューしたとき、川上未映子は3歳だったのだ。
一番面白かったのは、村上が自分の書いた過去の小説の内容やキャラクターの名前を、覚えていないということだ。まったく忘れている。嘘(うそ)でしょう、と川上は最初は信じていないのだが、それが本当であったことを4回目のインタビューの最後に知って、「そうすると、なんだか村上さんって……いっそ物語が通過して出ていくための器官みたいな感じがしてきますよね(笑)」と言う。「いや、そんなたいしたものでもないんだけど」という村上の答えに思わず笑ってしまった。別に誉(ほ)め言葉ではないのに、こんなふうに答えるところが村上の真骨頂だ。
つまり、職人芸に徹しているのが村上春樹であって、本書を読んでそのことがよくわかった。わたしは村上がまだ小説を書いていないとき、彼がやっていたジャズ・バーで酒を飲んだことがある。そのときのマスターぶりと懐かしくも同じなのだ。小説にとって何よりも文体が最も大事だ、と彼は言うのだが、これも職人が言う台詞(せりふ)である。しかし、そこから先が面白い。
長編小説を書くとき、「この文章はあっていいのか、ないほうがいいのか、ここまで書いて、この先は書かないほうがいい、とか、そういう見切りをつけなくちゃいけないわけです。そういういくつかの決断をすること自体が、自分を知ることになる」と言う。だから文体は変化する。そういう文章の生成の中に自分があるというのだ。
「わたしは今、村上さんの自由さに震えています」という川上未映子の発言がよくわかる。
ALL REVIEWSをフォローする