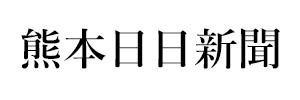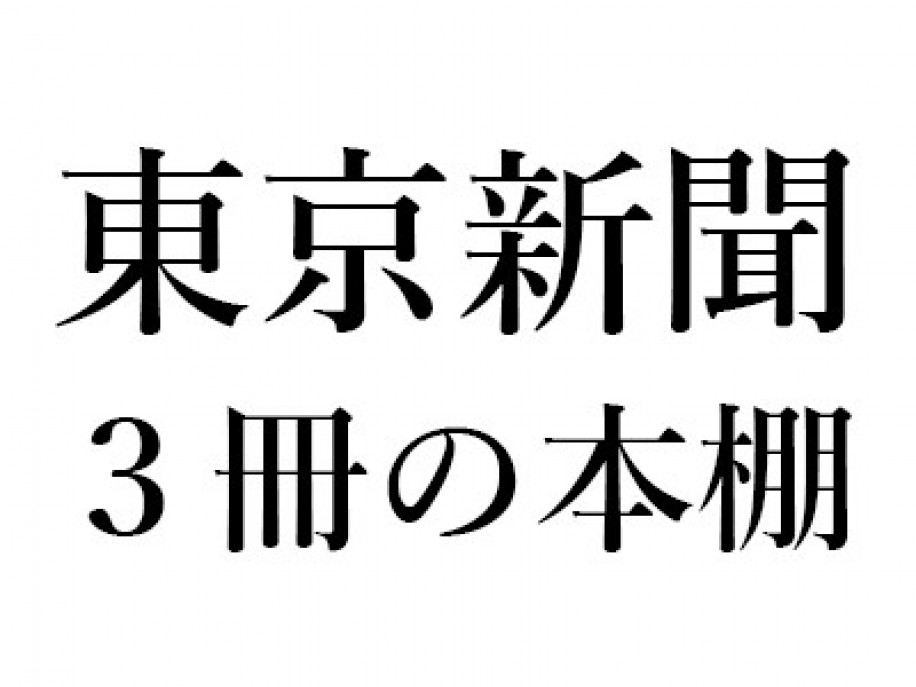書評
『切腹考』(文藝春秋)
現代の語り部 人生の総決算
現代の語り部、詩人伊藤比呂美の人生の総決算とも言える本である。みごとな語り口だ。うねるような文体である。まるで全身の体毛を毟(むし)りとるように、その痛みの皮膚感覚で書いている。若いときの彼女は詩を書くとき、実際に体毛を抜きながら書くことを実践していて、抜くことと抜かれることの間にある自分の皮膚感覚の大事さについて、彼女を主人公にした映画「毛を抜く話」(1981年)のなかでも語っていた。そういう著者が書いた「切腹」をめぐる本である。面白くないわけがない。
冒頭に「世の中に切腹愛好家多しといえども」とあって、切腹の愛好家がたくさんいるんだと驚かせる。「実際に生の切腹を見たことがある人はなかなかいないだろう。わたしはそのひとりなのだった」と続く。まことに、語り部として人をつかむのがうまい。
「切腹」について言えば、彼女はかつて「ハラキリ」という詩も書いていたのだった。熊本に移住してすぐの頃だ。切腹とセックスが同じ種類の恍惚(こうこつ)感を生み出すことが描かれ、「猟奇的ですなあ」という一行でその詩は終わっていたのだが、まさか、その詩を書いていた頃の彼女が変態雑誌の投稿家で、切腹小説の作者たちと交流があり、その筋では有名だったとは知らなかった。興味を持ったらなんにでも首を突っ込んでいく、というのが伊藤比呂美の一貫した流儀で、おかげでその後、人生の辛苦をさんざん嘗(な)めてきた。そしてそれを面白がってきたのである。
なぜ面白いのかを説明するのに、行わけの現代詩という枠組みは彼女にとって狭すぎた。必然的に散文詩になるが、その散文の文体のお手本を、中世や近世の口頭伝承の語り物の世界のなかに見つけるまで、紆余曲折(うよきょくせつ)があった。結婚と離婚、妊娠、出産、アメリカヘの脱出、日本に残る父親の介護とその死を看取(みと)り、さらにアメリカで新しい夫の介護とその死までを看取る。そのたびに、まるで中世の説経節の物語に出てくる主人公のように、くるくると立ち回り、引き受け、呪詛(じゅそ)し、祈り、つまりは自らを物語る以外に、出口も入り口もなかったのである。
いったいそれは何だったのか、とふり返ろうとしたとき、切腹愛好家だったかつての自分に戻ることになった、と思いきや、突然、「鷗外が好き」という一行が登場する。鷗外の小説のなかに「切腹」を見つけたのである。「阿部一族」だ。そこから一気呵成(いっきかせい)に、小説の原典となった熊本に残る「阿部茶事談」の原文からの翻刻版を使用して、現代語直訳を試みる。
一気呵成と言ったが、著者はうねるように勢いを増しながら、そこに至るまで、過去と現在の自らの生活について、あけすけに語り、寄り道をするのだが、これを「道行(みちゆき)」の文体と言えば言えるだろう。
記紀歌謡から、説経節、浄瑠璃や歌舞伎などに多い道行シーン。次々と移りゆく景色を読み込み、地名を読み込み、いきあたりばったりのことがらを長く記述するうちに気分が統一し、やがて、主題に到着して焦点を結ぶ。折囗信夫は「叙景詩の発生」で、それを「道行ぶり」と言ったが、伊藤比呂美の文体がまさにそれなのだ。
皮膚感覚で「切腹」から鷗外へ至り、ドイツに行って鷗外の愛した女のタイプを探り、自分とよく似ていると考え、最後にアメリカの自宅でひとりぼっちになった彼女が、鷗外の遺書から聞こえてくる声を想像し、窓から見えるユーカリの木が倒される運命を予感しながら終わる結末は、壮大な絵物語を読んだような気分にさせられる。
ALL REVIEWSをフォローする