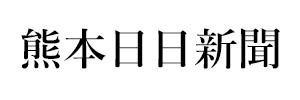書評
『ケルトの想像力 ―歴史・神話・芸術―』(青土社)
欧州文明の基層 日本と共振
どこから読んでも、何度読んでも、心をわくわくさせるような本である。ケルトの装飾文化研究の第一人者である鶴岡真弓の、これまでの研究成果の総集編ともいうべき一冊だ。わたしたちは長い間、ギリシア・ローマ文明がヨーロッパのルーツであると思い込んできた。しかしそれよりももっと古い時代に、ケルト文明がヨーロッパの中心部を占めていたこと、その後、古代ローマが繁栄したときも、アルプスをはさんだ北方の文明としてケルトはあり、相互に交易もしていたこと、つまリヨーロッパのルーツとしてケルト文明があったということが発見されたのは、19世紀後半の考古学資料によってであった。
古代ローマの将軍カエサルの『ガリア戦記』は、当時「ガリア」と呼ばれていた現代のフランス、そこに住むガリア人(ケルト人)たちを征服した記録だ。ローマによって紀元前51年に征服されたケルト人たちは、その後、ヨーロッパ大陸の西側へ追いやられた。ケルト文明の遺産はフランスのブルターニュ地方、イギリスのスコットランドやウェールズ、アイルランドなどに残った。ケルトは「北の蛮族」であり「敗北の民」だと、ギリシア・ローマ文明を中心としたヨーロッパ史は教えてきた。歴史の本は常に勝者の「歴史」を教えるのである。
しかし、ケルト文明は決して「敗北」していたのではなかった。カエサルによって大陸の西側に押し込められた彼らの文明は、ギリシア・ローマ文明が巨大な神殿や彫像に象徴されるような「秩序の格子」を持ったのに対して、神殿や彫像を持たず、また文字を持たず、「荒ぶる自然を畏敬(いけい)し、決して人間を主人にしない、『生命循環』の思想」を持っていた。「生命循環」の思想とは、「遠心力と求心力の相互反転の螺旋(らせん)的ゆさぶり」であると著者は言う。それはケルト美術に示される渦巻き模様がよく象徴している。
ケルト文明は渦巻きのように、彼らを征服した文明と巧みに融合し、ヨーロッパ文明の基層となった。例えばフランスの煙草(たばこ)「ゴロワーズ」は、ガリア人を意味している。敗者を顕彰するようなこの命名は、最後までローマに抵抗した「ガリア魂」を、フランス人が自らの祖先の魂であるとしたことから来ている。長い年月の末にかつての「敗者」の文化が勝者の文化にゆさぶりをかけたのである。
ところで、わたしはかつて詩人・ランボーが生まれたフランスのシャルルヴィル=メジエール市の歴史博物館で、奇妙なジオラマを見たことがあった。古代のシャルルヴィルの先住者(ケルト人)たちの家屋を再現したものだったが、不思議なことに家の入り口に日本の鳥居に似たものが建てられていて、その上部の横木の両端に鳥が止まっていた。人々は鳥居を通して日の出の方角を拝み、ケルト音楽で使う笛や太鼓を奏でていた。鳥はケルトの信仰では魂を運ぶものであった。日本も同じで鳥居はそのことを示し、鳥居の内側をアジール(聖域)としたのである。
著者は初めてアイルランドを訪れたときの印象を次のように述べている。「ユーラシア大陸を挟んで、その『東の極み』にあるわが国と、対極にある『西の極み』の『アイルランド』は、一万キロの距離がありながら『ユーラシア大陸の両耳飾り』のように向き合う島国である」。そしてまた、「『極み』の場所=島には、『宝が埋まっている』と、若い私には思えた」。
この直感が著者を支えた。確かにそうなのだ。ユーラシア大陸の西の端のケルト文化と東の端の日本の文化は共振している。この本には著者が見つけた「宝」が無数に散らばっている。
ALL REVIEWSをフォローする