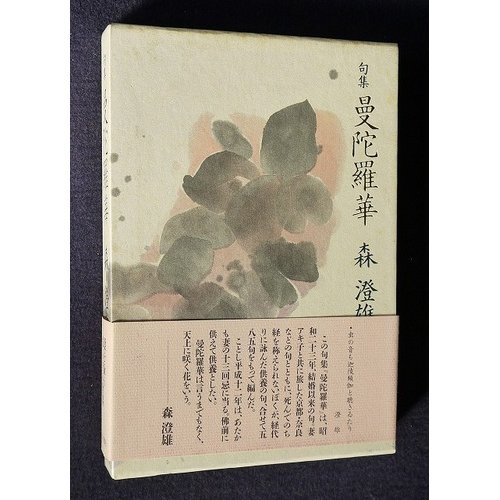書評
『氷菓とカンタータ』(書肆山田)
「戦後」見つめる叙事詩の誕生
詩集の「あとがき」に著者は書いている。「以後という年月の数え方があった。今年(2015年―引用者)は戦後七十年。/しかし、また別な数え方が出現した。大震災と原発事故以後である。以後と意識する日月が私を頓挫させていた」何を「頓挫」させていたのか。大震災と原発事故以後、詩集を編むことを、である。昭和8(1933)年に生まれた財部鳥子は、少女時代を中国の満州で育った。日本に引き揚げてきたのは昭和21(46)年。彼女が13歳のときだった。だから、「私が詩を書いてきた年月はすべて戦後何年というものだった。そこから逃れようとしても逃れようがなく、逃れたと思ってもそこへまた押し戻されてきた」。
詩を書く人間にとって、幼時体験は最も重要である。大人になると子ども時代の記憶を失(な)くしていくのが普通だが、逆に、いつまでも生き生きと、新鮮に思い出せることができる人間こそが、詩人であると言ってもいい。しかし痛切な体験であるほど、それを解きほぐして詩の言葉にするのは容易ではない。フィクション化する技法が必要なのだ。
財部鳥子が満州時代の体験をみごとなフィクションの構造を持って、鮮烈な詩として浮かび上がらせ始めたのは、わたしの知る限り、詩集『烏有(うゆう)の人』(98年)からであった。詩の技法が成立し、熟成するまで、ほぼ半世紀の年月がかかっている。
そういう著者が、今回の詩集を新たに編む気持ちになったのは、大震災と原発事故「以後」、多かれ少なかれ誰もが被爆者になると気づいたことによる。その災難を日本人は長い時間をかけて担い続けるだろう。それを見守る詩の言葉が必要だ。そのことで著者自身の満州体験が生きてくる。これは長く引揚者の体験に固執してきた財部鳥子ならではの、優れた直感である。
詩集『氷菓とカンタータ』のなかで、最も読者の心を揺るがすのは、長編詩「大江のゆくえ―フランクのソナタ・イ長調から」だろう。ベルギーで生まれフランスで活躍した19世紀の作曲家セザール・フランクの代表作、ヴァイオリンソナタ・イ長調。その第一楽章はゆるやかな波のうねりのような旋律が繰り返され、透明な哀(かな)しみが満ちてくる。「大江のゆくえ」は、大震災後、フランクのソナタを聴くことから始まる。聴いているのは「衰耄(すいもう)する女詩人」。彼女はフランクの曲に導かれるようにして、自然に自らの少女時代に戻っていく。長編詩の悠々たる出だしである。
中国大陸を滔々(とうとう)と流れる大河の岸辺に、「一人の少年が立って『おーい!』と叫んでいる/それは国破れた山河で髪を刈られた/女の子の少年姿である」。著者の少女時代の幻が浮かび上がってきたのだ。「あの声は胸の奥底から出ている自分の声だ/協奏のピアノがはじける隙間のどこにも声は住み始めている」
音楽から一挙に満州時代の少女の世界が広がる。大河の岸辺にはつねにキセルの煙管(ラオ)の竹を掃除している仙人のような老人がいる。水死人が流れる。大河から、日々生まれる。「あの水死人はどこへ行くの」と「少年」が聞く。「どこへも行かない」と老人は答える。水死人は大河にとどまり、冬になると凍結した氷の底から頭蓋(ずがい)骨を浮かび上がらせる。女詩人が2011年の大震災後、その大河の岸辺に行くと、やはりその老人はキセルを掃除しており、著者に「(しばらく見なかったねぇ)」と言うのだ。中国の古い民話のような骨格を持った、日本の「戦後」を見つめる、鮮烈な叙事詩の誕生である。
ALL REVIEWSをフォローする