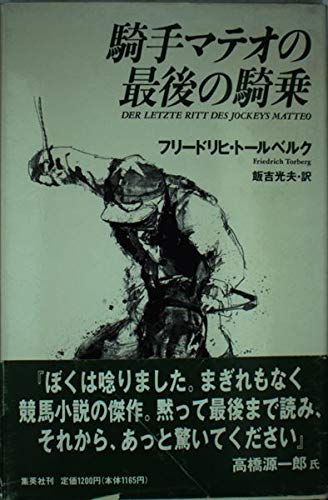書評
『夜と灯りと』(新潮社)
壁崩壊がもたらした鈍痛とエネルギー
広場に集まる人間や道ですれ違う男たち。身なりや顔つきは何一つ特別の印象は残さないけれど、通り過ぎてきた時間と空気が作りあげた内面は、おそろしいまでに独特で、その表出は文学にしか出来ないという当たり前のことを、この作品は今更ながら実感させる。少なくとも日本においては、社会の枠組みの中で生きるその枠組みが、目に見えて圧倒的ではない。じんわりと編み込まれた相互の意識によってかたちづくられている。その内面の様相も、網の中の魚群のように一定のかたちを保っており、固有であることにも限度があるような気がする。
けれどこの短編集には、厚い石壁のような固くて荒々しい社会が、強引な変化を遂げて来たなかで生きてきた人々の、日々刻々の意識が描かれていて、「底辺の多様さ」が痛いほどの印象を残す。
登場するのは、ベルリンの壁が崩壊し統一ドイツが誕生した後も、旧東独に生きてきた「負け組」つまり「二級市民」と呼ばれる人たちばかりだ。
鼻の折れた元ボクサーの囚人であったり、美人局(つつもたせ)稼業で旅を続けるホモのカップルであったり、はたまた薬漬けの画家、老犬の手術代のために競馬で一儲(ひともう)けを企(たくら)む失業者であったりで、およそ新生ドイツの恩恵を被る人物などいない。
あの壁の向こうには自由がある、夢を叶(かな)えてくれる世界があると信じて、壁に激突する意識を高め合い共有し合ってきた旧東独の人々にとって、この20年は何だったのか。
壁が無くなり「どこにでも行ける」自由を確かに手に入れたのだけれど、実は「どこにも行けない」という現実を思い知らされただけでなく、「行く能力の無さ」を自覚させられる苦い歳月でもあったのだと、その彷徨(ほうこう)する身体で教えてくれる、人間群像。
彼らの苦さと苛立(いらだ)ちのエネルギーは、それでもやるせなく希望の火影(ほかげ)を探す衝動となり、人の温(ぬく)もりを求めて手を伸ばす。絶望の一歩手前つまりもっとも苦しい場所で、呼吸出来る場所を探して動き回っている。
彼らは内省的でも自閉的でもなく、街角で、刑務所で、バーで、あるいは夢想の中で、世界の繁栄から取り残されたハエのように、自棄的なまでに激しく飛び回り、傷を負うと知って他者にぶつかっていく。
その内部には、体熱のように渦巻く暴力の衝動があるが、アメリカのそれのように外に向かって無差別に発散される質のものではなく、自らの痛みを確認するような被虐性を帯びているので、読む者は共感しながらも鈍痛を覚えないではいられない。そしてこの鈍痛によって、ドイツの「二級市民」が何たるかを知るのだ。
鈍痛が退く一瞬もある。そこに射(さ)し込む一筋の光明。
行きつけのバーで味わうビールやシュナプスは美味(うま)く、古くからの無愛想な友人は自分を裏切らず、愛犬は従順、ときには賭け事にも勝つ。万事思うようにならないのではなく、ひとつやふたつは希(ねが)いが叶うのだ。生きていることはまずまず良くて、壁をよじ登ろうとして死んだ人間よりマシではないか。
作者の声はシニカルだが、人間を愛(いと)おしむ暖かみも含まれている。
細部を丹念にというより執拗(しつよう)に辿(たど)る文体、極端に小さく絞られた視界を、コマ送りするような描写は、社会の底辺で生きる人間の息づかいを伝えてくるだけでなく、過去と現在を行き来し、妄想と現実をない交ぜにして進む。読みにくいが馴染(なじ)んでみると、この文体が人間の存在そのものとして入ってくる。
たとえば「ヨハネス・フェッターマンの短くも幸福な生涯」という一編で描かれる、クスリで朦朧(もうろう)とした画家の意識。
「憧(あこが)れはまだあった。ときどき、少しは、特に、いつか昼に目覚めたときなどには。もうまた夜だ、そして突然彼は非常に醒(さ)めていて、とても孤独だった」
切れ切れにフラッシュする意識を、作者が必死で追ううち、時間が飛び空間がシフトする。物と出来事と認識が、言葉の切片となって降り積もっていくとき、遠い昔に書かれたアメリカ小説の匂(にお)いが立ち上ってくるから面白い。
「犬と馬のこと」の中の主人公は、老いて足の衰えた愛犬にピートという名前を付けているが、ピートはテニスプレイヤーのピート・サンプラスから付けた。ブラジルのサッカー選手ペレやジョン・レノンはいまだに輝いていて、ユカタン半島のマヤ文明の遺跡は神秘的な魅力を失っていない。
それらがまだ光を保っていることに、長く閉ざされてきた旧東独のナイーブさを感じると同時に、「青年期の文学」という言葉も思い浮かんでくる。
成熟と洗練からは遠く、最先端からは一見周回遅れに見えるが、必死の形相で走るランナーには、問答無用の力強さがある。
ALL REVIEWSをフォローする