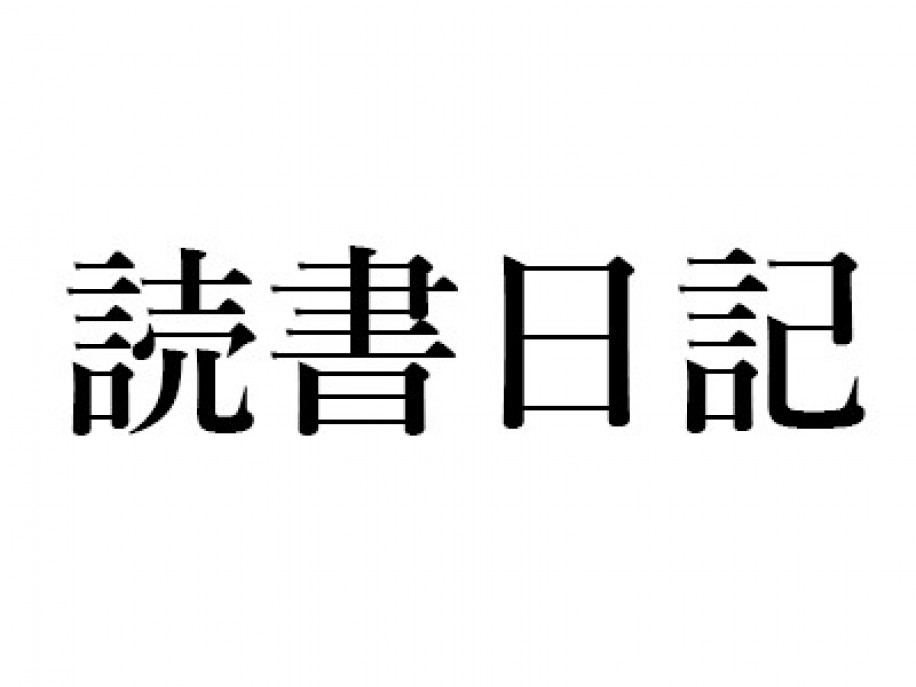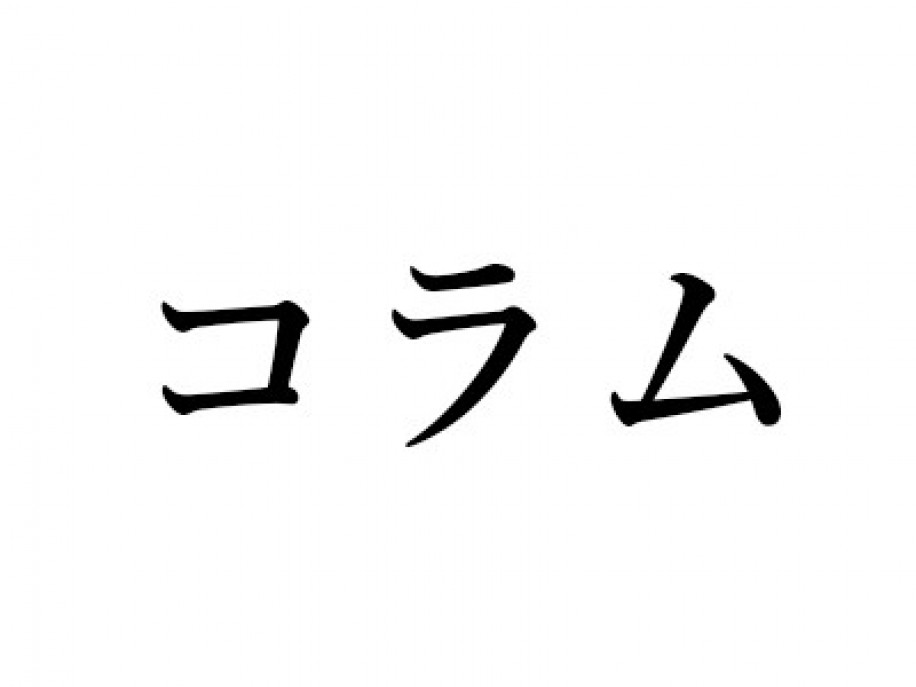書評
『悪党芭蕉』(新潮社)
「古池に飛び込む蛙」は虚構だった
芭蕉の実人生を、厖大な資料で読み解いた力作である。省略がきいていて歯切れがいい。思えば中学三年の夏休みに、読書感想文で『奥の細道』について書いた。市のコンクールで一等賞をもらった。で、才能があるのではないかと錯覚した。中学生に芭蕉の何が解るだろう。この年齢まで解らないままで来た。本著で半世紀ぶりに目が覚めた。芭蕉はとんでもない男だった。芥川龍之介は芭蕉のことを「三百年前の大山師」と書いたそうだ。私は大山師に騙されて、小説家になったのかもしれない。
思いこみ、仮想、の力は大きい。
古池や蛙飛こむ水の音、はポチャンか。大きい蛙ならタポン。しかし飛びこむ音なんてしないんだそうだ。ヘビなど天敵に襲われそうになったときだけ水面に向かって飛ぶそうだが、その場合も音をたてずにするりと水中にもぐりこむ。ふつうは池の端より這うように水中に入っていく。
著者はカエルの図鑑片手に、春の一日庭園の池で観察した結果、この句は写生ではなくフィクションであることを発見する。芭蕉のフィクションの力ゆえ、日本中いや世界中の人が「蛙が飛び込む音を聴いた」ような気になった。芥川が芭蕉を大山師だと言ったのは、事実より虚構が先行し、その虚構を事実のごとく広く世間に丶実感させる力を芭蕉が持っていたからだと著者は考える。であれば芥川も大山師で、大山師たちに騙され感動して文芸の道に入った私もミニ山師となる。
山師の功罪は、一度実感させてしまった虚構は、二度と消すことが出来ないという点にある。たとえ芭蕉本人が現われて、あれはウソでした、と言っても、蛙は音たてて水に飛び込むのである。とりわけ俳句が掴まえる瞬間は、一閃の光であるから、耳や目の奥を染める。染まったものは消えない。
時は元禄綱吉の時代。「生類憐みの令」が発布され蚊も殺せなくなった。なぜこんな理不尽な令が出されたかといえば綱吉は男色にふけり女に子を孕ませることが出来ず、母親の桂昌院が心痛して男子誕生祈願をする。それが「生類憐みの令」につながった。蛙が古池に飛び込む水音は、生類賛歌、時流に叶っている。芭蕉は政治に敏感な男なのだ。
男色の面でも、芭蕉の行動は、反蕉風、反ワビサビ、である。美しい弟子との愛の隠密旅行が『笈の小文』となる。かなりアブナイ。もっとも当時は、男色は大したスキャンダルではなかったらしい。
とはいえ芭蕉の衆道は俳句愛好家のあいだでは禁句になっていたようで、このようにして俳聖芭蕉のイメージが形成された、となれば、ダ・ヴィンチ・コード芭蕉版か。
本著はタイトルからして芭蕉のイメージをくつがえすべく書かれたように見えるが、実はそうでもない。芭蕉は悪党ではない。悪党に憧れ、弟子たちの悪党ぶりを容認し、何度となく危険な橋を渡りながらも、しかし百人とも三百人とも二千人ともいわれる弟子たちが各地につくる蕉門の首長として、かしずかれるだけの人望があった。死の報せを聞いて葬儀に馳来(はせく)る者も多く、大人気作家だったことがわかる。この存在の仕方は、『奥の細道』を弟子一人連れてとぼとぼ歩く“孤独な俳人”のイメージを裏切っている。
日本の美の源流となるワビサビは、このようにして生まれた、という文芸DNAの“虚構因子のしたたかさ”を証明する一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする