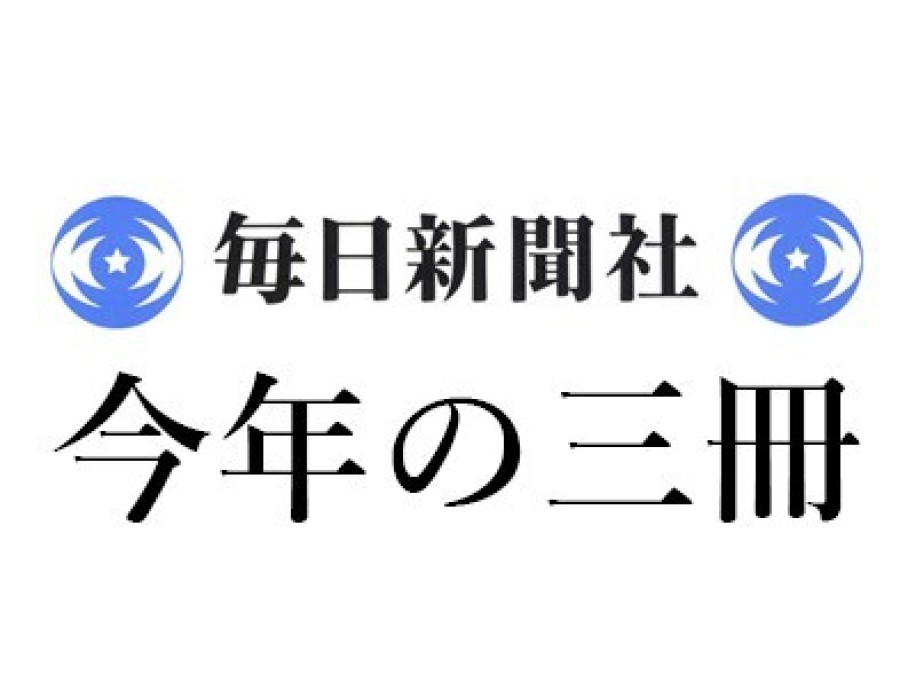書評
『ひよっこ茶人の玉手箱―インターネットでお茶を愉しむ』(マガジンハウス)
デジタルなお茶
「インターネットでお茶を愉しむ」とサブタイトルにある。むむむ? デジタル系と佗び寂び系、現代ふうと昔ふう。ネット上の交流と、席を同じゅうして味わうお茶とは、様式からしても、相容れないもののようだが。『ひよっこ茶人の玉手箱』(松村栄子著・マガジンハウス)は、とり合わせの妙に、まず引き込まれる。
三十代の著者はもともと、お茶のみならず日本的なるもの全般に、無関心だったという。成人式の着物を買うべく親が貯めてくれていたお金は、海外旅行の足しにしてしまったくらいだし、畳なんてかっこ悪いと、その上をじゅうたんでおおっていた。そんな著者がメール仲間に導かれ、よちよち歩きながらお茶を愉しむようになるまでのプロセスを綴った、エッセイだ。
結婚して関西に移り住んだ著者は、関東での暮らしに比べ、生活と伝統文化が近いところにあると感じた。神社や寺では、能だの狂言だのがしょっちゅう奉納されているし、よそのお宅を訪ねれば、日常的に抹茶を供される。お茶の飲み方くらい知っておかないとまずいかもと、まずは教室の門を叩いた。
興味が俄然、広がったのは、インターネットでお茶のメーリング・リストを覗いてから。略してML。電子メールを、一対一ではなく、おおぜいの人と交わすシステムである。
そういうものがあるとは、著者は知っていた。夫の父から夫に和服が送られてきて、着せようとし、ふと疑問がわく。男にも半襟は要るの?
くだんのMLには、男性も多いという。お茶をたしなむくらいなら、和服にも詳しかろう。思いきってメールを出したのが、はじまりだ。
読んでまず驚くのは、会員の多様性。初心者から、指導者、家元までいる。年齢、性別、職業もさまざま。外国に住む人も。茶道の世界でも、流儀やキャリアの枠を越えた、これほど自由な交流は、他にないらしい。利害関係はいっさいなし。共通点はただひとつ「お茶が好き」ということのみ。
MLに集う面々が面白い。茶室がほしいばかりに、二十代の若さで公営団地を購入し、和室を改造した男性。「公営」を選んだのも、規格上、民間のマンションより床下が深く、お茶に欠かせぬ炉が仕込めるからだという。山から竹を切ってきて、茶杓を削るなんて序の口。お茶といただく薯蕷(じょうよ)饅頭も、よりよいものを求め、山芋をおろすところから試作を重ねている人も。
意外だったのは、理系の人が多いことだ。古びた釜をもらったが、どうしたら使えるようになるかとの問いに、「赤錆びは水酸基を含む酸化鉄で、腐食反応により鉄がイオンとして溶解し」云々のメールがとびかう。伝統文化=文系ととらえていた著者の(あるいは読者の)固定観念を打破してくれる。世の中にはいろいろな人がいるということは、著者も頭では知っていた。が、あらためて思うのは、人間は「ひとりひとりがほんとうに面白い」。
MLに入ってから、自分でも「少しひとが変わった」という。前は他人にほとんど興味がなかったが、「敬意」がめばえてきた、と。殻を破って、外の世界へ。「ひよっこ」には、初心者であることの他、そうした意味も込められているようだ。
著者によれば、お茶席を成立させるのは、美味しいお茶を相手に飲んでもらうため、快い「場」を作り上げるべく、皆が心をひとつに合わせること。すなわち「一座建立(いちざこんりゅう)」だ。
ネット交流についても、同じことがいえる。匿名性ゆえの問題が指摘されるが、「茶の湯の精神」のように、インターネット本来の目的にかなったものと出会うとき、奇跡とも言うべき稀な、ピュアな人間関係を生むことができる。まさに「玉手箱」。開けてみて、目をぱちくりさせている著者の発見に、共感できる。
カバーは、表が和紙ふう、裏を返せばパソコンの画面を模したデザイン。中央には、世界の究極の像を意味する○(円相)のマーク。表裏一体、異なるとされるものの合一を表し、これまた妙である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする