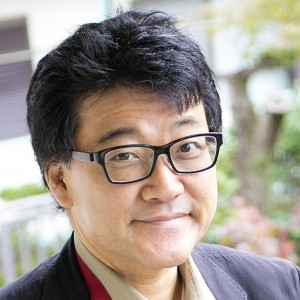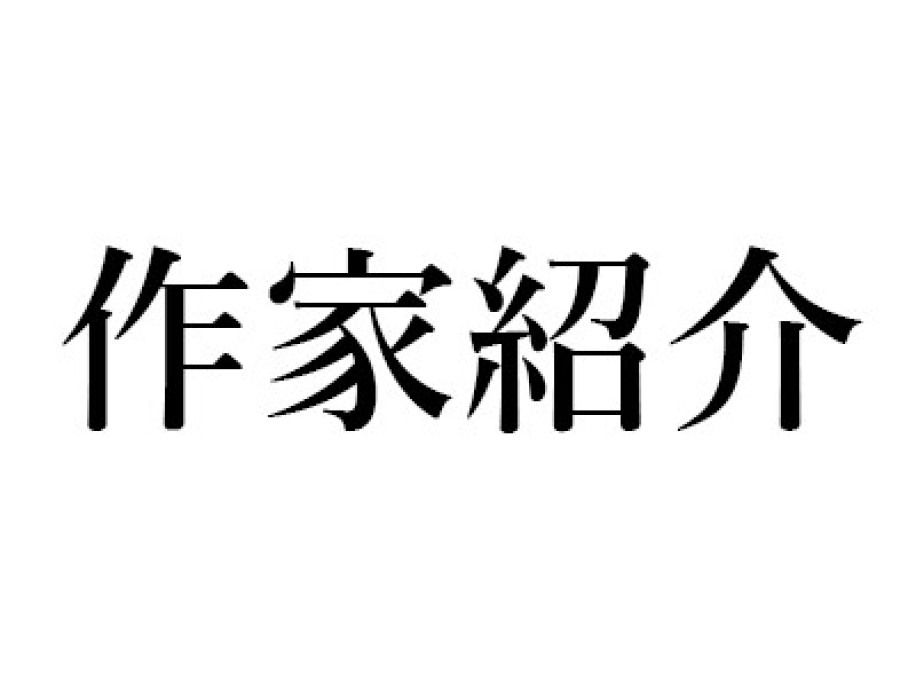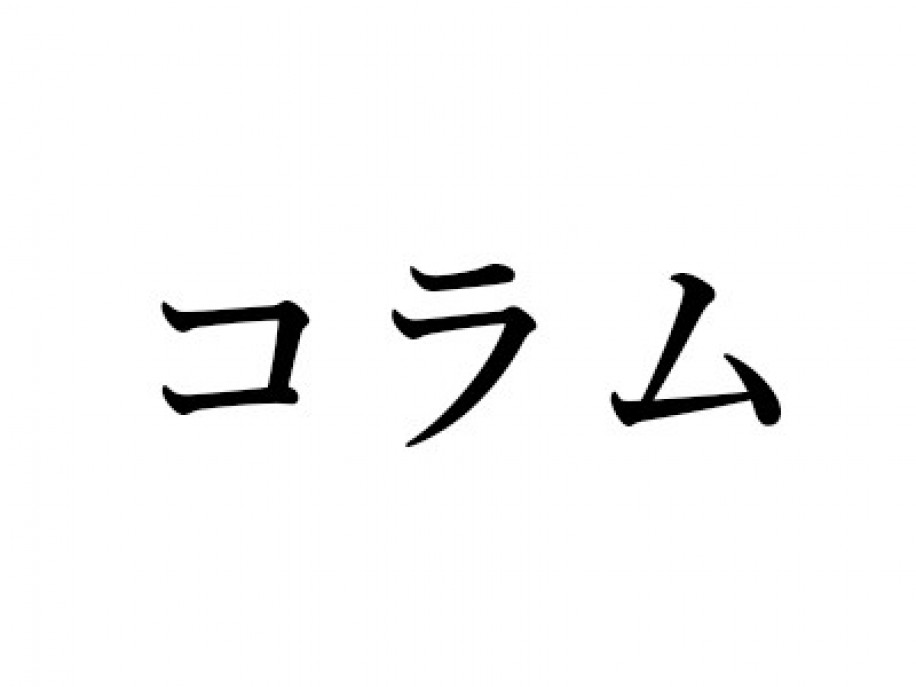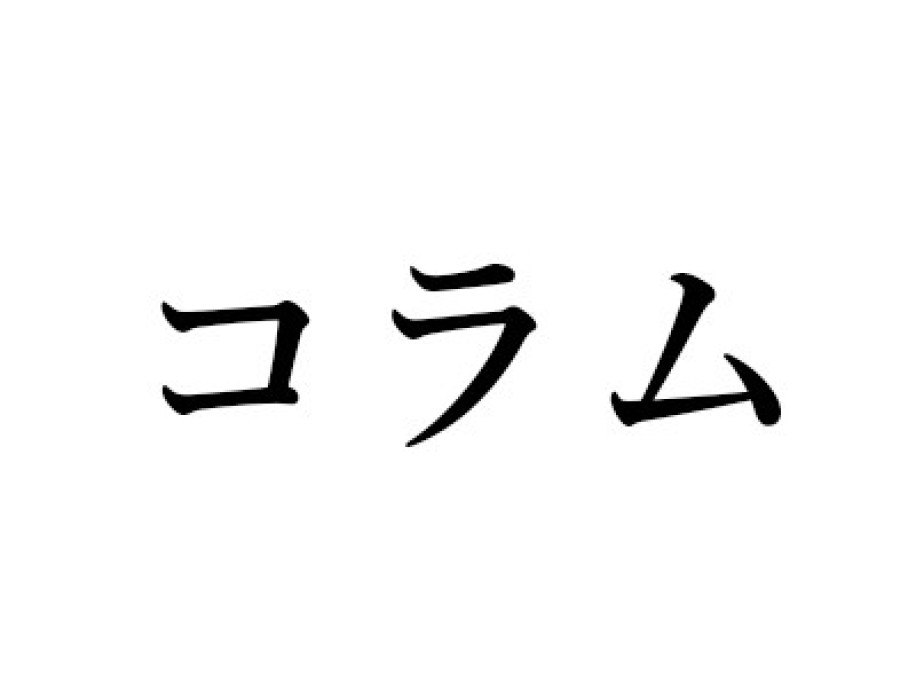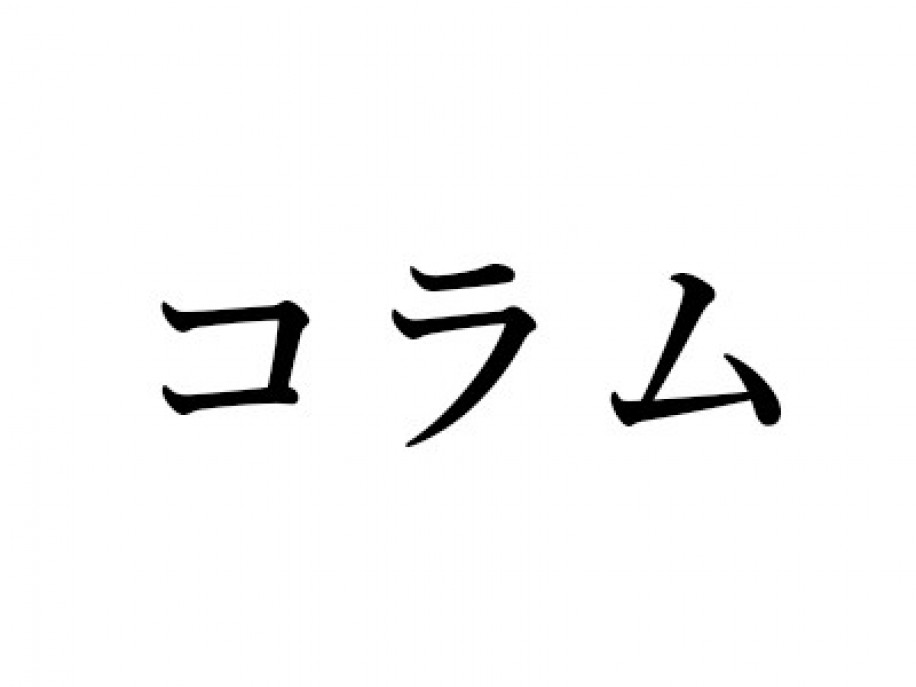書評
『ゴーストと旅すれば』(福武書店)
ジム・ダッジ(Jim Dodge 1950- )
アメリカの作家・哲学者。小説家としては『かものファップは知っている』(1983)が第一長篇。『ゴーストと旅をすれば』(1987)は第二作にあたる。第三作のStone Junction(1990)は、「ポスト・サイケデリック小説の近未来物語で、ある部分はピンチョン、ある部分はトールキン、そしてブローティガンを思わせる」と評される。そのほかの著作に、小冊子の詩集が数冊、作品集Rain on the River: New and Selected Poems and Short Prose(2002)がある。introduction
福武書店もひとときは新鮮な海外文学を紹介してくれるありがたい版元だった。スティーヴン・ミルハウザー『エドウィン・マルハウス』『バーナム博物館』や、スティーヴ・エリクソン『黒い時計の旅』も、最初は福武書店から上梓されたのだ。本書でも、ほかにウィリアム・コツウィンクル『ホット・ジャズ・トリオ』と、スコット・イーリィ『スターライト』を取りあげている。この会社が海外文学の路線から撤退しなければ、ジム・ダッジのStone Junctionも翻訳されるはずだった。まあ、死んだ子の歳を数えてもしかたないけれど。それよりもどこか心ある出版社が、この屈折痛快爆走青春ロードノヴェル『ゴーストと旅すれば』を再刊しないだろうか? 作中でかかっている往年のヒット曲の数々も、いまは、だいぶCDで聴けるようになったみたいだし。▼ ▼ ▼
純真な少年は、自分が生まれるまえに両親がなにしていたかなんてしゃべりたくないと言いながら、ライ麦畑で遊んでいる子どもたちが崖から落ちないように見はることを夢想してればいい。気の弱い不良ならば、夜中にこっそりと校舎の窓ガラスを割ってまわれば、まあ憂さばらしくらいにはなるだろう。しかし、おおよその青春時代の鬱屈というのは、そんなくらいじゃとても解消できやしない。もっと、いいかげんでバカバカしい、とてつもなく無意味なほうへと走らなければおさまらない。行きすぎたってかまうものか。
ぼくもティーンエイジャーのころはたいがいバカなくちだったが、『ゴーストと旅すれば』の主人公、飛ばし屋ジョージ・ガスティンにはかなわない。こいつはアンフェタミンを毎日二十錠飲んでいるうちに、もともとの性格がいっそう向こうみずになり、十八歳の懊悩とあいまって、いきなり高校を辞めてしまう。なんとなくサンフランシスコに行き、ろくでもない人生がはじまる。生きるためには金が必要なので、非合法なシノギにだって手を染める。そんななかで知りあった前科者(なんだろうな、どう見ても)スカムボール・ジョンソンに、事故に見せかけてクルマを毀すという仕事を紹介される。つまり、保険金目あてのクライアントからの依頼を受け、盗みだしたクルマを修理不能にするというビジネスだ。相棒のビッグ・レッドとふたり、はじめは機械的にこなしていたのだが、無軌道な若者ゆえだんだんムチャをするようになる。
だがとにかく、退屈しはじめたビッグ・レッドとおれは、同じぶち壊すにも楽しくやろうと考えた。あるときは、ビッグ・レッドが、マウント・タムで道路にそった崖の上に足場のぐらついたでっかい岩があるのを見つけてきたんで、うまく位置を決めて、てこを使って六一年型インパラの新車にその岩を落っことすことができた。それから、スティンソン・ビーチでクライスラーを燃やしたこともあったが、一番面白かったのは、フォート・ロス・ロードでサービス・ステーションの従業員の芝居をしながらオールズ八八をめちゃくちゃにしたときのことだろう。ビッグ・レッドが安物雑貨店で赤い星型のバッジを二個買ってきて、胸につけてそれらしく見せかけたんだ。おれたちは「星のマークの人になら、車をあずけてもだいじょうぶ」とか歌いながら、作業に精を出した。(略)
「ジョージ、おれはフロントガラスをきれいにするよ」ビッグ・レッドは楽しそうにいうと、八ポンド・ハンマーでフロントガラスをぶち破った。「きれいになっただろう? まるでガラスがないみたいじゃないか」レッドはこいつがかなり気に入ったらしくて、いつになくおしゃべりになっていた。
ジョージやビッグ・レッドが生きているのは、一九五〇年代末から六〇年代半ば。かつてビートニクスが暮していたサンフランシスコのノースビーチにも、ビートルズの音楽が流れはじめ、フラワー・チルドレンが髪を伸ばしはじめた時代だ。ジョージたちも、そうした時代の空気を吸ってはいるが、かといってビート世代の信条「物質文明への抵抗」にしたがって、クルマを毀しているのではない。基本的には金儲けのためだが、じっさいはモノを破壊する行為そのものを、子どものように楽しんでいる。
しかしある日、キャデラックのグローブボックスのなかから出てきた一通のラブレターが、ジョージの運命を変えてしまう。そのクルマは、大金持ちの老婦人が不出生のロックンローラーへの贈り物として用意したものだった。彼女は想いを果たす前に他界し、その後、彼も飛行機事故で亡くなっていた。しかし、いかなる事情にせよキャデラックはロックンローラーのもとに届けられるのが正当だ、ジョージはそう考える。墓の前で燃やしてやればいいじゃないか。かくして奇妙な〈巡礼〉がはじまる。
この〈巡礼〉も、クルマの破壊や自動販売機の窃盗とおなじくらい、意味のない行為だ。墓の場所さえ知らずに出発し、保険金詐欺の親玉からは狙われ、老婦人のラブレターと一瓶のアンフェタミンだけが道づれ。ジョージは、「自分が本当に解きはなたれて、なにかをしているんだという、ワイルドでクレージーな」感じを味わいながら、ハイウェイを飛ばす。そして彼が行程で出会う連中もみな、少なからず「ワイルドでクレージー」だ。
ワタリガラスが「アーク?」と鳴くのを聴いて、あれは昔ノアが方舟から放ったカラスだと直感し、真実を説くために、大出力のアンプを使って辻説法をしてまわっている化学者。世界ではじめてのロックンロール教会をはじめるため、ヒューストンにむかう途中の元チンピラの黒人宗教家。さまよっているゴーストを、本人のもとに送りとどけることを生業にしている、「世界一の」巡回セールスマン。冗談のいきすぎが原因で昏睡状態に陥った、プラクティカル・ジョーク・ショップの店主。
目的地に着くころには、ジョージ自身のゴーストまであらわれる。「ゴーストというのは死者の身体を離れた霊魂のはずだが、おれはまだ死んじゃいない。もしゴーストが死者の霊魂であって、おれがまた死者になっていないとすると、こいつはこれから起こることの予告ってことで、おれに警告しているんだろうか」などと、いちおうは悩むが、そのうちどうでもよくなってしまう。さらに、むかしのガールフレンドの幻影も、ジョージのクルマに乗りこんでくる。彼女はゲイのユング心理学者兄弟と一緒にいまは南米にいるはずだが、いったいどうした案配なのだろう。まあ、いいか。カーラジオを鳴らしながら、ひた走るだけだ。サウンドとビートがあれば、とりあえず行ける。
旅のおわりが近づくにつれ、ジョージは自分がいかにたくさんの荷を積んで走ってきたかを思いしる。キャデラックを燃やしても、過去は灰にならない、人生は消えない。ジョージはいまなお、アメリカを走りつづけている。出会う人たちに、ワイルドでクレージーな物語を聞かせながら。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする