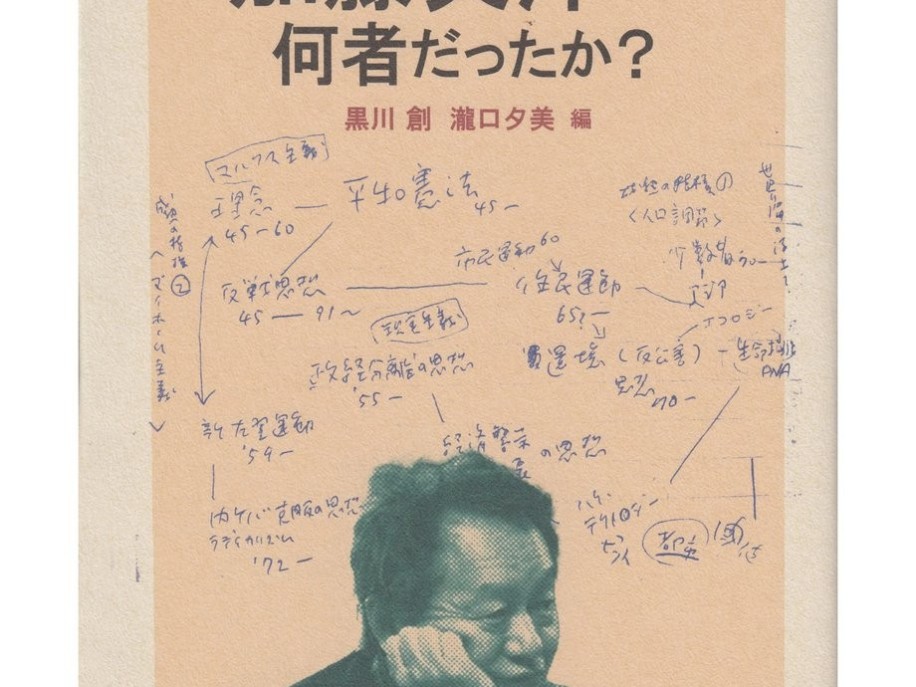書評
『国境 完全版』(河出書房新社)
いかなる線からも自由な視線で
読めば、作品ひいては世界への向き合い方に靴に砂でも入ったみたいな違和が生じ、各自に足下を見直させる。卓越した文学評論の名に値するすべてが本書にはある。我々は漱石や鴎外を教科書に載る〈国民作家〉として読みがちだが、それでは彼らの作品が〈美しい日本語・日本文学〉という凡庸な紋切り型に押し込められたままだ。
そもそも漱石や鴎外はどんな時代に書いていたのか? 植民地的野心を抱く生まれたばかりの近代国家が、戦争のたびに変動する国境のうちに、異質な言語や文化を持つ人々を暴力的に抑え込んでいた時代である。漱石は1909年に満州と朝鮮を旅行するが、その帰国直後に伊藤博文がハルビン駅頭で安重根に暗殺される。著者は漱石が記した「韓満所感」という新資料を発掘し、漱石を植民地という文脈で読み直す。
さらに鴎外の詩や泉鏡花、佐藤春夫の小説を当時の歴史状況に置き直し、日清・日露戦争、大逆事件、関東大震災など国家的事件と照らし合わせながら、思いも寄らぬ光景を露(あら)わにする。国境の内部に均質性と一元性を捏造(ねつぞう)し、それを強制する国家の思惑に収まりきらないテクストの微細な動きを本書は見逃さない。
文学作品は一つの言語や文化に回収されえず、そこには砂粒のように異質な要素が、多様な他者の声やまなざしが紛れ込んでいる。だがそれは植民地の時代に限られた話ではない。我々の〈現在〉そのものがそうした砂なしには成り立ちえないからだ。
それを誰よりも知る著者は、朝鮮半島出身者や、満州や台湾やブラジルへの日本人移民が日本語で書いた作品にも光を当て、近代文学の古典に対する以上の深い敬意と愛情を傾ける。差別や国境など人を分け隔てるいかなる線からも自由なその視線をなぞるとき、不安な美しさと豊かさに満ちた〈日本語文学〉の懐かしい風景が浮かび上がる。
朝日新聞 2014年1月19日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする