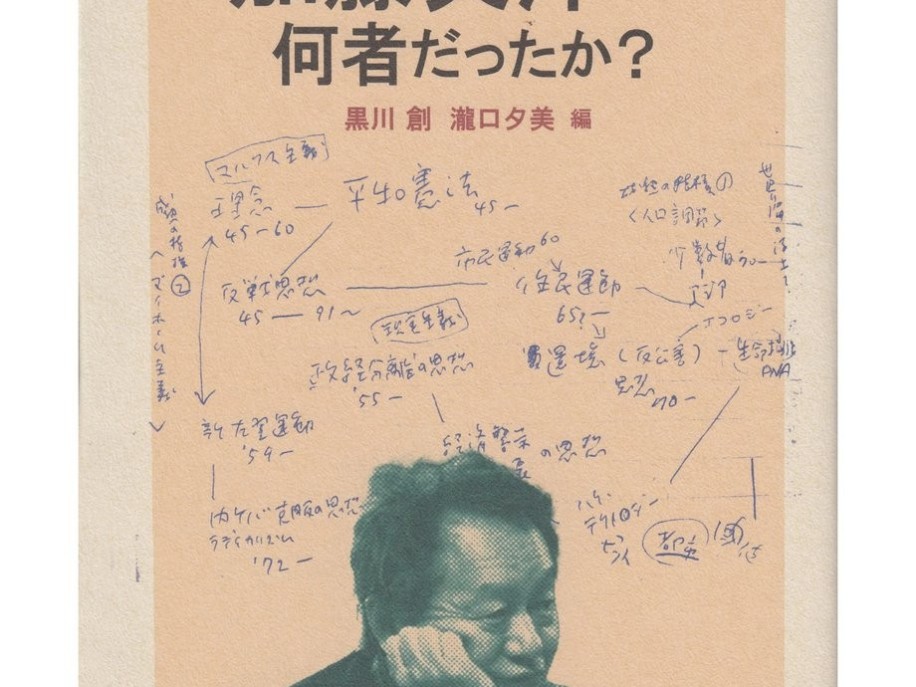書評
『若冲の目』(講談社)
恋の双幅図
本書は、旧植民地と日本語の関係を中心として、境界線をまたぐ言語の行方に目を向けた犀利(さいり)な評論集『国境』(メタローグ)などで知られる著者初の長篇小説である。ただし、長篇とはいえ、全体はゆるやかに独立したふたつの中篇からなっている。両者を結びつけているのは、表題にも採られた十八世紀の伝説的な細密画家、伊藤若冲をめぐる謎と、その謎を解こうとする男女の横顔である。つまり、若冲に深入りしていく過程が、そのまま自身の過去と現在を見直す契機になるという仕掛けがほどこされているのだ。
前半の「鶏の目」では、フリーライターの女性が若冲ゆかりの寺を訪ねて住職に話を聞き、過去帳を洗い直しながら、晩年の画家と暮らしていたとされる妹の存在を突き詰めていく。もはや評伝と呼んでも差し支えないふんだんな情報の開示と、そのスリリングな切り口を堪能しつつ、読者は彼女の執拗な追及の裏に、いかなる動機が隠されているのかについても興味をそそられるだろう。後半の「猫の目」は、この問いにたいするひとつの解答となっている。語り手は、先に登場した女性と同棲しているらしい元美術館学芸員のI。彼は漱石がその作品に書き記している若冲の絵の描写に基づいて、三十幅がならぶ代表作「動植綵絵(さいえ)」の全貌と構成にかすかな疑問をぶつける。若冲の絵の精緻な読解が可能にしたこのあたりの推理の展開は、前半をしのぐ面白さだ。
しかし若冲を見つめる彼らは、若冲に見つめられてもいる。両の目が完全に一致することはありえず、そこには埋めようのない時間の懸隔が生じている。本書の双幅図は、均衡の取れた貝合わせに陥らない微妙なずれを含ませる若冲の「動植綵絵」さながら、いかなるジャンルの規制をも逃れて、批評と小説、あるいは評伝と恋愛小説をしなやかに混合する自在な散文となった。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
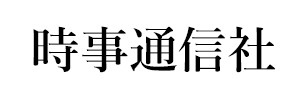
時事通信社 1999年5月
ALL REVIEWSをフォローする