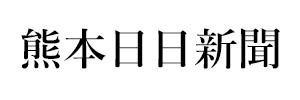書評
『セザンヌの地質学―サント・ヴィクトワール山への道』(青土社)
彼が執拗に山を描いた理由
セザンヌ(1839~1906年)の最後のアトリエを訪ねたことがある。彼が生まれた南仏のエクス・アン・プロヴァンス市の郊外にあって、樹木に囲まれた2階建ての細長い建物だ。アトリエは彼が生きていたときのまま保存され、それがそのまま美術館になっていて、セザンヌ協会の本部であり、研究センターにもなっている。アトリエは北側に広い窓があり、驚くほど背の高いイーゼル(画架)、静物画のモデルになった石膏(せっこう)像や壺(つぼ)があり、パレットや油絵具(えのぐ)も、そして絵のモデルになったリンゴなどの果物までが、当時と同じように並べられている。まるでいまもセザンヌが絵を描いているような雰囲気なのだ。
セザンヌは生涯、エクスの街のどこからでも見え、ランドマークとなっているサント・ヴィクトワール山を、さまざまな角度、距離から描き続けた。しかも、山を描いたどの一枚も、筆致は異なり、山肌の色も構図も違う。どうしてあんなに執拗(しつよう)に描き続けたのだろう。わたしには長い間、疑問だった。
アトリエ近辺からサント・ヴィクトワール山が見える。頂上がやや右に傾き、白い岩肌が目立つ。現実の山はさほど魅力的なものには思えない。しかしセザンヌが描くと、激しい筆のタッチで海の波のように見えるし、雪山のようにも、あるいはゴツゴツとした太い角のようにも見え、まことに変化自在、幻想的なのだ。
なぜそうなのかを、セザンヌの「地質学」への関心から解きあかしたのが本書である。彼が何を描こうとしていたのかを徹底的に分析している。紹介されている絵のどれもが面白く、また、著者の言葉は絵のなかの微細な筆致や空間配置、その理由にまで届き、なるほどと、わたしは何度も膝を打つ思いがした。
あのサント・ヴィクトワール山を見てごらんなさい。なんという勢い、なんという太陽の激しい渇望、そして晩になってあの重量が全部下りてきたときのなんというメランコリー……。
本書冒頭にセザンヌのこの言葉が引用されている。山の重量が夜になると全部下りてくるなんて。まるで詩の言葉である。
あの石の塊は火だったのだ、まだ中に火を秘めている。昼間、陰は震えながら後ずさりしているみたいだ、あの塊を怖(おそ)れているみたいだ。
サント・ヴィクトワール山は火山ではない。この地方は昔、海底にあって、そこに堆積した地層が隆起し、その最も高い地点が山となったのだ。山はかつての海が立ち上がったものだと言ってもよかった。その「石の塊」をセザンヌが「火」と見立てたのは、地層が隆起し、柔らかく褶曲(しゅうきょく)した時代のエネルギーを、山はいまも秘めていると見たからだった。そのエネルギーを彼は「火」と呼んだ。
セザンヌはそれを透視しようとして、山を生きもののように描く。すると、山のなかから、古代ローマ帝国時代の「石切り場」の風景が甦(よみがえ)り、旧約聖書から新約聖書へ移り変わる時代を描いた画家プッサンの古典主義絵画の風景が重なり、「山、斜面、岩石、岩盤、建築石材」などへ感受性が集中し、樹木も家も岩石も建築石材も、同じ夕ッチ、同じ肌合いで、溶け合うように描かれることになる。しかも山を描くときの視点はつねに空中高く浮いている。奇妙で奇怪な構図が成立する。
ああ、それでわかった。セザンヌの風景画が持つ大胆な構図と色彩は、彼の前にだけ姿を現した自然の風景なのだ。画家の魂に切り込んだ、緻密で壮烈な書である。セザンヌはただ地球が柔らかかった時代の、誰も描かなかった岩を描きたかったのだ。
ALL REVIEWSをフォローする