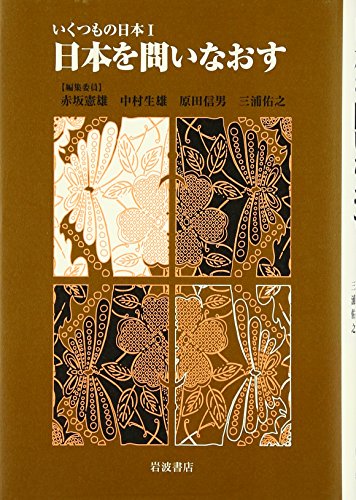書評
『講座日本美術史 物から言葉へ』(東京大学出版会)
専門家の着眼点と研究方法を探る
美術館に行って美術作品を見ていても、実は作品そのものについて知らないことが多い。ところが専門家が側にいて説明してくれると、なるほどそうなのかと思うことがしばしばある。この講座は、そうした美術史の専門家が作品を探ってゆく視点と方法を明らかにするシリーズである。
美術作品については、哲学に始まって文学や歴史学など多様な視角から探られてきているが、それを専門とする美術史学ではどのような形で向かいあっているのかを、魅力的に語ろうという企画である。
全六巻の講座の第一巻が本書で、作品をいかに言葉で説明するかという視点から編まれている。
そして「日本美術史研究の保守本流の立場で構想した」と編者自身が豪語するように、最初の章には仏画と仏像の記述のあり方が扱われている。
こうした基本的なことは鑑賞基礎知識を解説した本などにも詳しく記されてもいるのだが、ここでは単に基礎知識を提供するだけでなく、その記述に関わる問題点も指摘されていて、まことに興味が尽きない。
たとえば長さについては「法量」という言葉がよく使われているが、それに積極的な根拠がないことなど。
また仏画や仏像のどこに着目すれば、時代的な変遷がおさえられるのかも指摘されており、その目で見ると、これまでに書かれてきた文化財の調書の問題点も見えてくる。
絵画や彫刻と続けば、工芸品の記述も欲しくなろうが、原稿が出版に間に合わなかったようで、惜しまれる。これは最近の講座物の宿命か。
次の章は、専門家でなければわからない、作品の内部に立ちいたった研究方法に基づく記述である。
『源氏物語絵巻』を、テレビでも紹介された光学的な分析手法を介して考え、運慶の仏像を、胎内の銘記や納入品から探り、絹本『一遍聖絵』を、その修理で見えてきた絵画の裏側のあり方から見つめ、建物から切り離された障壁画を、どう復元してゆくのかを考察する。
ここでもその方法を紹介するだけでなく、扱い方についての問題点を指摘するとともに、とくに美術作品を正当に評価することの難しさを語っているのが印象的である。科学的分析が進めばすすむほど、作品の評価は困難さをましてゆくようだ。
最後の章は、外部から作品にいかに接近して記述するかを問題とする。
絵巻物には、絵につけられた詞書の作者から接近し、江戸時代初期制作の『彦根屏風』には、画家の側のあり方から接近する。俳人蕪村が描いた『夜色楼台図』には、詩文の世界との関わりから接近し、明治時代に制作された石版画には、データベースによる情報処理を通じて接近している。
それぞれに興味深い指摘ではあるが、この付近になってくると、他の分野から考える余地も多くあって、様々な異論も出てこようか。その意味からも刺激的な記述となっている。
このところ、営業努力を求められて美術館や博物館は苦労していると聞くが、これと同時発売の第六巻の木下直之編『美術を支えるもの』を読めば、特別展だけでなく常設展示の作品をもこの目で確かめたく足を向けたくなる。
なお最近の講座は索引のないものが多くて困るが、本巻にもない。かといってシリーズの最終巻にも同時発売なのでない。何とかしてほしい。
ALL REVIEWSをフォローする