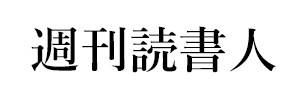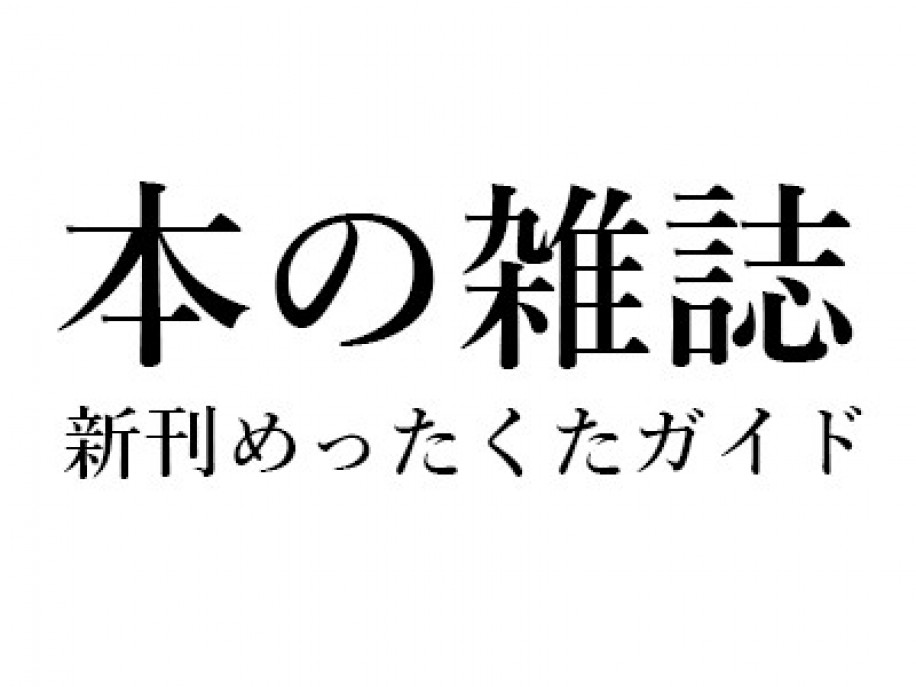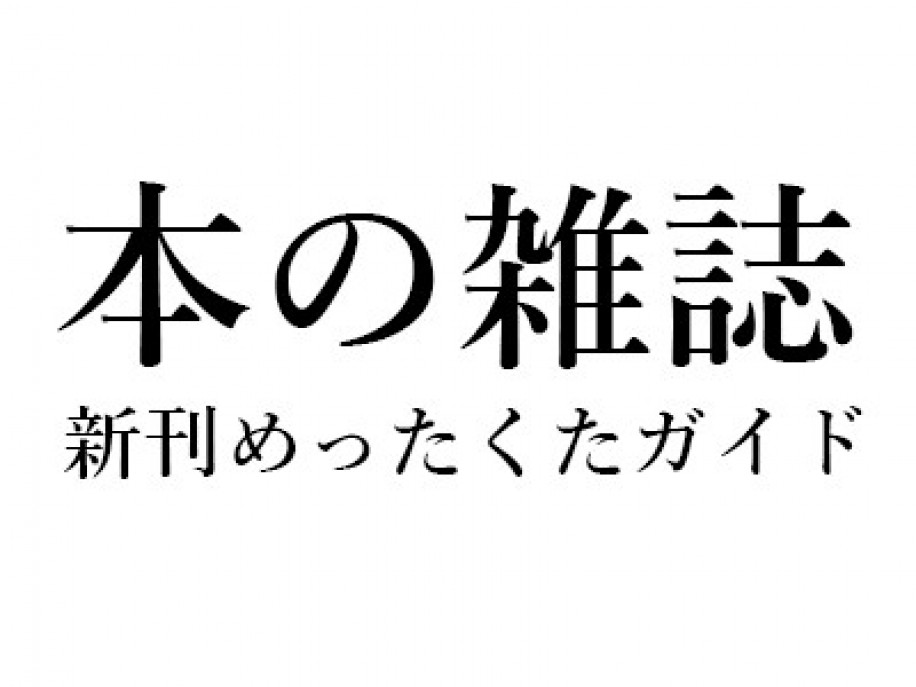書評
『楳図かずお論: マンガ表現と想像力の恐怖』(青弓社)
特異な作家の頭の中を解明
第一人者による本邦初の研究書
楳図かずおは戦後最大のマンガ家の一人といって差し支えないと思うが、楳図を論じて一冊とした評論、研究書はこれまでなかった。本書が本邦初の楳図かずお研究書ということになる。もちろん楳図を特集した雑誌やムックならそれなりの数が出版されている。著者の高橋明彦はそれらの主要なものにも寄稿してきた楳図研究の第一人者だ。楳図研究サイト「半魚文庫」を運営する半魚さんといったほうが通りがいいかもしれないが、ともかく、その筋で知らない人はおそらくいないだろうという筋金入りの楳図マニアである。
本業は大学教授で、日本近世文学・出版史が専門ということだが、力の入れ具合が、楳図研究にかなり、というより思い切り傾いているように見えるのは気のせいか。楳図を特集した『ユリイカ』二〇〇四年七月号にともに寄稿した縁だったか、その前後の別の楳図案件を通じてだったかで著者とは知り合ったのだけれど、当時から本書の構想は聞いていた。つまり十年以上を費やした畢生の大作なのだ。巻末の詳細な年表や資料まで含めると約五百ページという大著だが、「半魚文庫」を知っている身としてはつい「薄くない?」と漏らしてしまったものだ。エッセンスに徹した内容で、それでもこれだけ大きな本になるのだから楳図は巨大である。
実際、楳図作品群は膨大である。最大長編となった『14歳』の連載終了後の一九九五年、五十九歳の若さで擱筆したが、このときちょうどデビュー四十周年だった。四十年間に描いたマンガは、高橋によると、およそ三百作、原稿用紙で三万五千枚にのぼるという。
楳図作品は難解である、といわれる。最高傑作であるとされる『わたしは真悟』(一九八二年)がとりわけ難解と評されることが多いが、難しさの本質は初期の恐怖マンガから通底しているように見える。
どんな“本質”か?
その不可思議なユニークさに魅入られる者がいる一方で、否定的に評価する者ももちろんいる。批判から見ていったほうがわかりやすそうだ。
高橋は、否定的な人たちは、楳図作品を「非合理」で「破綻」含みなものと捉えているのだと指摘する。
一例をあげれば、代表作のひとつである『洗礼』には「夢落ちじゃないか」という批判がある。醜くなってしまった大女優が、美しさを取り戻すために娘に自分の脳を移植する物語だ。脳移植によって娘の人格は母と入れ替わる。頭には生々しい手術跡。だが最後にすべてが娘の妄想だったことが判明し、手術跡も消えてしまう。ところが、妄想すなわち夢落ちを前提としてもなお、ストーリーや細部には合理性を欠いたように思える部分が残る。
高橋は、それらを「非合理」「破綻」とする解釈は誤解であると斥けるのだ。「破綻」は一切ないとまで断言する。原因と結果を整合的に捉えきれず、論理を裏切っているような構造が楳図作品には至るところに見出せる。高橋はそれを「始原または結末がメビウスの帯のようにねじれていく構造」と呼ぶ。評者は「めぐらない因果」と書いたことがあるのだが同じことだ。
独自の認識論に基づく世界の原理と、それに従った作品世界の構築――これが楳図作品を貫くものである。そしてその認識と原理は、恐怖マンガの初期から胚胎されていたものであると高橋はいうのだ(ちなみに「恐怖マンガ」というジャンルを作ったのは楳図である)。
本書は要するに、楳図の作品世界を司っている論理構造、ひいては楳図かずおという特異な作家の頭の中をひたすら解明しようとしたものである。マンガ表現論から、書誌学、ポストモダン思想まで登場するが、それは、使えるものは何でも駆使して楳図の世界に分け入ろうという腹からだろう(個人的には、ポモのところは別の道具を使ったほうがよかったんじゃないかと思うけど)。
あとがきで著者は「完璧な一冊」は存在しないが「決定的な一冊」はあるといっている。研究者にとって無視できない一冊のことだ。著者の野望は、本書を楳図研究における「決定的な一冊」に仕上げることだったわけだが、少なく見積もっても、その野望は実現されたと評価してよさそうである。
ALL REVIEWSをフォローする