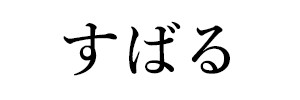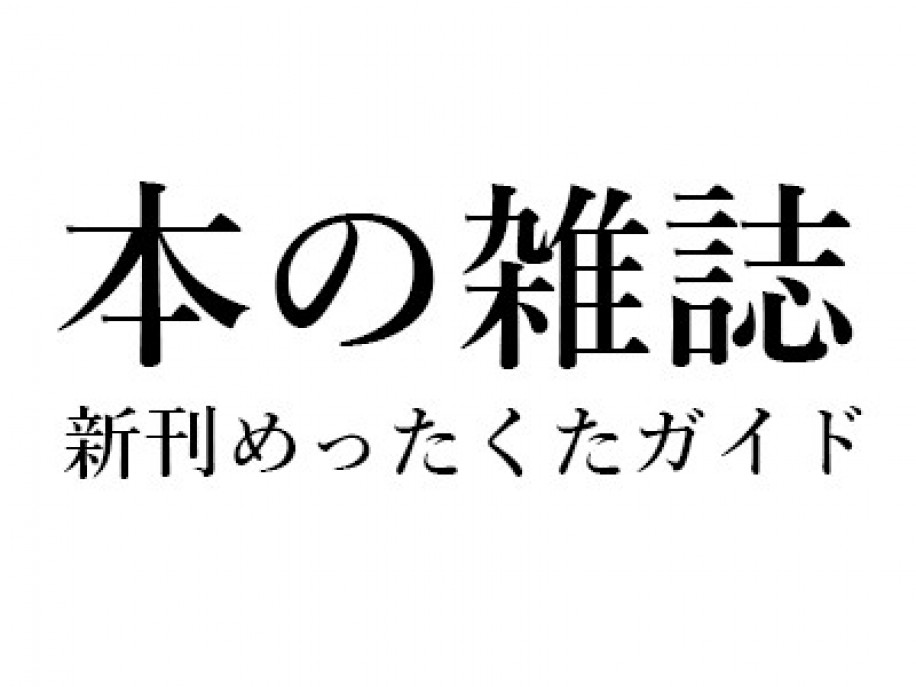書評
『どろにやいと』(講談社)
異界をどろにやいと
異界に閉じ込められる物語である。語り手の「わたし」はボクサーだったが右目を負傷して引退、ぶらぶらしていたところ父が死んで家業を継ぐことになる。父は自ら研究開発したお灸「天祐子霊草麻王」を行商で売り捌いていたのだが、熊に殺されてしまったのだ。父を手伝っていた叔父から跡を継ぐようにいわれた「わたし」は、顧客名簿を頼りに行商に出て、一年が経とうとしていた。
舞台は山陰地方の志目掛(しめかけ)村だ。村は四つ辻を中心にいくつかの集落に分かれていて、牛月山、魚尾山、湯女根山という三つの霊山に囲まれている。霊山はそれぞれ、過去、現在、未来を象徴しているとされる。出羽三山がモデルだろう。
この村に行商に訪れた「わたし」は、四つ辻を軸にたらい回しのようにうろつかされるばかりで、集落から出ることができなくなってしまう……。
民俗異界ものの類型じみた物語は、泉鏡花や深沢七郎、森敦といった作家を想起させる。戌井は『深沢七郎コレクション』を編んでいるし、森の「月山」はまさしく出羽三山麓の七五三掛(しめかけ)という集落に「わたし」が幽閉される物語だ。
外界から隔絶された集落を異界として描いた諸作にならい、この「どろにやいと」も要所に幻想を忍ばせている。蜘蛛の刺青をふくらはぎに持つ若い女は足を蜘蛛みたいに伸ばして「わたし」を絡め取るし、イノシシの肉を振る舞う千倉さんはイノシシみたいな相貌に変化する。
だが、どれもこれもちっとも幻想的じゃないのだ。「飄々」と形容されることの多い戌井の筆致が、そうしたシーンを夢幻のように描き出すことを拒んでいる。
あるいは霊山にしてもそうだ。村に足止めされた「わたし」は未来を象徴する湯女根山だけ見ることができない。牛月山と魚尾山、つまり過去と現在に囚われていることを暗示しているわけだが、あろうことか、作者は「わたし」の口を借りてこう説明してしまうのである。
なんだか、この村に来てから今生と過去をさまよっているような気になってきました。
身も蓋もない。事情は併録の「天秤皿のヘビ」にしても同じだ。南国のヘビ使いの少年というエキゾチックな題材を扱っていながら、情緒を削ぎ落として、冗談みたいにさばさばと進むのである。
「どろにやいと(泥に灸)」とは「無駄なこと、無意味なこと」という意味だ。結末での「わたし」の姿と呼応したものだが、異界をめぐる物語一切を、作者はどろにやいとしているようでもある。
ALL REVIEWSをフォローする