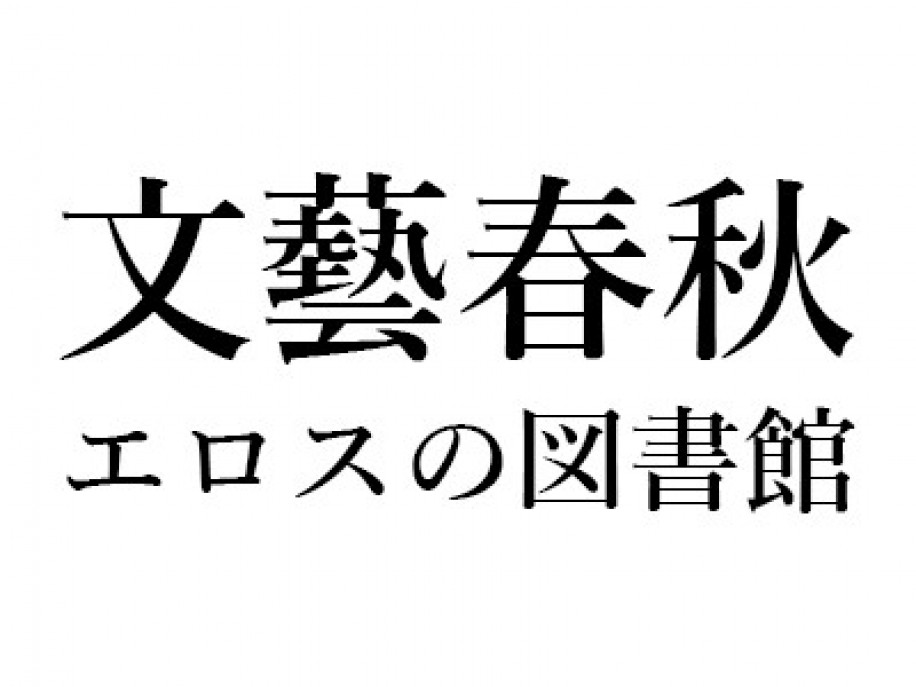書評
『岡崎京子の研究』(アスペクト)
映画「ヘルタースケルター」のヒットで岡崎京子の名前を見ることが再び多くなった。一九八〇年代前半にミニコミや自販機エロ本などからマンガ家としてのキャリアをスタートした岡崎は、九〇年代に入る頃にはカルチャースターとして独特の存在感を放つに至ったが、九六年に不慮の事故に遭って重度の障害を負い、以来、活動を休止している。
早いもので、もう十六年も経ってしまった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2012年)。
本書は、作家研究とも一種の評伝とも見ることができるが、いずれにせよ読者が目を見張る、あるいは戸惑うのは、異様なほど詰め込まれた情報の量だろう。
「岡崎京子の前史」「~黎明期」「~初期」「~中期」「~後期」と五期に分けられた本文は上下を二分割したレイアウトで、上部は「研究者のためのノート」と題された対談形式による解説(最初は論文形式だったものを読みやすくするために書き直したそうだ)、下部は微に入り細を穿(うが)ちあらん限りの情報を収めた年表となっている。下部を見るとデータの細かさにクラクラとするのだけれど、上部だけでも実はけっこうな情報量で、岡崎が中2のときに音楽雑誌に投稿したごく小さいイラストなんてものまでがさらっと発掘紹介されていたりする。
本体にあたる上部「研究者のためのノート」で特に重視されているのは、岡崎がコミットしてきた人脈であり、雑誌をはじめとするメディアである。サブカル的固有名詞が横溢(おういつ)していることについて評論家の山形浩生氏が「知ってる連中同士が符牒(ふちょう)を投げ合うという、悪い意味で内輪向き」(*)だと批判していたけれど、それはたぶん違う。個々を見ればたしかにどうでもいいような情報も少なくない。だが、内輪向きの符牒めいた人脈やメディアの輻輳(ふくそう)こそが岡崎京子という存在であり、彼女の本質なのだと著者は見ているのだ。
「本書が成立した理由は二つ考えられます。一つは、〔岡崎が〕様々なメディアに自分の発言や作品を残していること。もう一つは、様々なメディアからの影響を隠さなかったことです」「もし彼女がマンガ家はマンガだけを描いていればいいというような専任意識を尊ぶタイプであれば、おそらく本書は三分の一以下の薄さで十分だったでしょう」
ひたすらデータを集積することで作家像を描くという行為にはおそらくもうひとつ狙いがあって、それは、既存の評論や批評に対するアンチテーゼである。
「彼女がどんな仕事をしてきたのか、それだけを注意深く追うことがまずは必要だと思いました」
文芸批評の神様・小林秀雄の「批評とは竟(つい)に己の夢を懐疑的に語る事ではないのか」に我々は少々毒されすぎてしまった。その(悪)影響は文学に留(とど)まらずあらゆるジャンルに俗化して及んでいる。いい加減そういうのは解毒しましょうよ、というわけだ。偏執狂的な情報収集力は著者の持ち味であるけれど、岡崎京子のように感染力が強く、誰もが思い入れだけでうっかり語ってしまう対象にはとりわけ解毒が有効である。
大概のことはデータが語ってくれる。本当に語るべき、語られるべき言葉はデータの向こうにあるのだ。
(*)http://d.hatena.ne.jp/wlj-Friday/20120720/1342756979
早いもので、もう十六年も経ってしまった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2012年)。
本書は、作家研究とも一種の評伝とも見ることができるが、いずれにせよ読者が目を見張る、あるいは戸惑うのは、異様なほど詰め込まれた情報の量だろう。
「岡崎京子の前史」「~黎明期」「~初期」「~中期」「~後期」と五期に分けられた本文は上下を二分割したレイアウトで、上部は「研究者のためのノート」と題された対談形式による解説(最初は論文形式だったものを読みやすくするために書き直したそうだ)、下部は微に入り細を穿(うが)ちあらん限りの情報を収めた年表となっている。下部を見るとデータの細かさにクラクラとするのだけれど、上部だけでも実はけっこうな情報量で、岡崎が中2のときに音楽雑誌に投稿したごく小さいイラストなんてものまでがさらっと発掘紹介されていたりする。
本体にあたる上部「研究者のためのノート」で特に重視されているのは、岡崎がコミットしてきた人脈であり、雑誌をはじめとするメディアである。サブカル的固有名詞が横溢(おういつ)していることについて評論家の山形浩生氏が「知ってる連中同士が符牒(ふちょう)を投げ合うという、悪い意味で内輪向き」(*)だと批判していたけれど、それはたぶん違う。個々を見ればたしかにどうでもいいような情報も少なくない。だが、内輪向きの符牒めいた人脈やメディアの輻輳(ふくそう)こそが岡崎京子という存在であり、彼女の本質なのだと著者は見ているのだ。
「本書が成立した理由は二つ考えられます。一つは、〔岡崎が〕様々なメディアに自分の発言や作品を残していること。もう一つは、様々なメディアからの影響を隠さなかったことです」「もし彼女がマンガ家はマンガだけを描いていればいいというような専任意識を尊ぶタイプであれば、おそらく本書は三分の一以下の薄さで十分だったでしょう」
ひたすらデータを集積することで作家像を描くという行為にはおそらくもうひとつ狙いがあって、それは、既存の評論や批評に対するアンチテーゼである。
「彼女がどんな仕事をしてきたのか、それだけを注意深く追うことがまずは必要だと思いました」
文芸批評の神様・小林秀雄の「批評とは竟(つい)に己の夢を懐疑的に語る事ではないのか」に我々は少々毒されすぎてしまった。その(悪)影響は文学に留(とど)まらずあらゆるジャンルに俗化して及んでいる。いい加減そういうのは解毒しましょうよ、というわけだ。偏執狂的な情報収集力は著者の持ち味であるけれど、岡崎京子のように感染力が強く、誰もが思い入れだけでうっかり語ってしまう対象にはとりわけ解毒が有効である。
大概のことはデータが語ってくれる。本当に語るべき、語られるべき言葉はデータの向こうにあるのだ。
(*)http://d.hatena.ne.jp/wlj-Friday/20120720/1342756979
ALL REVIEWSをフォローする