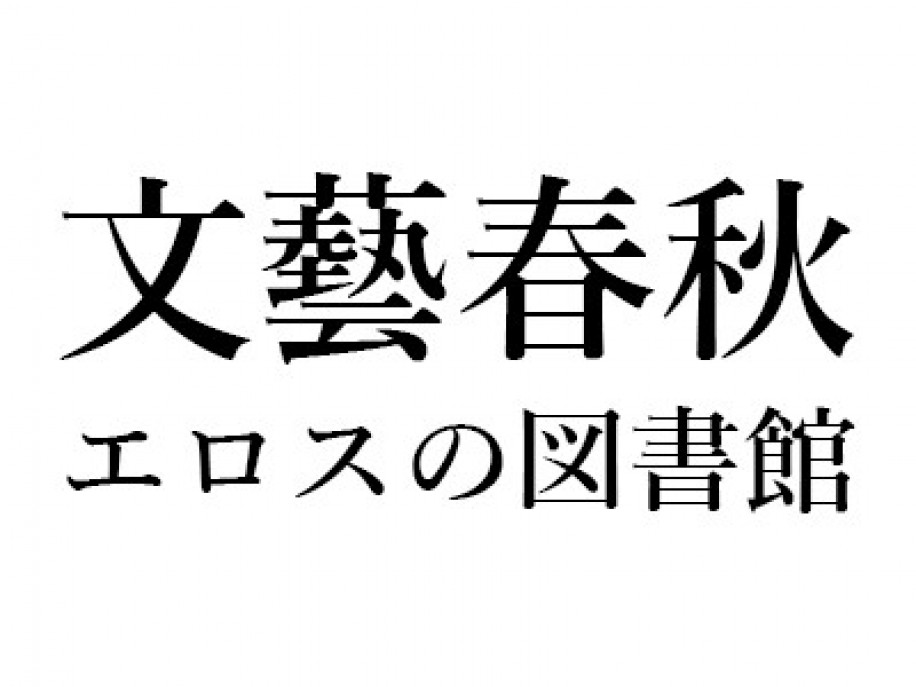解説
『贋作王ダリ―シュールでスキャンダラスな天才画家の真実』(アスペクト)
まことに驚くべき書物が出たものである。サルバドール・ダリの言動の奇矯さについては、あまねく知られていることだろうが、その「贋作(がんさく)」をめぐってこれほど衝撃的な事実があろうとは。「事実は小説よりも奇なり」というけれども、本書はまさしくフィクションを上回るノンフィクション――いや、読者は本書を世にも稀な小説(フィクション)として読まれても一向にかまうまい。実際、本書は小説のようにおもしろいのである。
カダケスにいるダリが、詩人ポール・エリュアールの連れてきたロシア人の妻ガラと運命の出会いをしたのは一九二九年夏のことである。たちまち意気投合した二人を置いて、エリュアールはひとりパリに戻った。そしてこの年の十一月にダリはアンドレ・ブルトンの紹介で初めてパリで個展を開き、シュルレアリストとして認知された。アンドレ・マッソンやアントナン・アルトーと袂(たもと)を分かったシュルレアリスムの総帥が、この二十五歳のスペイン人画家に新たな可能性を見たのである。ダリは、偏執狂の研究で世に出ようとしていたフランス人の精神分析学者ジャック・ラカンと二人三脚のようにして自ら「偏執狂的(パラノイアック)=批判的(クリティック)」と称する方法を唱え、華々しくシュルレアリスム美術の世界へ乗り出そうとした。
ハーヴァード大学を出て、ニューヨークでマルセル・デュシャンに出会い、彼についてパリに渡ったジュリアン・レヴィは、シュルレアリストたちと深く関わりながら、ダリを発見した。ダリの初期の代表作《記憶の固執》を買ったのは彼である。レヴィは、一九三一年、ニューヨークに画廊を開き、そして誰よりも先にダリを売り出そうとした。三〇年代のニューヨークにおいて、シユルレアリストといえばダリのことであり。ダリといえはシュルレアリストのことだったのである。
自慰の習慣と痙攣(けいれん)的な哄笑の発作から逃れられぬ「患者」ダリを、愛人にして聖母、聖母にして救世主たるガラは看(み)続けたようだ。「私と狂人との唯一の違いは、私が狂人ではないことだ」とダリはうそぶいた。こうしてダリは「狂っていない狂人」として三〇年代のニューヨークに君臨した。
ニューヨークでのダリの派手な言動をパリで耳にしたブルトンは、さすがに彼に対して嫌気が差してきたらしい。三六年に「ダリの症例」なる文章を書いて、その作品に早くも否定的な見方を示し始めた。その彼がダリを《Avida Dollars》(ドル亡者)として切り捨てたのは、一九四二年のことである。Salvador Daliの名前を構成するアルファベットを並びかえて、いわゆるアナグラムとして作りあげたのである。「アヴィダ・ドラルス」と発音する向きもあるが、ブルトンがこの言葉を使用したのは、ニューヨークで創刊したシュルレアリスム機関誌においてであるから、やはり流布した英語の発音「アヴィダ・ダラーズ」と記しておくのが妥当であろう。ヨーロッパ大陸での第二次世界大戦勃発を機に続々とニューヨークに亡命したシュルレアリストたちによって、ダリの王位は奪われた。四〇年代には、ダリは少なくともニューヨークにおいてすでに過去の人になりつつあった。
戦中から戦後にかけてニューヨークに台頭した「抽象表現主義」と呼ばれることになるアメリカの新しい芸術動向の理論的指導者の役割を果たした美術批評家、クレメント・グリーンバーグは、しばしば「良いフェルメール」と「悪いダリ」という表現を使った。ダリの作品に「良い」ものはひとつもないという認識の上に立っていたのである。ところが、そのダリほどフェルメールを高く評価した画家もいなかったのであるから、皮肉といえば皮肉なものである。ダリは生涯フェルメールにこだわり続けた。
さて、問題は「贋作(がんさく)」ということである。ほかならぬフェルメールの贋作事件――ハンス・フォン・メーヘレンという男が、フェルメールの《エマオのキリスト》という作品として美術館に飾られていたのを自分の作であると告白した――は有名だが、フェルメールの研究家がこれを「フェルメールの最高傑作」と呼んでいたのだから問題は厄介である。実際、美術の歴史は、とりもなおさず真贋問題の歴史であるといっても過言ではないほどである。この日本でも最近、イタリアの比較的名もない画家の作品を下敷きにして官製の賞まで貰いそうになった画家の事件があったが、ここではルーベンスの問題にいささか触れておきたい。
本書のなかで、あくどいやり口のためについに故国ベルギーの官憲に捕まった主人公のアート・ディーラーに対して、ピカソやダリやウォーホルが芸術なのか? と吐き捨てた予審判事が、「ルーベンスは芸術家だ」と断言するくだりがある。これをフランドル(ベルギー)出身の芸術家に対する愛国心にみちた素人的発言と簡単に片づけることもできないわけではないが、このくだりに思わず苦笑を禁じえなかったのは私ひとりだけではあるまい。というのも、この日本で「ルーベンス問題」が起きていたからである。
要はこういうことである。一九七八年に上野の国立西洋美術館が一億五千万円で購入した《ソドムを去るロトとその家族》という作品が、一九九四年の段階でルーベンスのオリジナルでないことがはっきりした。同名作品がアメリカの美術館に二点あり、さらに一九九一年のロンドンのオークションにもう一点出たから、じつに《ソドムを去るロトとその家族》という作品に四つのヴァージョンがあることがわかったのである。オークションに出た一点を除いて、あとの三点が国立西洋美術館に集められ、X線写真や赤外線写真、顔料の化学的分析や技法などによって徹底的に比較検討された。その結果、アメリカの一点がルーベンスのもの、アメリカにあるもう一点がルーベンス工房によるもの、東京の作品が工房以外で制作されたものとの結論が出されたのである。
ルーベンスはヨーロッパを舞台に大活躍した十七世紀を代表する画家だが、何人もの助手や徒弟のいる工房を構えていた。だからその制作法には幾通りもの可能性があるわけで、一点の作品に一人の芸術家の名前だけが必然的に結びつくわけではない。ルーベンス作品の「作者」名には、したがって「ルーベンス」「ルーベンスおよびルーベンス工房」あるいは「ルーベンス工房」の三通りがあるわけだが、それにしても「工房以外で制作された」とはどういうことだろうか。当時の国立西洋美術館館長の「すばらしい模作だ」との名言(!)によって、この「ルーベンス問題」は一件落着、つまりはうやむやのままに放置されてしまったのだが、「ルーベンスは芸術家だ」ということはまぎれもない事実であるにしても、問題そのものはルーベンスからダリまでほとんどまっすぐにつながっているといわなければならない。
これとよく似た事件が、もうひとつ日本で起きたことがある。一九九三年にマーク・コスタビのものだと思われていた三十点の作品が、彼の工房で働いていた画家とセールスマンが共謀してでっちあげたものだということが判明した。しかもそれらがすべて日本の販売会社に引き取られ、すでにうち二点が日本人に買われていた。販売会社は、真相を打ち明けずに絵を回収しようとしたが、当の客が「気に入っている」というので、手直ししたいと申し出て絵を送ってもらい、来日したコスタビがサインの部分だけを書き直して返送したというのである。
コスタビも自分の工房を、あのウォーホルを真似て「ファクトリー」と呼んでいた。マス・メディアによって流布されるスターの写真やコマーシャル・アートなどをそのまま色彩処理して同一画面に並べるシルクスクリーンの技法による制作で、ポップ・アートの旗手として時代の先端に躍り出たウォーホルだが、じつはシルクスクリーンそのものの制作に携わっていたのは別の人物だった。ウォーホルは、ただ指示するだけだったのである。コスタビもいつしか自分で絵を描かなくなり、サインというかたちで意図的に関与しているか否かだけが問題になった。形としては、ルーベンス工房の場合とほとんど変わらないといってもいいかもしれない。人は、昔も今も、ルーベンスの絵である、コスタビの絵である、そしてダリの絵であるという「信仰」に金を払うのだ。
本書は、そうした「信仰」を手玉に取り、それを徹底的に玩(もてあそ)んだ、スケールの大きなアート・ディーラーの物語である。詐欺師といえば詐欺師であるには違いないが、語り口のうまさ、正直さに、読者は彼を決して嫌いになることはできまい。「ドル亡者」という言葉は、ブルトンによってダリに与えられた極め付きの蔑称だが、しかし「ドル亡者」はまず誰よりもこの語り手であり、そして彼に群がる顧客たちであろう。ダリとガラの「ドル亡者」ぶりの実態は、本書に生々しく描かれているところがあるけれども、依然としてよく見えてこない。ガラのあくどいマネージャーぶりはしばしば伝えられるところだが、ダリは意外に恬淡(てんたん)としていたという話もある。
いずれにせよ、戦後のダリ、というより晩年に近いダリの活動の実態は、これまでほとんど明らかにされてこなかった。最後に「イシドロ・ベア」というダリの贋作(がんさく)者が登場するけれども、さもありなんという気がする。後期から晩年にかけてのダリのものとされる作品は、初期のものに比べると、とても弱いのである。ダリが真に作品を生み出せなくなった頃から、世にダリの石版画(リトグラフ)がやたらと出回り始めた。八〇年代バブルの頃にデパートや街で声をかけられた経験がある。ダリを買いませんかというのである。そんなことを思い出しながら、本書を一気に読んだ。
なお、『贋作王ダリ』という本書の原題は、『ダリと私――シュールレアルな物語』である。「贋作王」とは刺激的な表現だが、ダリにちょっと気の毒な感じがしないでもない。
【この解説が収録されている書籍】
カダケスにいるダリが、詩人ポール・エリュアールの連れてきたロシア人の妻ガラと運命の出会いをしたのは一九二九年夏のことである。たちまち意気投合した二人を置いて、エリュアールはひとりパリに戻った。そしてこの年の十一月にダリはアンドレ・ブルトンの紹介で初めてパリで個展を開き、シュルレアリストとして認知された。アンドレ・マッソンやアントナン・アルトーと袂(たもと)を分かったシュルレアリスムの総帥が、この二十五歳のスペイン人画家に新たな可能性を見たのである。ダリは、偏執狂の研究で世に出ようとしていたフランス人の精神分析学者ジャック・ラカンと二人三脚のようにして自ら「偏執狂的(パラノイアック)=批判的(クリティック)」と称する方法を唱え、華々しくシュルレアリスム美術の世界へ乗り出そうとした。
ハーヴァード大学を出て、ニューヨークでマルセル・デュシャンに出会い、彼についてパリに渡ったジュリアン・レヴィは、シュルレアリストたちと深く関わりながら、ダリを発見した。ダリの初期の代表作《記憶の固執》を買ったのは彼である。レヴィは、一九三一年、ニューヨークに画廊を開き、そして誰よりも先にダリを売り出そうとした。三〇年代のニューヨークにおいて、シユルレアリストといえばダリのことであり。ダリといえはシュルレアリストのことだったのである。
自慰の習慣と痙攣(けいれん)的な哄笑の発作から逃れられぬ「患者」ダリを、愛人にして聖母、聖母にして救世主たるガラは看(み)続けたようだ。「私と狂人との唯一の違いは、私が狂人ではないことだ」とダリはうそぶいた。こうしてダリは「狂っていない狂人」として三〇年代のニューヨークに君臨した。
ニューヨークでのダリの派手な言動をパリで耳にしたブルトンは、さすがに彼に対して嫌気が差してきたらしい。三六年に「ダリの症例」なる文章を書いて、その作品に早くも否定的な見方を示し始めた。その彼がダリを《Avida Dollars》(ドル亡者)として切り捨てたのは、一九四二年のことである。Salvador Daliの名前を構成するアルファベットを並びかえて、いわゆるアナグラムとして作りあげたのである。「アヴィダ・ドラルス」と発音する向きもあるが、ブルトンがこの言葉を使用したのは、ニューヨークで創刊したシュルレアリスム機関誌においてであるから、やはり流布した英語の発音「アヴィダ・ダラーズ」と記しておくのが妥当であろう。ヨーロッパ大陸での第二次世界大戦勃発を機に続々とニューヨークに亡命したシュルレアリストたちによって、ダリの王位は奪われた。四〇年代には、ダリは少なくともニューヨークにおいてすでに過去の人になりつつあった。
戦中から戦後にかけてニューヨークに台頭した「抽象表現主義」と呼ばれることになるアメリカの新しい芸術動向の理論的指導者の役割を果たした美術批評家、クレメント・グリーンバーグは、しばしば「良いフェルメール」と「悪いダリ」という表現を使った。ダリの作品に「良い」ものはひとつもないという認識の上に立っていたのである。ところが、そのダリほどフェルメールを高く評価した画家もいなかったのであるから、皮肉といえば皮肉なものである。ダリは生涯フェルメールにこだわり続けた。
さて、問題は「贋作(がんさく)」ということである。ほかならぬフェルメールの贋作事件――ハンス・フォン・メーヘレンという男が、フェルメールの《エマオのキリスト》という作品として美術館に飾られていたのを自分の作であると告白した――は有名だが、フェルメールの研究家がこれを「フェルメールの最高傑作」と呼んでいたのだから問題は厄介である。実際、美術の歴史は、とりもなおさず真贋問題の歴史であるといっても過言ではないほどである。この日本でも最近、イタリアの比較的名もない画家の作品を下敷きにして官製の賞まで貰いそうになった画家の事件があったが、ここではルーベンスの問題にいささか触れておきたい。
本書のなかで、あくどいやり口のためについに故国ベルギーの官憲に捕まった主人公のアート・ディーラーに対して、ピカソやダリやウォーホルが芸術なのか? と吐き捨てた予審判事が、「ルーベンスは芸術家だ」と断言するくだりがある。これをフランドル(ベルギー)出身の芸術家に対する愛国心にみちた素人的発言と簡単に片づけることもできないわけではないが、このくだりに思わず苦笑を禁じえなかったのは私ひとりだけではあるまい。というのも、この日本で「ルーベンス問題」が起きていたからである。
要はこういうことである。一九七八年に上野の国立西洋美術館が一億五千万円で購入した《ソドムを去るロトとその家族》という作品が、一九九四年の段階でルーベンスのオリジナルでないことがはっきりした。同名作品がアメリカの美術館に二点あり、さらに一九九一年のロンドンのオークションにもう一点出たから、じつに《ソドムを去るロトとその家族》という作品に四つのヴァージョンがあることがわかったのである。オークションに出た一点を除いて、あとの三点が国立西洋美術館に集められ、X線写真や赤外線写真、顔料の化学的分析や技法などによって徹底的に比較検討された。その結果、アメリカの一点がルーベンスのもの、アメリカにあるもう一点がルーベンス工房によるもの、東京の作品が工房以外で制作されたものとの結論が出されたのである。
ルーベンスはヨーロッパを舞台に大活躍した十七世紀を代表する画家だが、何人もの助手や徒弟のいる工房を構えていた。だからその制作法には幾通りもの可能性があるわけで、一点の作品に一人の芸術家の名前だけが必然的に結びつくわけではない。ルーベンス作品の「作者」名には、したがって「ルーベンス」「ルーベンスおよびルーベンス工房」あるいは「ルーベンス工房」の三通りがあるわけだが、それにしても「工房以外で制作された」とはどういうことだろうか。当時の国立西洋美術館館長の「すばらしい模作だ」との名言(!)によって、この「ルーベンス問題」は一件落着、つまりはうやむやのままに放置されてしまったのだが、「ルーベンスは芸術家だ」ということはまぎれもない事実であるにしても、問題そのものはルーベンスからダリまでほとんどまっすぐにつながっているといわなければならない。
これとよく似た事件が、もうひとつ日本で起きたことがある。一九九三年にマーク・コスタビのものだと思われていた三十点の作品が、彼の工房で働いていた画家とセールスマンが共謀してでっちあげたものだということが判明した。しかもそれらがすべて日本の販売会社に引き取られ、すでにうち二点が日本人に買われていた。販売会社は、真相を打ち明けずに絵を回収しようとしたが、当の客が「気に入っている」というので、手直ししたいと申し出て絵を送ってもらい、来日したコスタビがサインの部分だけを書き直して返送したというのである。
コスタビも自分の工房を、あのウォーホルを真似て「ファクトリー」と呼んでいた。マス・メディアによって流布されるスターの写真やコマーシャル・アートなどをそのまま色彩処理して同一画面に並べるシルクスクリーンの技法による制作で、ポップ・アートの旗手として時代の先端に躍り出たウォーホルだが、じつはシルクスクリーンそのものの制作に携わっていたのは別の人物だった。ウォーホルは、ただ指示するだけだったのである。コスタビもいつしか自分で絵を描かなくなり、サインというかたちで意図的に関与しているか否かだけが問題になった。形としては、ルーベンス工房の場合とほとんど変わらないといってもいいかもしれない。人は、昔も今も、ルーベンスの絵である、コスタビの絵である、そしてダリの絵であるという「信仰」に金を払うのだ。
本書は、そうした「信仰」を手玉に取り、それを徹底的に玩(もてあそ)んだ、スケールの大きなアート・ディーラーの物語である。詐欺師といえば詐欺師であるには違いないが、語り口のうまさ、正直さに、読者は彼を決して嫌いになることはできまい。「ドル亡者」という言葉は、ブルトンによってダリに与えられた極め付きの蔑称だが、しかし「ドル亡者」はまず誰よりもこの語り手であり、そして彼に群がる顧客たちであろう。ダリとガラの「ドル亡者」ぶりの実態は、本書に生々しく描かれているところがあるけれども、依然としてよく見えてこない。ガラのあくどいマネージャーぶりはしばしば伝えられるところだが、ダリは意外に恬淡(てんたん)としていたという話もある。
いずれにせよ、戦後のダリ、というより晩年に近いダリの活動の実態は、これまでほとんど明らかにされてこなかった。最後に「イシドロ・ベア」というダリの贋作(がんさく)者が登場するけれども、さもありなんという気がする。後期から晩年にかけてのダリのものとされる作品は、初期のものに比べると、とても弱いのである。ダリが真に作品を生み出せなくなった頃から、世にダリの石版画(リトグラフ)がやたらと出回り始めた。八〇年代バブルの頃にデパートや街で声をかけられた経験がある。ダリを買いませんかというのである。そんなことを思い出しながら、本書を一気に読んだ。
なお、『贋作王ダリ』という本書の原題は、『ダリと私――シュールレアルな物語』である。「贋作王」とは刺激的な表現だが、ダリにちょっと気の毒な感じがしないでもない。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする