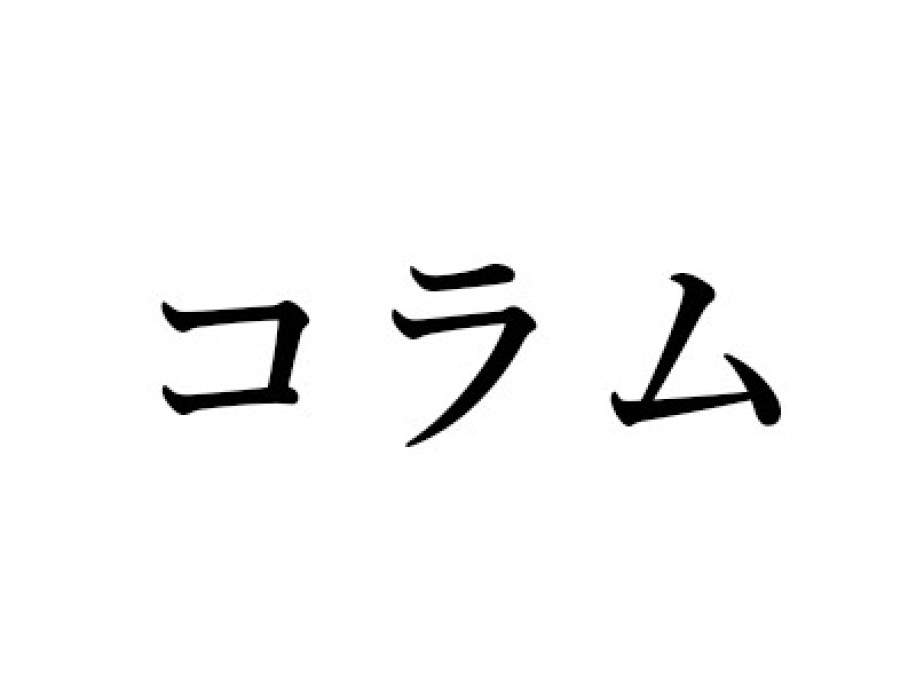書評
『女中奉公ひと筋に生きて』(草思社)
おしん
幸田文さんの書いたものを読み、ねじめ正一さんの『熊谷突撃商店』を読み、それからこの吉村きよさんの『女中奉公ひと筋に生きて』(草思社)を読んでいて、どれも懐かしく、かつどこかで聞いたことがあるんだよなと思った。いろいろ考えたあげく、なんだそうか、と気づいた。こういう話は、母親や祖母や親戚のおばちゃんから、イヤというほど聞いて、実際イヤになり、できるなら忘れようと思ったのだった。
父方の祖母が亡くなってから、もう十数年、いや二十年近くたった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1996年頃)。高橋家のトップに君臨した独裁者の祖母(祖父はぼくが赤ん坊の時に亡くなり、ぼくには記憶がない)のことを書きはじめるときりがないのでパス。その祖母が、脳溢血(のういっけつ)で急死。真夏のある日、大阪豊中の実家で葬儀が執り行われた。父が病欠し、ぼくが喪主となった(この葬式が終わって帰京した夜、この豊中の実家に住んでいた叔母が急死して電報が届いた。帰った親戚はみんな――ぼくも――祖母死去の電報がなにかの間違いでもう一回届いたと勘違いしたほどだった)。その席で、ぼくは見知らぬ老婆から声をかけられた。「源一郎さまですか?」「はい」「ああ、懐かしい。お祖父さまにそっくりでいらっしゃいますわ」。
その方は、高橋家の女中頭をなさっていたのである。
その昔、高橋家には女中頭がいて、その下に七、八名の女中たちがいた。祖父や祖母や父やその兄弟には一人一人専属の女中がいたそうである。赤ん坊のぼくには専属の乳母がいた。
残念ながら、ぼくはなにも覚えていない。間もなく、高橋家は没落したからである。よって、「高橋家興亡史」はもっぱら、祖母・叔母・母たち(高橋家の女たち)のする話によって知った。
女たちは寝る暇もなく働き、その一方、男たちはみんな、嘘つきで、女好きの怠け者ばかり。
もちろん被害を受けた当事者の話だから三割か五割、割り引いたって、ひどいなあと子供心に思ったものだった。『女中奉公』の吉村きよさんは、三歳で父と死別し、小さい頃からほとんど学校にも通えず、子守からはじまる仕事に精を出し、その後結婚するが夫は愛人と出奔、子供四人を抱えて働き続ける。わたしの母親より四つ年下だ。
この後も、長男が結婚するまでの十五年間、わたしは無我夢中で働きつづけました。傍目には苦労したように見えるでしょうが、辛いとか、苦しいとか、感じる暇さえなかったというのが、正直な気持ちです。つまらないことを考える暇などなくて、かえってわたしは幸せだったように思います。
とか
昔からの習慣が染みついて、いまでもわたしの睡眠時間は二、三時間です。
とか
どんな仕事でも、何を言われても、我慢、我慢、我慢、辛抱、辛抱、辛抱と努めてきたので、人が勤まらない家でもわたしは勤まりました。
とか
仕事をしてお金をいただくからには、一日分の金額の倍の仕事をしなくては気がすまない性分なのです。
という吉村さんの生涯はその語り口も含めて、ぼくには懐かしい。
本の帯には「現代版おしん」とあり、確かにこんな「おしん」はたくさんいた。それは「貧乏」や「辛抱」という言葉が生きていた頃で、「貧困」はいまでもあるかもしれないが、もはや「貧乏」は存在しないし、誰も「辛抱」なんかしない。「女中」も「奉公」も遠い世界の言葉となった。ぼくは懐かしいが、弟は懐かしくもなんともないというのである。みなさんは如何?
ALL REVIEWSをフォローする