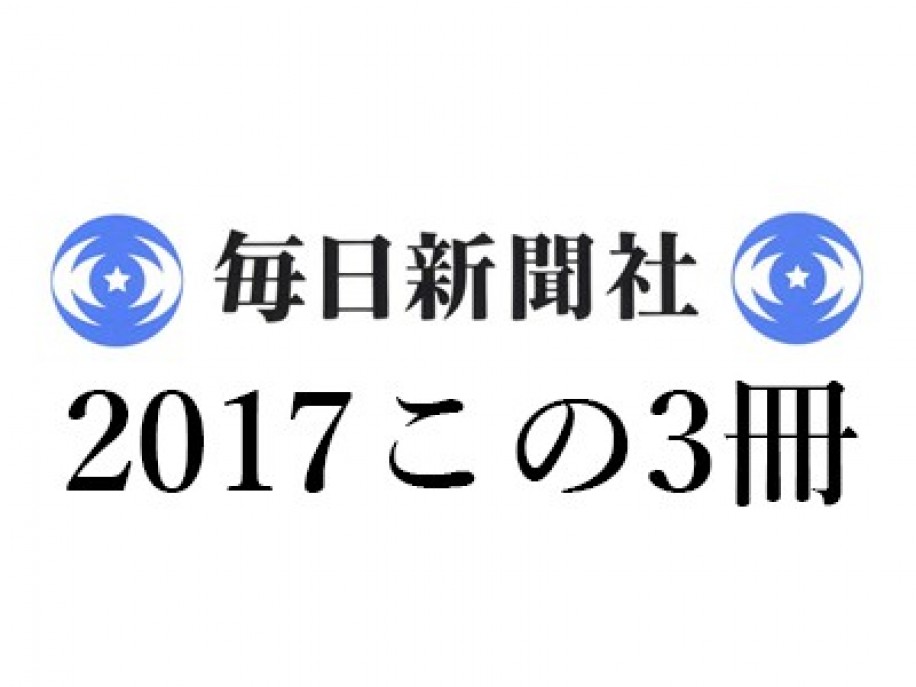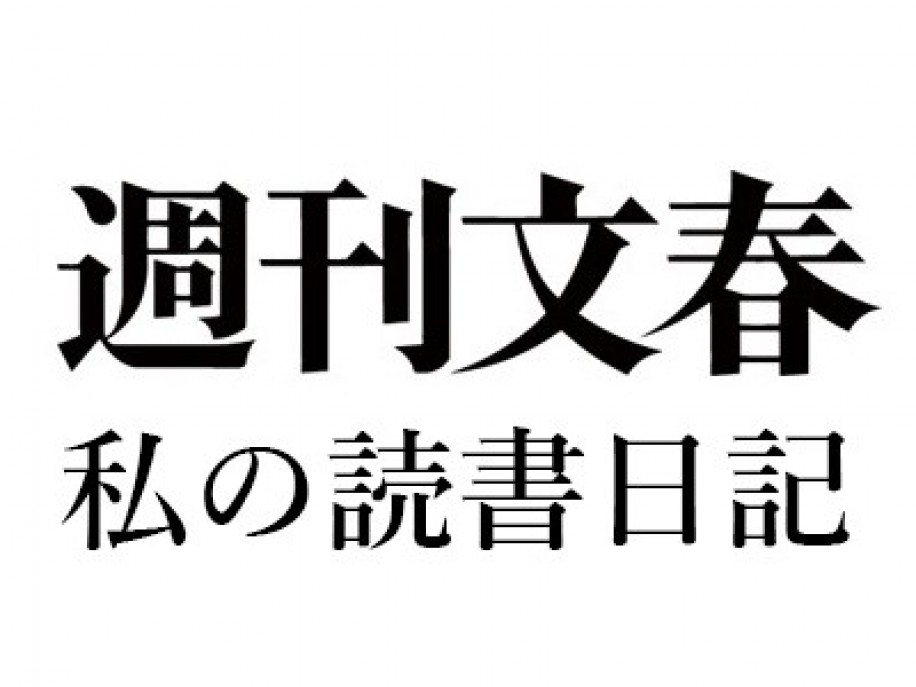書評
『同窓会の社会学―学校的身体文化・信頼・ネットワーク』(世界思想社)
記憶とノスタルジア
『同窓会の社会学』を読む
同窓会に出ておもしろいことの一つは、意外性に出合うことではなかろうか。学生時代は、いるかいないかさえはっきりしなかった女子が、華やかな有閑夫人に変貌していて、エッとうなること。逆に昔のモテ男が、見る影もなくなっている場合もある。昔、抱いた羨望と嫉妬感情の怨み? をはらしたりもできる。
そんなよこしまな感情を持って同窓会に出席していても、最後に運動会や対抗戦で必ず唄った応援歌を全員が肩を組んで大声で唄うと、「特別な性質がしみこんだ」(一六頁)過去が現前し、目頭が熱くなる。何十年も前の学校生活がすべて楽しかったわけではないにもかかわらずに、である。いったいこの感動は何に由来するのか。
同窓会会場は「疑似学校空間」であり、「運動会空間」となって集合的記憶が再生され、ノスタルジアが創出されるからだ、と本書(黄順姫(ファンスンヒー)『同窓会の社会学――学校的身体文化・信頼・ネットワーク』世界思想社、二〇〇七年)はいう。
調査校は福岡県立修猷館高校。藩校から始まる名門校で、広田弘毅元首相(一八七八~一九四八)や山崎拓衆議院議員などの母校。面接調査、学校史・文集の分析、質問紙調査によって、同窓会ウォッチを十数年も続けた成果である。
本書は学校愛の分析だけにとどまらない。同窓生の信頼を通じての人脈資本(社会関係資本)の形成と蓄積についてまで対象を広げている。
ある卒業生は、学校時代は目立たなく、友人も少なかった。しかし、卒業後同窓会活動に熱心に取り組み、しだいに同窓生の信頼を獲得する。彼が施設をつくりかけているといううわさが同窓会ネットワークで広がると、有形無形の援助がひきもきらなかった、という。
「同窓生の過去の学校は、彼らの現在の学校であり、未来に開かれた学校でもある」(一八頁)と著者はいう。名フレーズである。
週刊東洋経済 2007年11月3日号
1895(明治28)年創刊の総合経済誌
マクロ経済、企業・産業物から、医療・介護・教育など身近な分野まで超深掘り。複雑な現代社会の構造を見える化し、日本経済の舵取りを担う方の判断材料を提供します。40ページ超の特集をメインに著名執筆陣による固定欄、ニュース、企業リポートなど役立つ情報が満載です。
ALL REVIEWSをフォローする