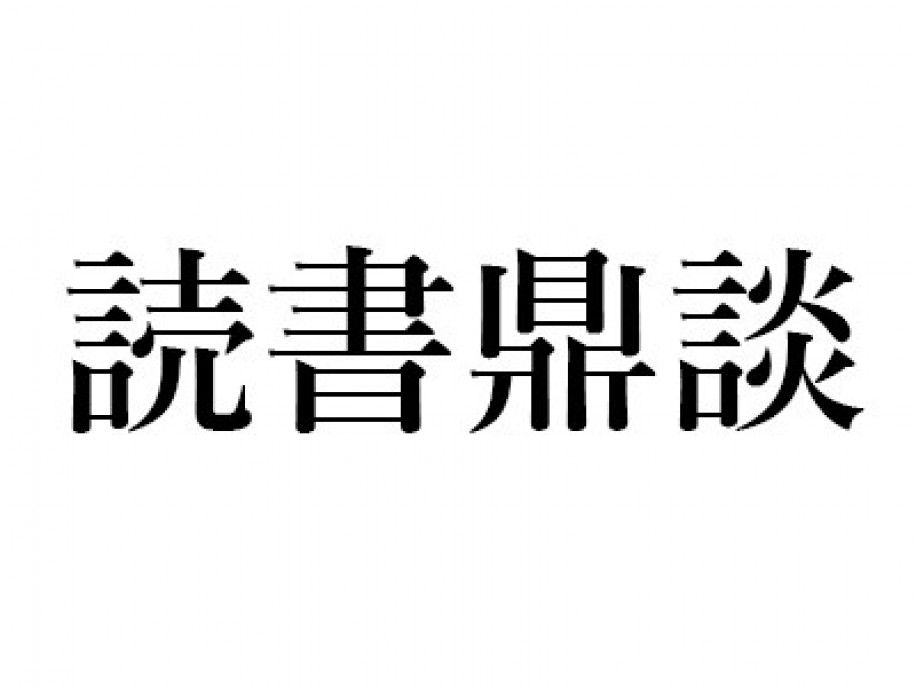書評
『大学講義 野望としての教養』(時事通信社)
知の大道芸人
『野望としての教養』を読む
大学教授などによる学問や教養、読書の勧めを読んでいて、ふとこんな疑問を感じたことはないだろうか。猫も杓子も学問や読書になびけば、本も売れるし、あなた方を尊敬もするでしょう。だとしたら、学問や教養の勧めという啓蒙主義や教養をすべての国民にという国民的教養論は、あなた方の業界利害に基づくイデオロギーなのではないか、と。
奇才浅羽通明は、はっきりとこう言っている。「教養」など必要としないのが多数の人々であり、「教養」なくしてはいられないのは少数の人々である。自分はその少数の人々に向かってしゃべり、書くのだ、と。本書(浅羽通明『野望としての教養――大学講義』時事通信社、二〇〇〇年)は、そうした少数者の間でベストセラーとなった著者の『大学で何を学ぶか』(幻冬舎文庫)の続編である。
法政大学での講義を元にまとめただけに、著者の語り口が生かされ、さながら知のライブ。最後まで一気に読ませる筆力と語り口に感心する。
小説『浮雲』の主人公内海文三を「文III」君と名付けたり(この意味については本書で)、日本の小説の題名は個人名が少なく、『デイヴィッド・コパフィールド』(ディケンズ)が戦前には『男の一生』となり、『細雪』が英訳では The Makioka Sisters に変わってしまう不思議さなど、数々の創見に満ちている。また、著者はマイナー本の名作の発掘と紹介がとてもうまい。わたしは後で読んでみたいと、メモを取ったほどである。
セーフティネットとしての教育産業論、つまり暗くてダサい社会的不適応者の収容所が大学院であるなどの指摘は耳が痛いが、あすの大学と人文系の学問を考えていく上で重要で率直な指摘である。著者の姿に、化石化した啓蒙知識人や大学知識人とは異なった、躍動感に溢れる大道芸人型知識人を思い浮かべてしまう。ギリシャの哲学者たちも、そもそもは著者のような知の大道芸人だったのではないだろうか。
初出メディア
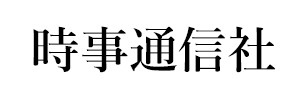
時事通信社 2000年8月6日ほか
ALL REVIEWSをフォローする