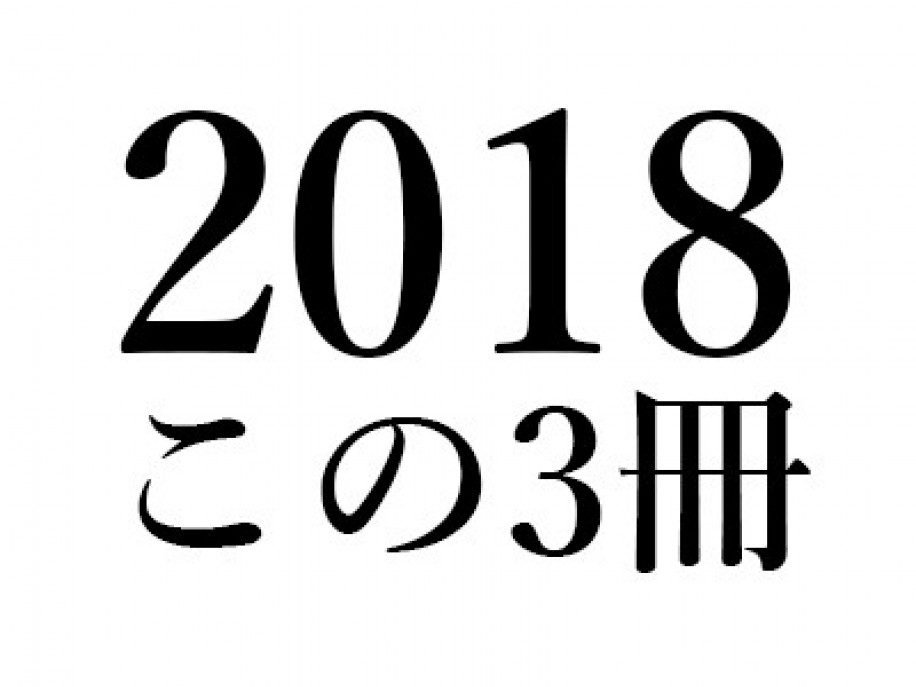書評
『創造と狂気の歴史 プラトンからドゥルーズまで』(講談社)
心の遺物のパラダイム移行を鮮明に
二〇世紀を代表する精神病理学者ユングは「精神のまともな人がいれば見せてもらいたい。その人を治してあげよう」と語ったという。誰でも多少は精神病をかかえているというなら、凡人にはホッとするところがある。もっとも、本書がとり上げるのは、凡人ならざる人物である。古代ギリシアの頃から、「狂気の混じらない天才はかつて存在しなかった」と指摘されている。プラトンもアリストテレスも「創造と狂気」には深い結びつきがあることに気づいていた。プラトンは神々に由来する狂気によって偉大なる詩人が生まれると語り、アリストテレスは創造力をメランコリー(うつ病)と結びつける論者だった。
このような狂気の背後にはもともと神々と人間を仲介するダイモーンがいると信じられていた。だが、唯一神を崇(あが)めるキリスト教が受容されるにつれ、ダイモーンは悪霊として追放される。悪霊が人間にまとわりつくかぎり、うつ病のような怠惰になり、創造と結びつくことはなかった。千年にわたる中世社会のなかで、ダイモーンは斥(しりぞ)けられながらも、畏怖(いふ)されていた。はたして、近代はそれを払拭(ふっしょく)することができるのだろうか。
デカルトといえば、コギト(われ思う)によって近代人の主体を確立したかのように見なされている。だが、彼の「理性」は「理性的霊魂」であり、狂気(ダイモーン)に取り憑(つ)かれているかもしれないという疑いを通じて、「理性」を取り出してくるという。デカルトの人生を病跡学からながめれば、自分が世界とうまく調和できないという分裂気質があるらしい。
カントもまた、ルソーのような病的人物の考えにふれることによって、狂気に陥るかもしれないという「理性の不安」をかかえるようになったという。彼は狂気に対する防衛を試み、狂気を隔離して閉じ込める哲学を体系化したのである。
このような解釈は、フーコー、ラカン、デリダ、ドゥルーズなどのフランスの現代思想家たちが切り開いた地平である。デカルトやカントの近代的主体は、確固たるものからほど遠く、啓蒙(けいもう)的理性には狂気が巣くっていることに注目したのである。
さらに、ヘーゲルにとって、狂気は人間の理性に対する「否定性」であり、その非理性(狂気)を乗り越えようとして弁証法を磨きあげる。「正」「反」「合」の運動をくりかえせば非理性(狂気)は最終的に克服されるという期待があった。
かつて精神分裂病とよばれた統合失調症は近代の病だという。その人は「世界のなかの事物のもとに安心して逗留(とうりゅう)することができない」(ビンスワンガー)のである。その意味で詩人ヘルダーリンは統合失調症者の最初の事例であるという。しかも、狂気の克服を説いたヘーゲルの親友であり、克服できない狂気を身をもって示したのだから、歴史の皮肉と言うしかない。
存在そのものにこだわるハイデッガーは「狂気のなかで<存在>という深淵(しんえん)」をのぞかせる詩人ヘルダーリンにことさら感化されたという。それは哲学の「統合失調症」化でもあった。
さらには、狂気の芸術創造という恩恵に注目しながら精神病論を築いたラカン、「不可能なもの」は一様ではなく差異をはらむ複数のものとして脱構築するデリダ、狂人嫌いでありながら統合失調症のプロセスに興味をいだき「決定的な出来事」からの逃走を強調したドゥルーズなどの現代思想が論じられる。
「創造と狂気」の関係から出土した心の遺物について、その考古学調査を試行しつつ、パラダイムの移行を鮮明に浮かび上がらせる。読み応えのある精神病理学の歴史書である。
ALL REVIEWSをフォローする