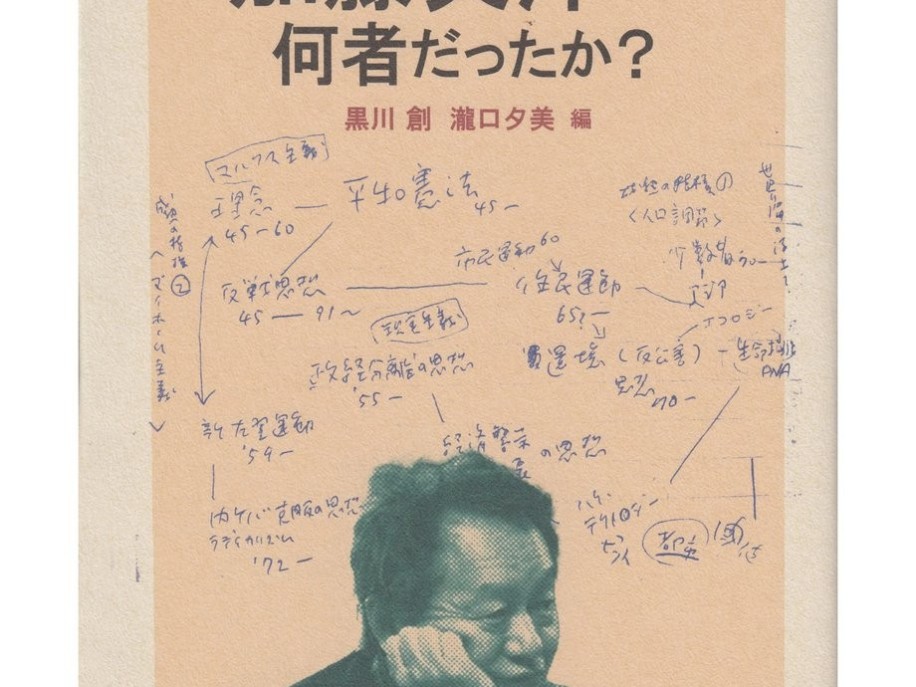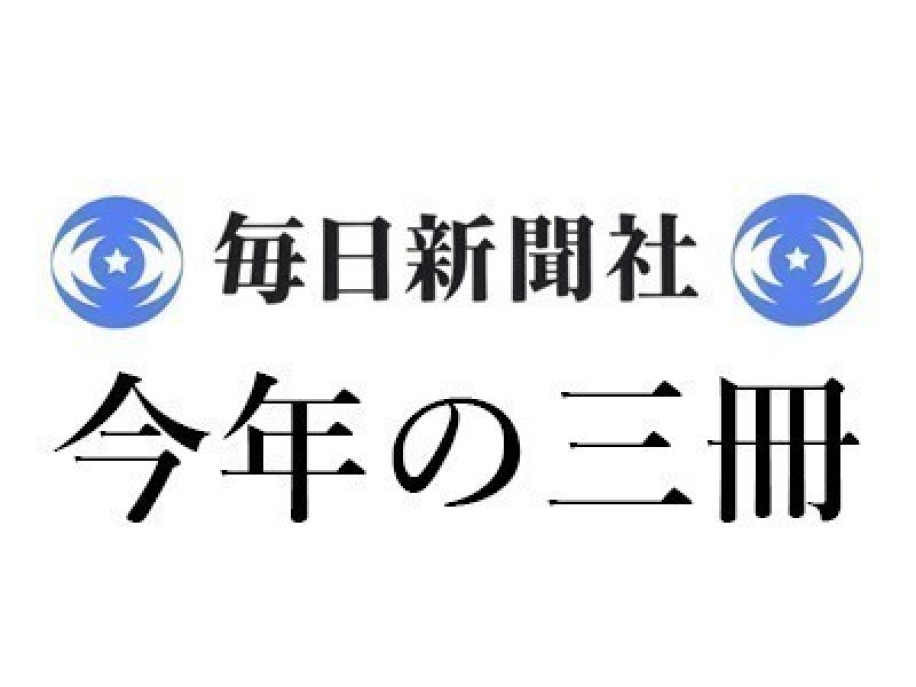書評
『エッフェル塔のかけら―建築家の旅』(紀伊國屋書店)
空間のホメオスタシス
大道芸人や観光客が集う出会いの場を提供しているなだらかなスロープを下り、カラフルな空調設備がむき出しになっている入口から広々としたホールに足を踏み入れると、その片隅にはシャイヨー宮とならぶ優れたシネマテークがあり、ファサードにとりつけられた透明なカプセルのなかを抜けていく近未来的なエスカレーターを昇れば、堅苦しい研究者の資格など抜きで誰もが自由に閲覧できるほぼ全冊開架式の図書館や、斬新な企画で膨大な数の観客を動員する美術館があり、パリの屋根を見渡すのに最適の展望台とカフェテリアがある。いまや誰知らぬ者のないパリの複合文化施設、ポンピドゥー・センター。だがほんの二十年前、くすんだ壁の連なる古いパリの中心部にはじめてこの建物が姿を現わしたときには、十九世紀末、シャン・ド・マルスに地上三百メートルの鉄塔が出現した際にも匹敵する論議を呼んだのだった。ところで、さまざまな批判の対象となったこの「歴史的建造物」の設計に、若い日本の建築家がかかわっていたことを知る者はあまり多くないだろう。本書『エッフェル塔のかけら』は、二十代の青春の一部をポンピドゥー・センター建設に捧げるというまことに稀有な幸運に恵まれた著者の、清新なエッセイ集である。一九七四年当時、困難な設計に携わっていた若い建築家たちに、著者は「多国籍部隊」といういくらか物騒な呼称を与えている。イタリア人レンゾ・ピアノ、イギリス人リチャード・ロジャースを代表格として、スタッフは日本人、イギリス人、スイス人、オーストリア人、イタリア人で構成され、驚くべきことに設計の初期段階を除いてフランス人の姿はなかったという。保守的な空気の濃かったパリの建築風土を揺るがす建物の、妙な権威主義に陥らない開放的な性質は、すでに青写真の段階で決定されていたのだ。本書はだから、巨大事業に参加した戦士たちとの熱い共闘の記録でもあって、その友情の深さと持続は、もしかすると山田宏一の『友よ映画よ』(ちくま文庫)に再現された「カイエ・デュ・シネマ」編集部のそれに匹敵するかもしれない。伝統的なフランス映画に異を唱えたシネフィルたちと、過酷な条件をつぎつぎに克服しながら新しい建築の実現をめざす「多国籍部隊」には、どこか通ずるものがある。
とはいえその筆に戦闘的なところはまったくない。建築のみならず、世界各地の都市や旅の記憶がちりばめられた七章におよぶ部材を、リベットの跡すら残さずなめらかに接合しているのは、過去への安易な寄り掛かりではなく、ゆるやかな時間の手触りであり、距離をもってそれを慈しむ節度である。ひとつの風景のなかに固定される建造物の作り手が、嬉々として移動を引き受ける逆説のなんと心地よいことか。土地の匂いと空間に身を置いた身体の記憶が、さらに文学や絵画の印象と交錯する。五感のすべてが身体の周囲に見えない梁をめぐらし、思考にのびやかな運動の場を与え、それらがいつしか具体的な建築への意志に収斂していく。そしてその思考の土台にあるものこそ、ポンピドゥー・センターなのだ。
重要なのは、設計に携わった当人が、その後も映画館の増設や大規模な展覧会の展示を担当しながら、子どもの成長を追う親のような目でセンターがひとり立ちしていく様子を見守ってきたことだろう。「ポンピドゥー・センターは歴史に残るすぐれた建築なのか、という問いには答えがない。建築というカテゴリーを越えた別の何かとして考えた方がいいと思う。私自身は、都市の中に重層する新たな場(フィールド)を作り出したメカニズムとでも定義してみた方がいいと最近は考え始めている」と語られた言葉に狂いはない。そして建造物としてのポンピドゥー・センターが、極度に煩雑な集団作業の成果であり、だからこそアノニムなぬくもりを持った場となりえたのだとの認識は、やがて「多国籍部隊」を担った仲間たちとの共同作業の到達点とも言える、関西国際空港旅客ターミナルビルのプロジェクトにつながっていくことになる。
著者の筆が最も高揚するのは、その国際空港のメインターミナルビルの屋根の形状が、内部環境の制御を担当していたエンジニアのアイデアによって一挙に具体化していく経緯をつづった第六章だ。ブランクーシの「空間の鳥」に発想を得たという一・七キロメートルにおよぶエアサイドのウイングのしなやかな動態に接合するには、対称形のアーチは静的に過ぎ、空調制御のダクトを天井に取りつけるのは、屋根の重量やメンテナンスの面から無理が生じる。その窮状を救ったのが、「八〇メートルの一端からジェットエアを天井面に吹き付け、空間断面と天井の形状をエアの拡散と落下に合わせて」創り出すというアイデアを盛り込んだ、共同設計者からの一枚のファクスだった。アーチの頂点が床面の両端から三対二の地点に位置する放物線のなかで一瞬のうちに結合し、最適の解を導いてくれたときの興奮。ここには、すべての思考の「かけら」が空間のホメオスタシスとでも呼ぶべき地平で融合した、ほとんど官能的な悦びがある。
最後に、これら一連の文章が、関西国際空港開港後に起きた大震災の衝撃を経て書き出されていることを明記しておきたい。建築家の存在理由を揺るがしかねない天災後の癒しが、あらたな都市創造ではなく、自身を見つめる文章によって得られたことは、書き手にとっても読み手にとっても、幸福な出来事であった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする