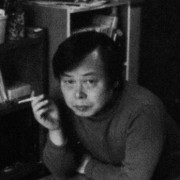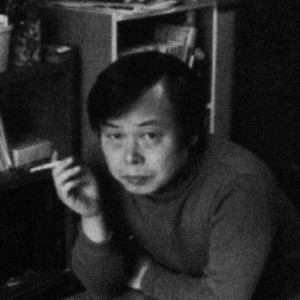書評
『屏風のなかの壺中天』(青土社)
快楽の迷路、隠れているのはだれ?
訳題が『屏風(びょうぶ)のなかの壺中天(こちゅうてん)』とあって、なんとなく好色本のにおい。さしずめ荷風の妾宅(しょうたく)「壺中庵」が思い起こされる。屏風六曲のかげには、不断の宵闇ありて(略)、實に世上の人の窺(うかが)ひ知らざる壺中の天地なれと……
とは荷風の屏風礼賛の弁。
中国の屏風(衝立<スクリーン>)のかげにも、そんないかがわしい戯れを秘めた壺中天が囲われていたのだろうか。台座の上に太い縁で囲まれた衝立は謁見(えっけん)する天子の権威象徴の公的儀式装置である一方、使いようによっては、夜宴に集う客と女たちをひそかに閨房(けいぼう)のかげに隠し、隠すがゆえに鑑賞者ののぞきの欲望をかき立てるエロティックな装置ともなる。
南唐の画家顧こう中(ここうちゅう)はこの手法で横長に画巻のように展開する『韓熈載夜宴(かんきさいやえん)図』を描いた。同じ頃、周文矩(しゅうぶんく)が内容的にほぼ等しい『合楽(ごうらく)図』を描いたが、その発展上に、場面が縦長に重層する『重屏(ちょうへい)図』を描く。前景に碁を囲んでいる男たちの男性サロン、後景の衝立には同じあるじが女たちとくつろいでいる奥の家庭内部。画のなかにまた画がある入れ子構造。すなわち重屏図(ダブルスクリーン)である。
さらに十三世紀の劉貫道(りゅうかんどう)『銷夏(しょうか)図』では衝立の画中画はさらに重層化し、前景にくつろいでいるあるじ、その背後の衝立には彼の公務中の書斎での姿、さらに書斎のなかの衝立に山水画、といったふうに衝立の入れ子構造はだまし絵風に奥行きを深め、あるじの社会活動と私的安息、さらにそれさえ捨てて無人の自然に逃れんとする彼の内心の渇望を表すにいたる。
満族出身の皇帝として政治的には支配者、文化的には漢族文化の所有者であった清の乾隆帝の公私生活における謎めいた挙動にいたるまで、衝立をめぐる隠れん坊遊びは尽きない。故事来歴(著者のいわゆる「テキストの包囲網」)が重層しているので、それ相当の教養が必要とされるが、著者も訳者も「包囲網」を解くべき配慮を周到にめぐらせており、いったん重屏図の魅力にはまったら、幾重にも囲われた衝立の迷路のなかの、俗界を離れた快楽にめぐりあえよう。
朝日新聞 2004年4月11日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする