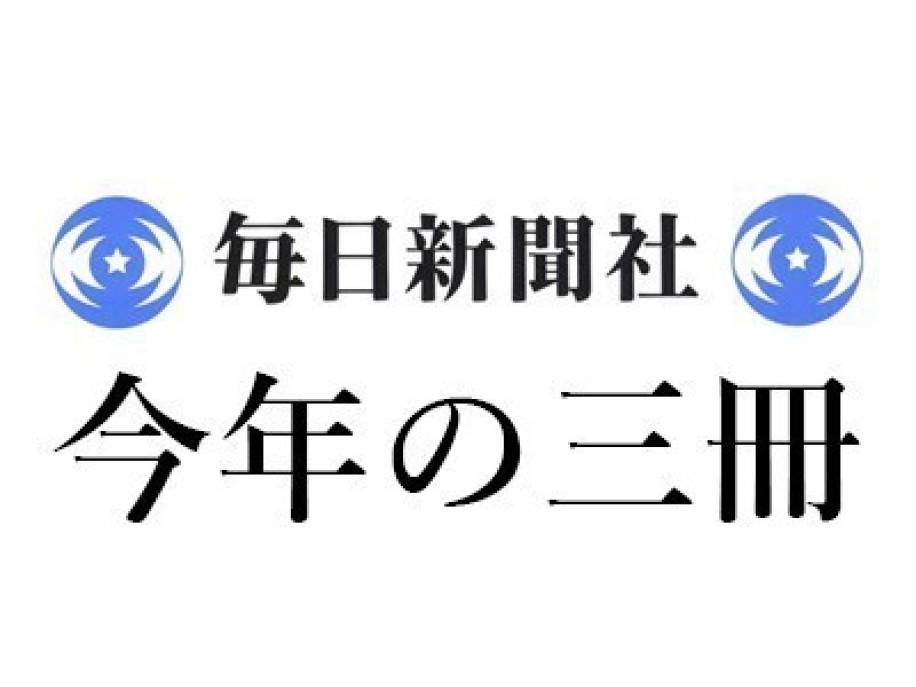書評
『うるわしき日々』(講談社)
綻(ほころ)びる
小島信夫の『うるわしき日々』(読売新聞社)を読んだ。読みながら、この小説についてどう書いたらいいんだろうと思った。書評する人間は、ほんとのところずいぶん悩むだろう。小島信夫は日本でもっとも偉大な現代小説家だから、現代小説のたどり着いた地点について書く――というやり方は当たり前すぎる。
『抱擁家族』をはじまりとして、事実とフィクションの微妙な境界を突き進んで来た連作の意味について書く――のもいまさらなあという気になる。
ぼくは『うるわしき日々』を読みおえた後、作者がこの作品のキーになる言葉をどこかに書いていたような気がして、もう一度最初からパラパラとめくり、三分の一ほど進んだところで傍線をつけたこんな文章を見つけた。
いま現在、彼女は少しずつ、気づかれないことをたのしんでいるように、ほんの僅かずつ綻んできている。綻びつつあるのがうれしいのは、何も人間の顔だけではない、と彼は思った。
ぼくはこの「綻んで」を服が綻ぶという意味、つまり耐用期限が過ぎ解けていく、緩んでいく、という意味だと思った(この少し前に「微笑する」という意味で「綻ぶ」が使われているけれど)。なぜなら、この小説には「綻んで」、つまり緩み、バラバラになっていくものばかりが出てくるからだ。
主人公であり著者である「老作家」は八十歳を越えている。二度目の妻である「老妻」もボケの徴候が出始めている。なにより、この小説のもう一人の主人公である五十四歳の長男は、過度の飲酒から来るコルサコフ氏病症候群で痴呆状態にあり病院や施設を転々としている。「綻んだ」老夫婦がやはり「綻んだ」長男の世話に汲々とする日々。長男が「綻んだ」のはその妻との関係が「綻んだ」ためだったが、老夫婦の関係もいまや年と共に「綻んで」いく。では「綻ぶ」とはどういうことなのだろうか。
高原の道を歩きながら、彼女はもう半分しか彼の話を聞いていないし、そのうち聞くことさえやめたらしかった。それはひどく淋しいことで、絶望的ともいえた。
それに近い経験は度々あった。ただ、得意であり自信の元でもあった高原の中の道でのことであり、根本的なことに関してであった。
「問題は脈絡のことである」
彼は口に出していったかもしれない。山全体に匹敵するくらい、重くて重大なことがそこにあった。
彼女は道にしゃがんで顔を隠した。そうしているのが彼自身であるように見えた。
彼女は今、かつてのような料理を作ることができない。料理というものはそもそも何であるか、ということが分らなくなり始めている。
「綻ぶ」ということは、学んできたものがわからなくなるということである。世界から教わってきたものの意味がわからなくなるということである。しかしそれは悲惨なことであろうか。世界はいままでちゃんとした意味を教えてくれてきたのだろうか。
「綻ぶ」のがおそろしいのは、そういう「根本の」疑問に、人生の最後に直面しなければならないことだ。
――とここまではふつうの作家にも書けるのである。なぜなら、小説とは世界に意味を見つける手段、ほうっておくと無意味に陥る=「綻んで」しまう世界に抵抗する手段だとふつうの作家は思うからだ。しかし、小島信夫は違う。小島信夫は「綻ぶ」こともまた小説ではないかと示唆する。雁字搦(がんじがら)めに意味にしばりつけられた世界から「綻ぶ」ことも小説、いや人生ではないのかと。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする