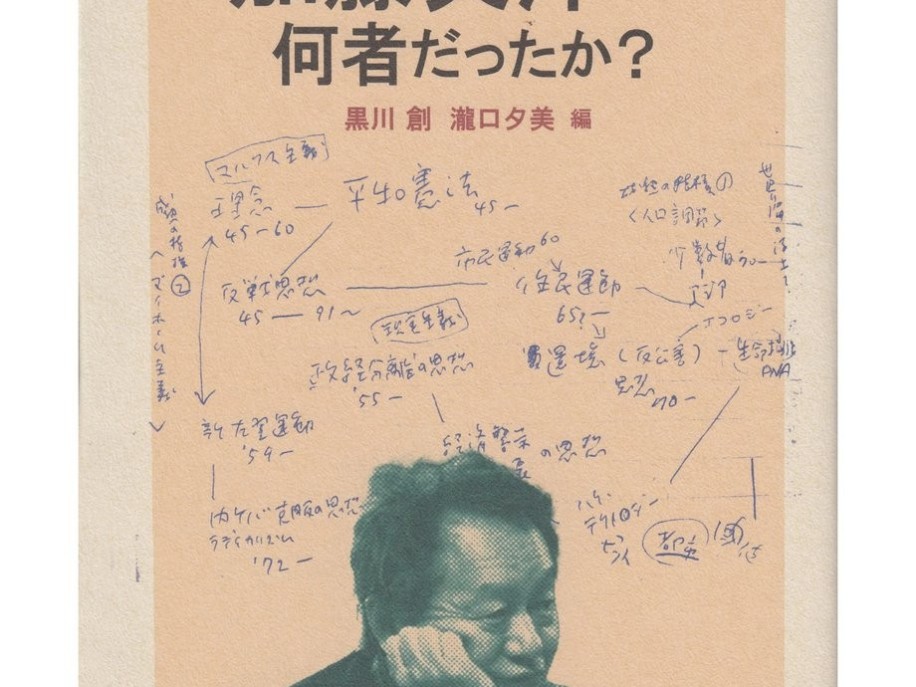書評
『茂田井武美術館 記憶ノカケラ』(玄光社)
昨年(’08年)の秋の日曜日のことだった。画家・茂田井武(もたいたけし)の回顧展を見にでかけた。雨の降りしきる中、思い切って見に行ってよかった。何とも愉しく、せつなく、胸の奥を揉まれる気分にひたれたのだった。
その回顧展は茂田井武の生誕百年を記念して開かれたものだった。一九〇八(明治四十一)年に生まれ、一九五六年に四十八歳で亡くなった人だから、最晩年の作品でも半世紀以上前に描かれたわけだが、ちっとも古くさくない。カワイイ。新しい。ショップで茂田井グッズ(カードやバッジ)を買い込まずにはいられなかった。
そんな今風の魅力をたたえながらも、決して浮薄に流れてはいない。どこか心の深いところ――魂に訴えてくるような絵なのだった。
この『茂田井武美術館 記憶ノカケラ』(講談社、ALL REVIEWS事務局注:2017年に玄光社より復刻)という本も生誕百年を記念して出版されたもの。二〇〇点に及ぶ作品が収録されているばかりではなく、その得がたい人物像もよく伝えている。
茂田井武は美術界の権威的な部分とはまったく無縁に生きた。児童向けの雑誌や本を中心に挿し絵・装丁・広告などを手がけた。その作品の数かずを見ると、「巧い」「芸術的」「深刻」に見られることを厭がっているかのようだ。
こんなエピソードがある。「(茂田井は)子どもの描く素朴で自由な表現を愛した。自分の絵は惜しげもなく捨てるが、子どもたちの描いた絵は大切に保存していた。児童画の模写もよくし、なかには子どもとの合作や、どちらが作者か判別に悩む作品もある」。私が特に好もしく思うのは「自分の絵は惜しげもなく捨てるが」というところ。「私」への執着よりも「無心」への憧れが強かった人だと思う。
茂田井武は詩人の心を持つ人でもあって、『宝船』と題された絵物語は、中学時代の夏休みに千葉の寺で過ごした思い出を絵に文にしたもの。その時の風や雨音まで感じられ、しみじみと美しい。
人生のある一瞬の記憶は、茂田井武の中心モチーフになっていて、彼自身、こんなふうに書きとめている。「記憶ノ一切ヲ悉(ことごと)ク大鍋二入レ、ジックリト火ニカケ、ユックリカキマハシカキマハシテハ ネリコネッテ、ウマイヨーカンニスル」――。絵物語『宝船』は、まさに「うまい羊糞」なのだった。
巻末には、『巴里の子供』と題された特別付録あり。切り取ってたたむと小さな絵本になるというもの。
茂田井は二十二歳から三年間をパリで過ごした(わが憧れの一九三〇年代前半のパリだ!)。その記憶を楽しみながら、茂田井は貧しい暮らしの中で三歳の長女のためにこんな絵本を手作りしていたのだった。贅沢、と思う。
【この書評が収録されている書籍】
その回顧展は茂田井武の生誕百年を記念して開かれたものだった。一九〇八(明治四十一)年に生まれ、一九五六年に四十八歳で亡くなった人だから、最晩年の作品でも半世紀以上前に描かれたわけだが、ちっとも古くさくない。カワイイ。新しい。ショップで茂田井グッズ(カードやバッジ)を買い込まずにはいられなかった。
そんな今風の魅力をたたえながらも、決して浮薄に流れてはいない。どこか心の深いところ――魂に訴えてくるような絵なのだった。
この『茂田井武美術館 記憶ノカケラ』(講談社、ALL REVIEWS事務局注:2017年に玄光社より復刻)という本も生誕百年を記念して出版されたもの。二〇〇点に及ぶ作品が収録されているばかりではなく、その得がたい人物像もよく伝えている。
茂田井武は美術界の権威的な部分とはまったく無縁に生きた。児童向けの雑誌や本を中心に挿し絵・装丁・広告などを手がけた。その作品の数かずを見ると、「巧い」「芸術的」「深刻」に見られることを厭がっているかのようだ。
こんなエピソードがある。「(茂田井は)子どもの描く素朴で自由な表現を愛した。自分の絵は惜しげもなく捨てるが、子どもたちの描いた絵は大切に保存していた。児童画の模写もよくし、なかには子どもとの合作や、どちらが作者か判別に悩む作品もある」。私が特に好もしく思うのは「自分の絵は惜しげもなく捨てるが」というところ。「私」への執着よりも「無心」への憧れが強かった人だと思う。
茂田井武は詩人の心を持つ人でもあって、『宝船』と題された絵物語は、中学時代の夏休みに千葉の寺で過ごした思い出を絵に文にしたもの。その時の風や雨音まで感じられ、しみじみと美しい。
人生のある一瞬の記憶は、茂田井武の中心モチーフになっていて、彼自身、こんなふうに書きとめている。「記憶ノ一切ヲ悉(ことごと)ク大鍋二入レ、ジックリト火ニカケ、ユックリカキマハシカキマハシテハ ネリコネッテ、ウマイヨーカンニスル」――。絵物語『宝船』は、まさに「うまい羊糞」なのだった。
巻末には、『巴里の子供』と題された特別付録あり。切り取ってたたむと小さな絵本になるというもの。
茂田井は二十二歳から三年間をパリで過ごした(わが憧れの一九三〇年代前半のパリだ!)。その記憶を楽しみながら、茂田井は貧しい暮らしの中で三歳の長女のためにこんな絵本を手作りしていたのだった。贅沢、と思う。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする