書評
『新版 池袋のアジア系外国人』(明石書店)
語り始める声
何年か前になるが、ある朝普段よりも早い時間に池袋駅西口から地下道をR大学方面に向かって歩いたところ、反対方向に急ぐ人々のほとんどがアジア系外国人だったので、さすがに驚いたことがある。西口界隈だけでも近年いわゆるエスニック料理屋が目立って増えている。確かに街は変わりつつある。だが、どのようにとなるととたんに曖昧模糊としてしまう。あれら外国人はどこから何の目的でやってきたのか。それもはっきりしない。そこから噂がささやかれることになる。地域住民でない我々にその噂はいかにもリアルに聞こえるもののどこか胡散臭い。本書を読んで、多くの疑問が解けた。アンケート調査という地道な方法によって、池袋にアジア系外国人が集まる理由、彼らが何を考えているのか、さらには地元の人間が何を考えているのかが明らかにされる。
しかしそれだけなら、最終的にすべては数に還元されてしまうわけだが、本書のユニークなところは、抽象化から再び具体化へと向かっているところだ。すなわち、インフォーマ ントの内面を探るのである。そのとき、公式的な発言の裏に隠れていたもう一つの声が生き生きと語り始める。これは社会学というよりも文化人類学の方法に近いかもしれない。いくつもの声たちに耳を傾けながら、オスカー・ルイスの著作を思い浮かべた。佐木隆三や佐藤洋二郎の小説にも通じる。
一口にアジア系外国人といっても実に様々だ。本書では対象をニューカマーズに限っているが、出稼ぎ組もいれば留学生もいる。そんな彼らをアジア系外国人と一つにくくってしまうことで我々は安心したり不安になったりしているのだ。相手が抽象的であれば排除するのに抵抗を感じなくなる。
大都市が空洞化しつつあり、そこへ外国人が入ってくるという。「移民の研究は受け入れ社会の研究である」という本書中の引用文をもう一度引用したくなる。
初出メディア
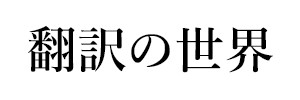
翻訳の世界 1994年4月号
ALL REVIEWSをフォローする








































