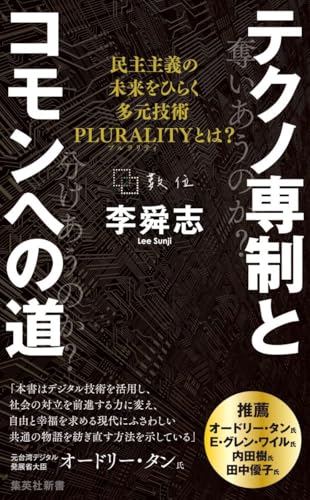書評
『ぼくは始祖鳥になりたい』(集英社)
意識の複合体という聖杯を求めて
抽象的なテーマをリアリズムの手法で書きたい。これは宮内勝典が繰り返し唱えてきたことである。それなりの志操を持つ作家ならば、口には出さなくとも、同じ気持を抱いているにちがいないが、ヌーヴォロマンやアメリカのポストモダン小説、ラテンアメリカの新小説を意識してきた作家の言葉となると、そこには漠然とした思い以上の何かがこめられているにちがいない。彼は言語や形式の実験が表面的には出尽し、リアリズム回帰やミニマリズムへの移行が世界的趨勢となり始めた頃に、本格的に作家活動を開始している。したがって、巨視的に見れば、いわば実験小説の時代への反動とみなすことも不可能ではないのだが、宮内の場合は、前の時代に背を向けるとかそれを無視するというのではない。要するに、抽象的なテーマをリアリズムで書くということ自体が彼にとっての実験なのであり、その意味で彼はまだ、たとえばラテンアメリカの新小説を本気で乗り越えようとしている数少ない作家のひとりなのである。したがって、『ぼくは始祖鳥になりたい』は、実験の時代の余熱の中で書き始められた「実験小説」であるということをまず認める必要がある。次に、テーマについて考えてみよう。単純化すれば、この作品はジローというスプーン曲げ少年の後日譚であり、いくつもの冒険や試練を乗り越えて彼が成長していく物語すなわち一種のビルドゥングス・ロマンと呼べるだろう。彼の成長を促すのが、アメリカ・インディアンの保留地で体験する荒行であることは明らかで、それを境に彼はたくましい青年へと変貌する。にもかかわらず、主人公の受動的姿勢は必ずしも変化するわけではない。実験の素材としてアメリカに呼び寄せられたときから、赤道近くのジャングルで反政府ゲリラの闘争に参加し、メキシコらしき国を経てアメリカに帰還するまでの間、彼は一貫して状況を拒まず、受け入れていく。つまり、他者に対してほとんど自己主張をしないのだ。おそらくこの受動性が原因なのだろう、全体が作者の見た夢あるいは幻視にも感じられる。この感覚は、ダンテの『神曲』に通じる。主人公の前に老師や女性の導き手が現れたり、とりわけ火山の宇宙的風景が描かれていたりするところからそういう印象を受けるのだ。もっともこの印象は必ずしも突飛なものでもないようだ。後で気づいたのだが、ある対談集で作者は、『神曲』を下敷きにしようと思ったときがあること、結局そうはしなかったものの、「意識の深いところに」その作品が存在していたことを、事実として認めているからである。
宮内によれば、登場する女性のうち、レイはベアトリーチェであり、彼女を通じて「女性性の奥行きの方へ入ってい」くことによりジローは、「シャーナという巫女に突き当た」る。そして、最後のシーンでシャーナとレイがジローの意識の中に入り込み、喋り合うのである。ここに本書の重要なポイントが示されているのであるが、話を少し戻すことにしよう。
この小説のテーマあるいは少なくともモチーフは同化と拒絶という問題にあるのではないだろうか。この概念が思い浮んだのは、作者のデビュー作『南風』に、主人公の青年明が故郷に戻ってきてもその土地に同化できず、外へ出る以前同様よそ者であり続けるということが書かれていることに起因する。あるいは同じ明が出てくる『火の降る日』にしても、主人公は土地からも家族という最小限の共同体からも遊離し、同化してはいない。三田誠広が指摘するように、主人公と土地、共同体との関係は、たとえば中上健次の紀州サーガとはベクトルの向きが違っている。中上の小説では、主人公は土地に受け入れられながら土地を呪うのに対し、宮内の小説の主人公は決して土地に受け入れられず、彼の方も土地との距離を失くそうとはしない。
『ぼくは始祖鳥になりたい』の主人公ジローも、先に引用した二部作の主人公同様、根なし草的存在である。四歳のときに一家で渡米した彼は、ニューヨークのジュニア・ハイスクールに通っていた十三歳のときに、両親の離婚にともない母と一緒に日本に戻る。この設定は、明の場合そして満州帰りという作者の体験と遠く冴し合っている。重要なのは、一家の滞在が日本に顔を向けた短期のものではなく、永住する可能性があったことであり、ジローはことによると日系アメリカ人になっていたかもしれないということである。つまり彼は、アメリカへの帰化未遂に終った根なし草なのだ。さらに、ジローの場合は、土地と同時に社会、とりわけマスメディアが権力を持つ高度資本主義社会から切り離されてしまった人物でもある。マスメディアは彼を、超能力を発揮していた間は受け入れたが、失ったとたん拒絶した。そして彼はアメリカの研究所に目をつけられ、渡米するのだが、ここでも真に受け入れられたわけではない。
このような存在を、デラシネと呼んで感傷的にまたナルシスティックに描くことも、ディアスポラとして肯定的に描くことも不可能ではない。その気になれば、主人公に永遠の越境者として移動を続けさせることだってできる。だが、作者は別の方法で主人公に世界との折合いをつけさせようとする。ただし、その世界がWASPのアメリカでないことは言うまでもない。宮内はほとんど本能的に白人を嫌悪し、有色人種とりわけモンゴロイドにシンパシーを抱く。それはこの作家のユニークなところであると同時に、ときに弱点ともなる。
それにしても、土地や共同体に帰属せず、回帰することも和解することもなく、いかにして世界と折り合えるのか。おそらくこれが『ぼくは始祖鳥になりたい』のメイン・テーマだろう。つまり本書で語られているのは、その方途を探究する旅なのだ。主人公は聖杯が何であるのかを知らぬままに旅を続ける。そして賢者たちに出会い、出会いの印としてラピスラズリの指輪やインディアンの羽根飾りをもらうことになる。彼は科学の国、考古学の国、先住民の国を回り、さらに赤道近くのジャングルにまで足を伸ばす。水の上を漂うその場面は一種の胎内巡りであり、緑の地獄巡りとも言えるだろう。
ニカラグアなど中米諸国の国名を伏せ、位置をずらすことで神話化を施したこの個所の叙述は、その自然描写など詩的幻想性に富んでいるのだが、火傷をともなうインディアンの儀式に比べると、主人公の再生をもたらすには装置としてはいささか弱さを感じさせる。たぶん理由のひとつは、主人公の姿勢の違いにあるのだろう。どちらの場合も受動的ではあるのだが、インディアンの儀式の場合ジローは、この少数民族の側に立っているために、明らかに積極的に儀式に巻き込まれていく。つまり、善悪の判断が下しやすいので、ジャスパーの冒険主義に対しては批判的であるものの、彼に批評上の迷いは生じない。ところが、ジャングルのゲリラ闘争の場合、事は単純ではない。というのも、ここでのゲリラはアメリカに支援された反革命軍という性格を持つからだ。さらに、この個所と重なるノンフィクション、『ニカラグア密航計画』にはなかった、メキシコのチアパス州で起きた先住民の反乱の問題を新たな情報として持ち込むことによって、組織の関係はあまりに複雑になってしまった。その結果、ジローは自分の行動を正当化するために、「自分はただ、最も弱い者の立場で苦しんでいる人たちの側に立つしかない」と独白せざるをえないのだが、それが言い訳にすぎないことを彼は自覚している。そこで、「義(ただ)しいことをやろうとすればするほど、おれはいつも、いい笑いものだ。茶番になる」と言って、判断を停止してしまう。確かにジローという青年の理解力では、内戦の中の内戦といった構図は読み解けないにちがいない。それにジュニア・ハイスクールで習ったとはいえ、彼のスペイン語力では会話はおぼつかないはずだ。その意味では彼がより消極的にならざるをえないというのはリアルなのだが、にもかかわらず、物足りなく感じられるのは、ジローの知的成長ぶりが発揮されていないからだ。しかもここでは、出会った先住民系の女性が真の導き手になっていない。主人公は目的も意欲も激しい葛藤もなく、ひたすら漂い続ける。そのため、唐突に訪れる帰還が『オデュッセイア』のようには輝かないのである。そしてもうひとつ、ジャングルの冒険における主人公にはもはやサイキック少年の面影がなく、あまりに作者に近づきすぎている。これまではジムやニューマンら複数の人物を登場させ、作者の考えを分担させることができたが、このエピソードでは視点が固定してしまっていることも、盛り上りを欠く原因なのだろう。たとえば、ここを、グロテスクな悪夢として描くという手もあっただろう。そうすれば前述の胎内巡り、地獄巡りという性格ははっきりしてくる。そうしなかったのは、作者が「北」ではなく「南」の人間であるからに違いない。「北」の人間はしばしば「南」を異界として描く。だが宮内の眼差しはむしろ「南」の人間の眼差しであり、彼にとって「南」は「北」に勝るとも劣らぬ現実なのである。
この作品のもうひとつのテーマは、人間とは何かという昔ながらの問だろう。この問に答えるためには、個人の内面に分け入り、徹底的に心理描写を行うという方法がある。つまり、ミクロ・コスモスとしての人間を分析するのだ。だが作者は新たな答を見出すべく、人間を種としてのヒトとして捉え、ヒトをヒトたらしめるものは意識であり、自己認識できることであるとし、意識の進化を考える。したがって、自意識をやっかいなものとしながらも、薬物や超常現象によって一時的にそれを克服するのではなく、根本的に自意識を乗り越える方法として、意識の進化を考えるのである。意識が進化すれば、そこには同化と拒絶という二項対立は存在しなくなり、すべてを受け入れることができるようになるだろう。
ここで登場するのが、「意識の複合体」という概念である。これについて作者は早々とジローの口を借りて喋らせている。自分が退行催眠を受けて喋った言葉を再現してみせる場面で、ジローはこう語っている。
わたしはきみたちが考えるような超越的な存在ではない。わたしはひとつの複合的なレベルにすぎない。意識の複合体だ。わたしのようなものは宇宙にいくらでも在る。とりあえずわたしといっているが、むろん人格的な存在でもない。
だとすれば、この小説は、ジローという選ばれた少年が、意識の複合体という聖杯を探究する物語であり、意識の複合体という謎を解明するミステリー小説でもあることになる。あるいは様々な科学的仮説をパラフレイズしたSFさらにはオカルト小説とみなすことも可能だろう。作者が積極的にジャンルの混淆を試みていることは明らかだ。最初の小説『南風』に既に見られるジャンルの闘争が、この作品ではより大きな形で存在している。それもこの小説が実験的である理由のひとつである。
人類の歴史というタイムスパンで見ればごく最近の発明でしかない近代小説は、それ自身が発明される以前のことを語るのが不得意だ。同様にはるか彼方の未来について語ることも得意ではない。要するに想像が及ばないのである。ところが宮内勝典という作家は、日常的現実の中に、五万年前の地球を見てしまう。なぜそのような幻視が可能なのか。理由のひとつは、彼が育った土地の風景に求められるかもしれない。
明を主人公とする初期二部作において、作者は二万年前の火山の噴火が生んだ風景に特別な意味を持たせている。そこは惑星としての地球、言い換えれば宇宙が露出している場所であり、日常からは切り離された空間である。主人公たちはそこではるかなる過去を幻視しているのだが、作者は日本文学の制度という枠の中で書いているために、それを単に想像としてしか書けず、また南極に神が集うのを見る人物を狂人としてしか語れない。とはいえ、父親の帰還を予言し、当てる超能力者が既に現れている。『ぼくは始祖鳥になりたい』は、そうしたリアリズム小説がタブーとする領域に大胆に踏み込んだ作品と言えるだろう。恐竜の化石やインディアンの聖地は、はるかな過去を再現し、人類を相対化するための装置あるいは合理主義に染まった人間が経験できないことを経験できる場所として選ばれている。それを作者の周到な戦略と見ることも可能だろう。
だが、それでも、「意識の複合体」といった概念は、リアリズム小説には馴染まない。そこで作者が持ち出すのが、混淆、混血という概念である。折しも「クレオール」についての言説が盛んに言われるようになったことは、宮内にとって追い風になったはずだ。彼は「意識の複合体」という概念をあまりに飛躍したものと感じさせないように、一般的読者にも想像できる混淆や混血という概念をクッションとして差し出すのである。そのために、主要な登場人物は混血として設定され、多言語的状況が描かれる。さらに作者はジャングルから帰還する途中、メキシコシティーらしき都市に立ち寄ったジローに次のように言わせている。
いたるところ混血者だらけだった。(…)ここはもう民族全体がまるごと、どの人種とも特定できない新しいヒトへと変わりつつあるらしい。(…)
民族まるごと混血化してしまったのか。やはり、こうなっていくしかないのだろうな。惑星のネイティヴたちが血を交え、溶けあい、新しいヒト科へ変成していくわけか。
未完となった小説『異族』で中上健次は混血の問題を提示した。だが、その小説のベクトルが水平であったのに対し、『ぼくは始祖鳥になりたい』は、時空的に垂直のベクトルを導入する。そして天空から地球を眺める。このイメージは既に『火の降る日』でも語られている。『奇蹟』のトモノオジやオリュウノオバが霊魂として土地の人間たちを見守ったのに対し、宮内の小説では、意識がヒトを眺めるのだ。
『ぼくは始祖鳥になりたい』の終章で作者は、ありうべき意識の複合体のささやかなモデルを提示している。それはジローの意識であると同時に様々な声を含んだ多声体である。これより前に、ジローやニューマンの意識にシャーナやレイの声が混じるという場面があったが、ここではスケールがさらに大きくなっている。と同時に、地球という惑星が一個の意識であることが述べられている。
人間とは変らないものだということを、小説は繰り返し語ってきた。それに対し、ヒトの進化、さらにヒトという種が亡びた後のことまで想像し、小説にした例はSFをのぞけばほとんどない。宮内勝典がその惑星的視野によって書いた『ぼくは始祖鳥になりたい』の真の評価は、ことによると、はるか後の世代によって成されるのかもしれない。
ALL REVIEWSをフォローする