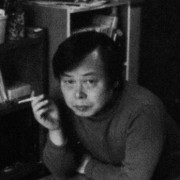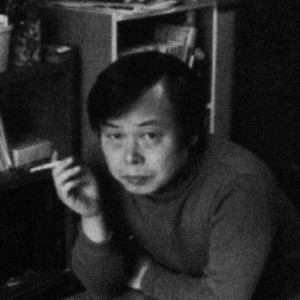書評
『人生、しょせん運不運』(草思社)
自らの死を描こうとした作家の余白
誕生の記憶を書いた作家(三島由紀夫)はいるけれども、自らの死を書いた作家はいない。デュシャンではないが、「死ぬのはいつも他人」だからだ。しかし予想はできる。古山高麗雄の場合は、独り暮らしだから倒れてもすぐには発見されずにいるだろう。暑い時期なら私の死体が発見されたときには、腐臭を放っているかもしれないなあ。その腐臭で発見されることになるかもしれない。
とまれ確実にやってくる結末を前にして、八十一年の生涯を回顧した。旧朝鮮の旧満州との国境の町、新義州の富裕な医師の家庭に生まれ、兄一人のほかは母、姉妹と女ばかりに囲まれて育ち、やがて内地の旧制三高へ。当時としてはエリートまっしぐらの道程だ。ここでつまずいた。というより進んでドロップドアウトした。リベラルな校風で知られた三高にまで軍国主義的風潮が及んでいるのに堪(た)えられなかったからだという。東京へ出た古山は荷風『ぼく東綺譚(ぼくとうきたん)』にかぶれて、送金が尽きるまで玉の井に入り浸る。ちょっとした放蕩三昧(ほうとうざんまい)。するうちに妹も母も死に、幼時から彼を包んできた「女の国(ムンドゥスムリエブリス)」は崩壊する。その後は戦場へ。ここから先は戦後の読者のご存じの通り。
戦争三部作第一部『断作戦』に、帰還者が戦友の妹を捜しあてて、兄の末期を報告しに行くくだりがある。戦友の妹はいざ会ってみると何となくよそよそしい。彼女が当夜待っていたのは、非日常的な死を遂げた兄の過去の消息より現在同居中の息子の毎夜の帰宅とわかり、報告者はついしらける。直線的なエリートコースからドロップドアウトして円環的に反覆する「女の国」にかつての戦場体験者が見たものは、戦争も平和も呑(の)みこむ千篇一律(せんぺんいちりつ)の日常だったのだ。
作者の死により予定の半分以下で回想は中断されるが、一方で苛酷(かこく)な戦場体験を強いられながら、確信犯的かつ、かなりじだらくなドロップドアウト人間だった男の八十一年の生を支えた、したたかな「女の力」がまざまざと感じ取れる。未完の後半は『小さな市街図』のいつまでも埋まらない白地図のように余白のままに残った。
朝日新聞 2004年6月6日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする