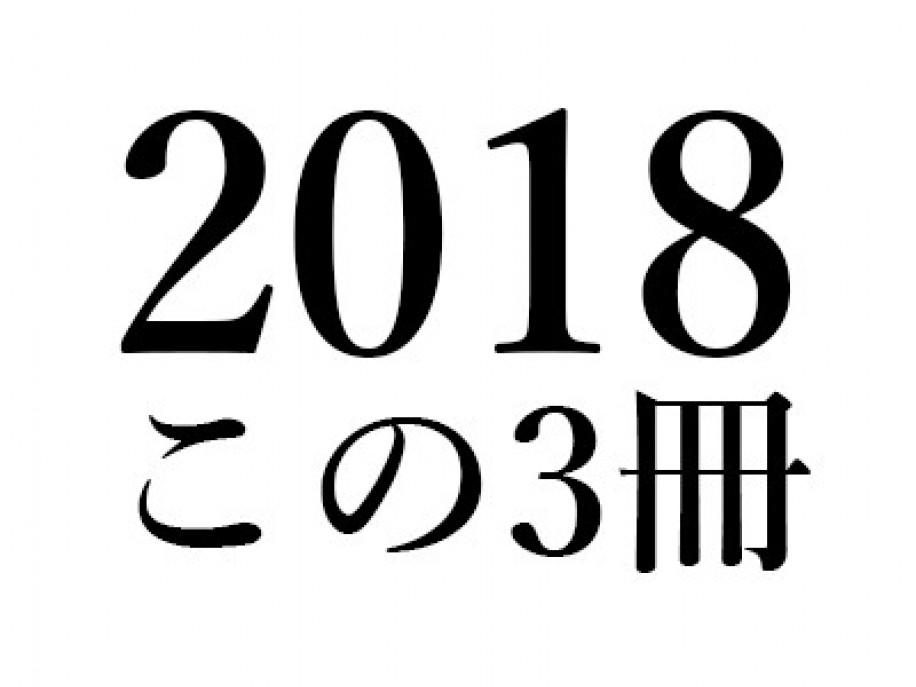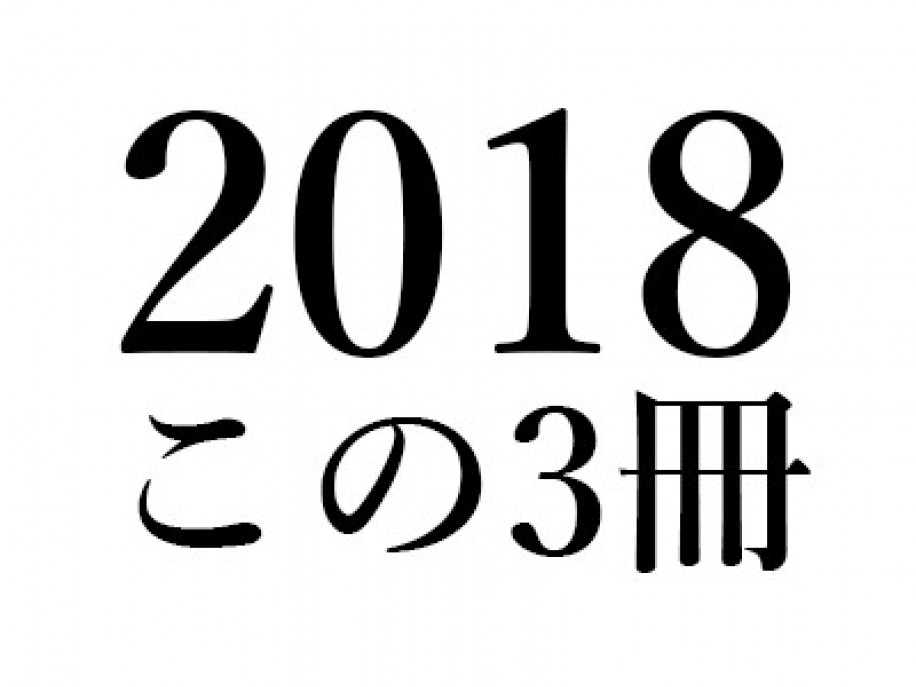書評
『身体の零度』(講談社)
日常のさりげない所作に宿る「思想」
長いこと身体は鍛えるものであっても論ずるものではなかった。だから、何年か前から雑誌などで身体論が目につくようになった時、いったい何を論じているんだろうかといぶかったが、読んでみて、目のウロコが何枚も落ちた。はじめて都市論に接した時と同じで、一見ただの物質にすぎない、せいぜい言っても器にすぎないと軽く見ていたものが実は精神とか文化とかと同じくらいの意味を持ち、いやむしろ精神や文化もそうした器や物質からの分泌物にすぎないんじゃないかとすら思わせられた。三浦雅士は、現代思想の批評家兼編集者としてスタートを切り、今は舞踊を語ることに力点を移している。思想と身体の華ともいうべき舞踊に今いちばん入れ込んでいる著者の手になる身体論を読まないのは、造り酒屋に行って旬の絞りたてを頂かないのと同じ損失といえようか。
批評家の常として、元ネタは他の人の著作から出ているのだが、編集者の常としてまとめ方がまことに上手で分かりやすい。たとえば、武智鉄二(たけちてつじ)の論考を契機として紡がれる日本人の歩行についての一章は高校生なんかにも是非読ませたい。日本人はかつて今とは全くちがう歩行をしていたなんてご存じだろうか。今は手と足を交互に前に出すのが当たり前だが、明治以前の日本人は右足と右手を同時に出す〈ナンバ〉という歩き方をしていたというのである。飛脚のようなプロの歩行者もナンバで走っていたというからマサカと思ったが、言われてみると相撲の出足も能の前方移動もナンバにちがいない。ナンバは、クワを打つ時の姿勢に象徴されるように農耕民族に特有のものという。
相撲や能はむろん剣道も日本舞踊もスリ足を基本とするが、これも農耕民族に固有で、「浮足立つ」「跳ね上がる」「腰が据わってない」なんて否定的言い方があるように、伝統日本においては跳ねたり飛び上がったりすることは邪道。もちろんこの反対がヨーロッパのダンスということになる。
スリ足のナンバ、これで軍隊や運動会の行進が行われる光景を想像するとおかしいが、明治の日本は伝統歩行の撲滅に乗り出す。初代文部大臣森有礼(もりありのり)は、組織だった行動になじむ身体と心性を育むために、つまり農耕社会から産業社会にすみやかに移行できるようにとこれを進め、軍隊が完成させる。幼稚園や小学校に入った時の最初の記憶の一つに”前へならえ”があるのは、深い深い意味を持っているのである。
このように、日頃何気なく自分がやっている身体の動きが実は……という点に本書の読み味がある。
読み終わり散歩に出て、スリ足のナンバをそっとやってみたりするのは私だけではないはずである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする