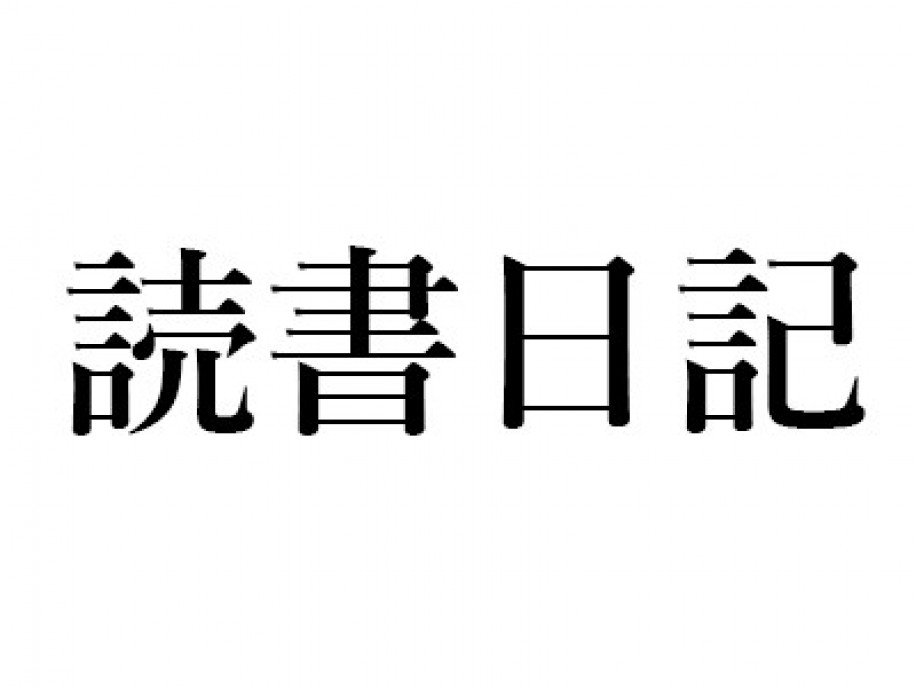書評
『緋の河』(新潮社)
小説家とカルーセル麻紀。ふたつの存在が彩なす物語。
北海道釧路の原風景のなか、男として生まれたひとりの少年が「きれいな女のひとになりたい」とゲイボーイへの憧れを抱く。親さえ敵にまわすことを厭(いと)わない、孤立無援の道のはじまりだ。長編小説『緋の河』が描く、孤独と勇気の物語。一行一行がしなやかなバネを思わせて強い。この強度、緩みのなさはどこから生みだされるのだろうと考えるとき、それは小説家の気迫によるものだと気づいてあらたに引き込まれた。
本作にはモデルがいる。
カルーセル麻紀。
いまでこそ「ニューハーフ」という属性が用意されているけれど、1942年生まれの「平原徹男」(旧名)が釧路の実家を飛び出してゲイバーを転々としはじめた十代のころ、その言葉さえなかった。
モロッコで受けた性転換手術のエピソードをあけすけに語り、機転の利いたトークを繰り広げて芸能界の売れっ子になると、妖艶な外形と釣り合いのとれない伝法な口調が世間の興味と関心を惹(ひ)いた。まだジェンダーの概念も薄かった昭和のころ、カルーセル麻紀は、その道を切り拓いたパイオニアなのだった。
あらかじめ存在そのものが強烈だったから、ページを開く前にすこし緊張感をおぼえた。モデルが健在のままフィクショナルな世界が展開する場合、とかく虚実皮膜の響き合いに困難がともないがちだから。
ところが、冒頭数行めで杞憂は吹き飛んだ。昭和24年、姉の章子が弟の秀男の耳元で「ヒデ坊、雪だ」とささやいた瞬間、私は一気に真冬の釧路に招き入れられ、あとは小説世界に没頭するばかりだった。
札幌のゲイバーを振り出しに、生き抜くために芸を磨きながら荒波をくぐる一匹狼、秀男の姿から目が離せない。流れ着く先々、目の前に現れる男たちは、ドンファンもピエロも、ホンモノもニセモノも、百戦錬磨の役者揃い。受けて立つ秀男の武器は、度胸と愛嬌と頭の回転の速さだ。
化粧から作法まで伝授してくれたマヤねえさんは、ことあるごと大切な言葉を秀男に投げかけてくれる。
「神様を許すのがあたしらの生きる道なんだよ。神様だって間違うんだから、人間に期待しちゃ気の毒だろ」
「泣くんじゃない。あたしらは泣いた分だけ命がすり減るんだよ。明日の顔が台無しだ」
心のなかに育まれてゆく清いもの、貴いもの。小説家は、嘲りや蔑みを受けてまで身体を張って自分の道を進もうとするときの人間の拠りどころを、カルーセル麻紀という実在の人物を通じて焙(あぶ)り出してゆく。
家族の物語でもある。白羽の矢を当てられて舞台やテレビに出るようになった秀男の瞼から、釧路に暮らす父や母、兄や姉の姿が消えることはない。おなじ男として、父や兄は存在を蔑むことでしか秀男と向き合えないが、姉の章子と母は、秀男の存在をまるごと受け止めようとする。母との邂逅(かいこう)の情景のせつなさ、温かさは本作の白眉(はくび)だ。
創造の源泉としての、カルーセル麻紀のすごみを感じる。読後、半人半馬のケンタウロスを思い浮かべた。桜木紫乃とカルーセル麻紀が上半身になったり下半身になったりしながら緋(ひ)の河を駆け抜けてゆく。
ALL REVIEWSをフォローする