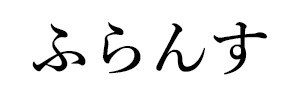書評
『僕はどうやってバカになったか』(青土社)
25歳の鮮烈なデビュー作
今年、弱冠19歳で芥川賞を受賞した綿矢りささんは、受賞作の冒頭の一行を決めるのに半年かかったという。小説家にとって書き出しの一行はそれほどに重要だ。「今日ママンが死んだ」(『異邦人』)にしても「いままたわれわれはまたしても孤独だ」(『なしくずしの死』)にしても、単に読者を最初からその世界に引きずり込むだけではなく、小説全体の基調音となって読者の耳にいつまでも響く。2001年、25歳のソルボンヌ大学学生マルタン・パージュが書いて、ベストセラーとなった本書はこう始まる。ここは本誌(ALL REVIEWS事務局注:本書評は雑誌「ふらんす」(白水社)に掲載されたもの)の読者のために原文で引用しよう。
Il avait toujours semblé à Antoine avoir l'âge des chiens. Quand il avait sept ans, il se sentait usé comme un homme de quarante-neuf ans.
猫の年じゃいけないのかなんて言わないでほしい。スウェーデンのハルストレム監督の作品だって、「マイ・ライフ・アズ・ア・ドッグ」(仏訳はMa vie de chien)だからいいので、あれが猫だったらあの優しさと切なさはない。犬だからこそ、小説全体を覆うユーモアと切なさとバカバカしさが生まれてくるのだ(わからない人は、仏和辞典でchienを引いておこうね)。
主人公のアントワーヌは、優柔不断であまりに寛容すぎるために「自国に居ながら無国籍者の境遇を味わっていた」。しかし、25歳のいま、彼は今までの生き方を捨て、新たな社会参加をしようと決心する。そのためにまず選んだのがアル中になることだった。といっても、好奇心の赴くまま手当たり次第に学問を修め、蜂蜜採集法や「お隣の犬のおしめを交換する」術までも身につけてきた彼のこと。まずはアル中に関する本を片っ端から読破する。だが、悲しいかな、実践が伴わず、生ビール半分で人事不省になる始末。アル中になる能力すらなかったのだ。
病院で知り合った自殺志願の女性から自殺クラブを紹介された彼は、退院後せっせとそこに通いつめ、自殺の方法を完全にマスターする。しかし、そうなればもう死ねない。アントワーヌはいよいよ最後の手段として、知性を捨て、みんながしているように「理解することを忘れ、政治を信じ、きれいな服を買い、いろんなものを大嫌いになってみ」ようと決意した。それは「バカになる」ことにほかならなかった。
最初に作者が断っているように、これは一種の遍歴譚である。アントワーヌは最後には再び「バカの世界」から無事帰還するのだが、その経緯を彩るエピソードや友人たちの人物造型が抜群である。皮肉で知的で不条理で可笑しくて、どこか悲しげで美しい。それは冒頭の数行とみごとに響きあい、この小説の奥行きを一層深くしている。本好きなら買うべし。
ALL REVIEWSをフォローする