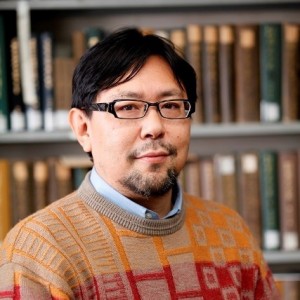書評
『京都の謎〈戦国編〉』(祥伝社)
秀吉や家康の「なぜ」を深く考える楽しさがある
2018年つまり一昨年のこと。静岡市の駿府城・天守台付近の発掘調査で、300点以上の金箔を貼った瓦が出土した。豊臣秀吉は、駿府に本拠を置いて東海地方を領していた徳川家康を関東に移したあと、同地域に信頼厚い中規模大名、数名を置いた。駿府城は中村一氏(かずうじ)に与えられた(14万石)が、金箔瓦をのせた天守閣はこの一氏の時期のものと考えられる。
発見は文句なく素晴らしいが、金色に輝いていたであろう天守建設の意図を尋ねられたある研究者が得々と次のように答えていたのには苦笑いしかなかった。「秀吉は豪華な天守を築くことで豊臣政権の経済力を関東に誇示し、家康の反乱を未然に防ごうとしたのだろう」。当たり前すぎる。それくらい、歴史好きな小学生だって考えつくんじゃないか。もう少しそれらしい解説はできないものか。
歴史資料をもとに考えることは楽しく、難しい。平凡な説明では聞いている人は満足しない。といって、上杉謙信は女性だった的な珍説・奇説をくり出したのでは、本道からはずれる。時には歴史資料がつく「ウソ」も考慮に入れながら、バランス良く独自の分析を行う。それが歴史を考察する醍醐味だろう。
この醍醐味がギュッと詰まっていて、ぜひおすすめしたいのが本書。戦国時代の京都を舞台に「なぜ秀吉は、京に大仏殿を建てたのか」「なぜ家康は、京都に無用な城を造ったのか」などの謎を解くかたちで、さまざまな歴史分析が示されている。
しいて主人公を一人挙げるなら、秀吉。それから、京都を去ったウラ主人公が家康。ときに首肯できない説も出てくるが、本当かな?こうじゃないかな?と、「深く」考えさせてくれる。豊かな構想と斬新な解釈が、読者を考える楽しみに誘うのだ。
ALL REVIEWSをフォローする