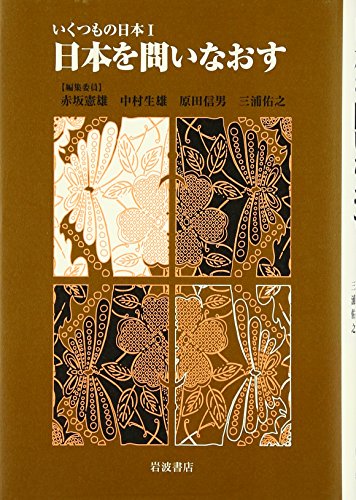書評
『天皇の歴史5 天皇と天下人』(講談社)
天下統一の「軸」を見定める刺激の書
戦国末期から近世にかけての歴史については、多くが個性の際だった三人の天下人を中心にして描かれてきており、そのためそれぞれの天下人についての思い入れや思いこみの激しい歴史ドラマや歴史小説が作られてきている。そこでは天皇の存在は付随的に考えられてきたのだが、しかし天皇を軸にして考えると、全体の流れが実にすっきりとすることが、本書を読むとよくわかってくる。秩序が乱れた時代には、天皇の存在が急浮上してくるのがこれまでの例であるが、この時代においても全く同じであった。
本書は『天皇の歴史』シリーズの第五巻に相当する。天皇の存在をきちんと歴史的に位置づける作業がやっと本格化したもの、と高く評価される企画であるが、それだけに様々な思い入れをどう処理するかが課題となる。
そこで著者は思いこみを排するために、淡々と政治の動きに沿って叙述するようにしたのであろう。あまりにも強い主張に満ちたこの時期の最近の著作とは実に対照的な本となっている。
文書や日記などの史料をしっかり読み、その要点をおさえ、枝葉末節には言及せず、天皇をめぐっての彼ら三人の動きに絞り、歴史の流れを過不足なく記してゆく。
基本史料を解釈するなかで叙述するという歴史研究者のとるべき方法が貫かれており、多くの文書の解釈が記され、今後の研究にとってまことに有益である。
さてプロローグでは、永禄八年(一五六五)七月に正親町天皇が発したキリシタン禁令を発掘してその意義を語っており、そのことだけを見ても、本文への期待は大きく、またそれを裏付けているのが信長をめぐる動きを扱った最初の二章である。
第一章「義昭・信長の入京」では、信長が永禄十年十一月に美濃の稲葉城を落としてその城下を岐阜と改め、「天下布武」の印章を使い始めたことに対し、天皇が綸旨(りんじ)をもってほめ称(たた)えた点から信長の天下人への第一歩と指摘して、信長の動きと天皇の対応を探ってゆく。
この時期の文書はその解釈によって意味が大きく変わるだけに、読解をゆるがせにはできないのだが、読むなかで成る程と思わせる解釈に満ちていた。ただ三二ページの「くわんしゆ寺くわんらくとて」を「勧修寺勘落とて」と読むのはどうだろうか。「くわんらく」は歓楽(病気の忌詞)ととったほうがよいかと思う。
続く第二章の「正親町天皇と信長」では、元亀四年(一五七三)七月に信長が将軍足利義昭を攻めて没落させた時に、信長が毛利にあてた書状で、義昭が「天下捨ておかる」と記したことをもって天下人としての信長の登場と見なし、信長と天皇の動きを丁寧に語ってゆく。
ただ第三章の「天下人秀吉の誕生」になると、秀吉の天下人としての登場に触れてはいるが、もう少しつっこんだ分析が欲しかったところである。総じて断定を避け、課題を提示するのにとどめているが、天皇や朝廷の対応についての信長との違いなどについても言及してほしかった。
その点で、第四章の「後陽成天皇と朝鮮出兵」では、朝鮮出兵をめぐる天皇と秀吉の動きを浮き彫りにしていて、よく読ませる叙述となっている。これを読むうちに、皇居の北京移転を思いとどまらせようとした後陽成天皇という存在が気になってきた。そもそも「後陽成」という諡号(しごう)がどうしてつけられたのであろうか。陽成天皇といえば、特異な天皇として考えられてきており、その天皇にちなむ諡号をどうして、と思ったからである。
第五章の「後陽成・後水尾天皇と家康」は、著者が本領とする徳川家康を対象とするのであれば、信長・秀吉の動きを踏まえて、どう家康が動いたのかが明らかにされるものと期待したのだが、これはもう紙数が少なくなったためであろうか、一章しか与えられておらず、足早に叙述をしているのは残念なところである。
また本のカバーに見える「家康・秀忠の強権に悲憤慷慨(こうがい)した後水尾天皇の胸中」についてもほとんど記述がないのはどうしてなのであろうか。こうした天皇の個性に関わる問題にももっと触れたならば、よかったであろう。改めて正親町・後陽成・後水尾天皇を軸にしてこの時代の動きを探ってみたらどうなるかと強く思った。
天下の平安、京都の治安、朝廷の安泰、皇位の継承に心を注いだ天皇の動きが時代とどう関わっていたのか、本書を読むなかでさらに知りたくなったのである。
エピローグは、秀吉が大明神に、家康が大権現に祀(まつ)られた問題を記しているが、ここでも信長がそうならなかったことに言及してほしかった。このような無いものねだりをしてしまうのも、三人の天下人の動きを天皇との関わりで探る刺激的な書であるからこそである。
次の研究への大きな架け橋となる書として読まれることを期待したい。
ALL REVIEWSをフォローする