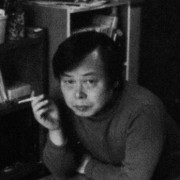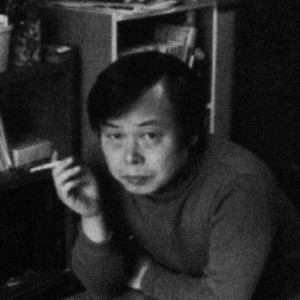書評
『毒曜日のギャラリー』(リブロポート)
ボナールの〝オレンジ色〟
「平賀敬の鼻はストロベリーのように赤い」と谷川晃一が書くと、思わずポンと膝を叩くほかはない。確かにあの鼻は梅干色でもなければドドメ色でもなくて、ずばりストロベリーのように赤いのだ。平賀敬を知っている人ならまずそう思わないわけはないし、この文章を読んではじめて平賀敬に会った人は、ああこの人がストロベリーの平賀さんかと、一目見て了解するにきまっている。ポルトレという文章形式がある。絵の方の肖像画ではない。ある人物の風貌やキャラクターを、ごく短い文章のなかで一触に書ききる諷刺文だ。谷川晃一『毒曜日のギャラリー』には、右の平賀敬を含めて戦後美術の代表選手二十五人のポルトレが、ずらりと並んで掛かっている。圧巻である。これを見ればここ三十数年の戦後美術がどういう展開を遂げてきたかが一目で分かるし、見なければ何も分からない(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1985年)。それも戦後美術論などという、ことごとしい物腰はまるでない。一点々々が俳文調にさらりと書き上げた、ポルトレの傑作ぞろいである。最後に「甲斐先生の思い出」という付録がある。夕暮れが迫ると突然絵筆を持つ手が震えだし、「コーちゃん、お酒!」と弟子の谷川少年に焼酎を買いにやらせる、アル中の老女流画家甲斐仁代。むざんに壊れてよれよれに萎れた母胎であるにもせよ、やはりこれが谷川晃一の(また他の二十五人の)母胎だったのだ。その母胎はボナール風のオレンジ色をしていたという。美しい母胎だったのである。
ALL REVIEWSをフォローする