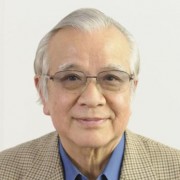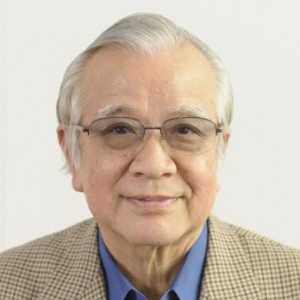書評
『新潮選書 手妻のはなし 失われた日本の奇術』(新潮社)
西洋とは異なる独自の技芸
本を開くと、前口上として“手妻とは日本人が考え、独自に完成させたマジックの事だ”とあり、さらに“幕末に日本にやって来た欧米人が手妻を見て、その技術の高さに驚嘆した”と記しているが、本書はこのユニークな庶民文化について歴史をたどりながら克明に綴った力作である。マジックはだれが見ても不思議だ、おもしろい。人々の好奇心を引いて、合理を超えた力をほのめかす。それゆえに当初は神秘と結びつき、宗教とも無縁ではなかった。これは権威の保護を受けて、今でも命を永らえている、と言ってもよいだろう。
一方、大衆の中に散って放下(ほうか)と呼ばれ、おおいに民衆を楽しませた。人気沸騰して興行は現在の価値に直して一人一万円の席料でも満員になったとか。
発展するにつれ道が分かれ、不思議を売り物とする一派とはべつに、歌舞伎などの影響を受けた華麗な一派が現れ、このことによりさらに演芸としての質を高めた。それぞれの時代にそれぞれの名人がいたことは論をまたない。
“世界の国々の中で、伝統のマジックを持っている国というのは、中国とインドと日本くらいしかない”のであり、この技は日本人の手先の器用さ、演じ物への強い関心とあいまって独自にして多様多彩な大衆文化を創りあげた、ということ。豊富な資料に基づく論述は、必ずしも知名度が高いとはいえない芸人が次々に登場して繁雑に映るきらいはあるが、全体を通して、確かな説得力に富んでいる。美貌の手妻師・松旭斎天勝(てんかつ)が登場して大正・昭和の興行界を席巻した事実は、今なお記憶に留める人もいるだろう。こうした流れの中から西洋マジックとは趣を異にした手妻が新しい技芸を取り入れながら生き続けていること、本書はその意味をいとおしみながら切実に訴えているようだ。
もちろん、これだけのことを綴る著者・藤山新太郎氏は手妻の名人であり、“私の演じる手妻の中で、「水芸」と「蝶」を越える作品はない”と、一見を勧めている。
朝日新聞 2009年11月8日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする