書評
『岡本一平漫画漫文集』(岩波書店)
一九九五年秋に岩波文庫から出版された『岡本一平漫画漫文集』が面白かった。
岡本一平には以前から興昧があった。作家・岡本かの子の夫であり、画家・岡本太郎の父である。こんな強烈な母子と暮らした一平はどんな人だったのだろうかと。もちろん、デビュー当時、夏目漱石にも激賞されたという、その漫画漫文のことも知りたかった。
明治の終わり頃、東京美術学校西洋画科というから今の芸大でオーソドックスな画家修業をしていた一平が漫画家になったのは偶然のことからだったが、いったんその仕事を始めてからは、外国漫画やサイレント映画のアイディアを取り入れたり、漫画に文章をつけるという創意工夫をめぐらしたりして(イラストライター南伸坊の大先輩というわけだ)、二十代でもう朝日新聞社のスターになっていた。二十九歳のときにはみずから東京漫画会(日本初の漫画家団体)を組織し、実質上の会長になっていた。
この『岡本一平漫画漫文集』には、一平の代表作、つまり大正の初めから昭和十年代までの作品がおさめられている。
私が一番面白く読んだのは、第二章の「女百面相」だ。大正六年に女性誌に掲載されたもので、コマの枠を映画フィルムのようにデザインしたストーリー漫画なので、“映画小説”と銘打っている。
ごく普通の中流家庭の奥さんたちが主役の漫画である。「ため子夫人」が夫にねだって秋草見物に連れて行ってもらう、その、さしたる事件も起きない平々凡々の一日をつづって、何やらホワーッとあたたかく、いとおしい気持にさせる手腕は、確かだ。
たとえば、冒頭の四コマ。デフォルメされた「ため子夫人」の顔の絵に、こんなキャプションがついている。
この「ため子夫人」とその夫は向島百花園に行って、秋草や虫の音に風流を感じるが、その帰り道に土手で夫の勤め先の同僚にバッタリ出会う。そのときの「ため子夫人」の恥じらいながら、しっかり横目で男たちの様子をうかがっている姿が、なかなか見ものだ。昔の日本の女の、分別や行儀や計算の厚苦しい衣の下に、おさえがたい好奇心や自己顕示欲をうごめかしている感じが出ていて。
「ため子夫人」とその夫は、食事をして、映画(長尺物の悲劇とチャップリンの笑劇)を見る。「ため子夫人」は呉服店のショーウインドーに新柄を発見、「よう貴夫(あなた)やア本当にもうこれっきりですからってばよう」と夫にねだって、買ってもらう……。
のどかな短い話だが、妙に「ため子夫人」がかわいらしくなってくる。即物的ないきものとしての女のかわいらしさが、うまくとらえられていると思う。
編者・清水勲氏による詳しい解説、小伝、年譜がついているのが、ありがたい。それによると、この「女百面相」が書かれたのは、前年まで一平の放蕩によってかの子との夫婦生活は危機的状況だったのが、二人とも宗教に関心を持ち出し、危機を乗りこえ、平穏を取り戻した頃だったという。確かに修羅場を通った人間でないと、こんな日常の些事の中からおかしみといとおしさをすくいあげることはできないのかもしれない。「ギャグ」ではなく「ユーモア」によって描かれた家庭漫画である。このへんは東海林さだおの大先輩という感じもする。
「漫画漫詩の東京」の章、あるいは「新東京風景・東京新夜曲」の章の大正末期から昭和初期の東京スケッチも興味深い。その当時にはすでに「銀ぶら」「ボートレース」「アパート」「デパート」などがあり、銀座ではとんかつ屋がはやり(「時代のすべてが露骨になって行くように食ものも露骨になって行く。今までトンカツと蔭でそっと綽名(あだな)に呼ばれていたものが堂々と表看板になった」と書いているのが面白い)、郊外沿線には「独逸(ドイツ)のモダニズム擬(まが)い、アメリカのバンガロー擬いの洋館」が林立する「文化村」がいくつもできあがり、「銀座をモンマルトルとすれば新宿はモンパルナス」といった感じだった……ということがわかる。
妻かの子が亡くなったのは、昭和十四年。一平はしばらくの間、かの子の仕事を整理し、発表することに追われる。敗戦のあと、小説家として再起しようと決意するが、『かげろふ一休』を遺して、昭和二十三年に脳溢血のため亡くなる。六十二歳。
そもそも一平は小説家になりたかった人なのだ。「父親に中学時代、小説書きになりたいと申し出ると、これからは絵画の時代になるから画家になれ、といわれ絵の稽古にやらされた」という人なのだ。
小説家になるつもりが画家の道に進み、本格的な洋画家をめざしていたのが漫画家になった。文章を書く才能、絵を描く才能を漫画漫文という形で充足させた。文豪・漱石に絶讃されたり、その世界では若くしてトップを走っていたり、漫画の社会的地位の向上に尽力したり……ということがあっても、当人は最後まで小説家への夢にこだわっていたのかもしれない。
しかし、こうして『岡本一平漫画漫文集』を読むと、やはり文章と絵の両方がある強味で、小説やルポルタージュ的文章よりも、ずうっと鮮やかにその時代の様子や気分が伝わってきて、楽しく貴重な資料になっている。本来、笑って読み捨てにされるべきものが、皮肉なことに案外とたいせつな記録になって後世に遺ったりするものだ――とつくづく思う。
いきなり話が下世話になってしまうが、何葉かのスナップ写真を見て、一平のハンサムなことにも驚かされた。若い頃はどこかネットリとした色気を漂わす好男子だったのが、戦後つまり六十歳過ぎてからはサッパリと枯れた上品な初老になった。息子・岡本太郎のあの狂おしい眼は、どうやら父ではなく母から受け継いだもののようだ。
最後の写真は、多磨墓地の一平の墓の前に、太郎が花をかかえてたたずんでいるところである。その墓石というのが、太陽が笑っているような、例の太郎オブジェである。出棺のとき、太郎は「岡本一平万歳!」を提案、涙の万歳三唱が行われたという。
【この書評が収録されている書籍】
岡本一平には以前から興昧があった。作家・岡本かの子の夫であり、画家・岡本太郎の父である。こんな強烈な母子と暮らした一平はどんな人だったのだろうかと。もちろん、デビュー当時、夏目漱石にも激賞されたという、その漫画漫文のことも知りたかった。
明治の終わり頃、東京美術学校西洋画科というから今の芸大でオーソドックスな画家修業をしていた一平が漫画家になったのは偶然のことからだったが、いったんその仕事を始めてからは、外国漫画やサイレント映画のアイディアを取り入れたり、漫画に文章をつけるという創意工夫をめぐらしたりして(イラストライター南伸坊の大先輩というわけだ)、二十代でもう朝日新聞社のスターになっていた。二十九歳のときにはみずから東京漫画会(日本初の漫画家団体)を組織し、実質上の会長になっていた。
この『岡本一平漫画漫文集』には、一平の代表作、つまり大正の初めから昭和十年代までの作品がおさめられている。
私が一番面白く読んだのは、第二章の「女百面相」だ。大正六年に女性誌に掲載されたもので、コマの枠を映画フィルムのようにデザインしたストーリー漫画なので、“映画小説”と銘打っている。
ごく普通の中流家庭の奥さんたちが主役の漫画である。「ため子夫人」が夫にねだって秋草見物に連れて行ってもらう、その、さしたる事件も起きない平々凡々の一日をつづって、何やらホワーッとあたたかく、いとおしい気持にさせる手腕は、確かだ。
たとえば、冒頭の四コマ。デフォルメされた「ため子夫人」の顔の絵に、こんなキャプションがついている。
当日の朝床(とこ)を離れるや否(いな)や眠(ねむ)い眼(め)を眩(まぶ)しそうに仰いで空模様を気にする顔。
お化粧する顔。顔の造作を延したり縮めたり、相手が鏡ゆえ安心して亭主にも見せないほどの思切(おもいき)り間(ま)の抜けた顔をする。
お着換(きが)えの時下女(げじょ)に襟(えり)を揃(そろ)えさす顔。
家を出た時の顔。近所の手前を兼(か)ね亭主よりはズット離れて歩き『あんな人なんかチットモ知りませんよ』といった風に乙(おつ)に澄(すま)した顔付。
この「ため子夫人」とその夫は向島百花園に行って、秋草や虫の音に風流を感じるが、その帰り道に土手で夫の勤め先の同僚にバッタリ出会う。そのときの「ため子夫人」の恥じらいながら、しっかり横目で男たちの様子をうかがっている姿が、なかなか見ものだ。昔の日本の女の、分別や行儀や計算の厚苦しい衣の下に、おさえがたい好奇心や自己顕示欲をうごめかしている感じが出ていて。
「ため子夫人」とその夫は、食事をして、映画(長尺物の悲劇とチャップリンの笑劇)を見る。「ため子夫人」は呉服店のショーウインドーに新柄を発見、「よう貴夫(あなた)やア本当にもうこれっきりですからってばよう」と夫にねだって、買ってもらう……。
のどかな短い話だが、妙に「ため子夫人」がかわいらしくなってくる。即物的ないきものとしての女のかわいらしさが、うまくとらえられていると思う。
編者・清水勲氏による詳しい解説、小伝、年譜がついているのが、ありがたい。それによると、この「女百面相」が書かれたのは、前年まで一平の放蕩によってかの子との夫婦生活は危機的状況だったのが、二人とも宗教に関心を持ち出し、危機を乗りこえ、平穏を取り戻した頃だったという。確かに修羅場を通った人間でないと、こんな日常の些事の中からおかしみといとおしさをすくいあげることはできないのかもしれない。「ギャグ」ではなく「ユーモア」によって描かれた家庭漫画である。このへんは東海林さだおの大先輩という感じもする。
「漫画漫詩の東京」の章、あるいは「新東京風景・東京新夜曲」の章の大正末期から昭和初期の東京スケッチも興味深い。その当時にはすでに「銀ぶら」「ボートレース」「アパート」「デパート」などがあり、銀座ではとんかつ屋がはやり(「時代のすべてが露骨になって行くように食ものも露骨になって行く。今までトンカツと蔭でそっと綽名(あだな)に呼ばれていたものが堂々と表看板になった」と書いているのが面白い)、郊外沿線には「独逸(ドイツ)のモダニズム擬(まが)い、アメリカのバンガロー擬いの洋館」が林立する「文化村」がいくつもできあがり、「銀座をモンマルトルとすれば新宿はモンパルナス」といった感じだった……ということがわかる。
妻かの子が亡くなったのは、昭和十四年。一平はしばらくの間、かの子の仕事を整理し、発表することに追われる。敗戦のあと、小説家として再起しようと決意するが、『かげろふ一休』を遺して、昭和二十三年に脳溢血のため亡くなる。六十二歳。
そもそも一平は小説家になりたかった人なのだ。「父親に中学時代、小説書きになりたいと申し出ると、これからは絵画の時代になるから画家になれ、といわれ絵の稽古にやらされた」という人なのだ。
小説家になるつもりが画家の道に進み、本格的な洋画家をめざしていたのが漫画家になった。文章を書く才能、絵を描く才能を漫画漫文という形で充足させた。文豪・漱石に絶讃されたり、その世界では若くしてトップを走っていたり、漫画の社会的地位の向上に尽力したり……ということがあっても、当人は最後まで小説家への夢にこだわっていたのかもしれない。
しかし、こうして『岡本一平漫画漫文集』を読むと、やはり文章と絵の両方がある強味で、小説やルポルタージュ的文章よりも、ずうっと鮮やかにその時代の様子や気分が伝わってきて、楽しく貴重な資料になっている。本来、笑って読み捨てにされるべきものが、皮肉なことに案外とたいせつな記録になって後世に遺ったりするものだ――とつくづく思う。
いきなり話が下世話になってしまうが、何葉かのスナップ写真を見て、一平のハンサムなことにも驚かされた。若い頃はどこかネットリとした色気を漂わす好男子だったのが、戦後つまり六十歳過ぎてからはサッパリと枯れた上品な初老になった。息子・岡本太郎のあの狂おしい眼は、どうやら父ではなく母から受け継いだもののようだ。
最後の写真は、多磨墓地の一平の墓の前に、太郎が花をかかえてたたずんでいるところである。その墓石というのが、太陽が笑っているような、例の太郎オブジェである。出棺のとき、太郎は「岡本一平万歳!」を提案、涙の万歳三唱が行われたという。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
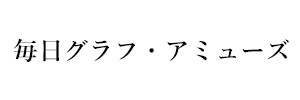
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする










































