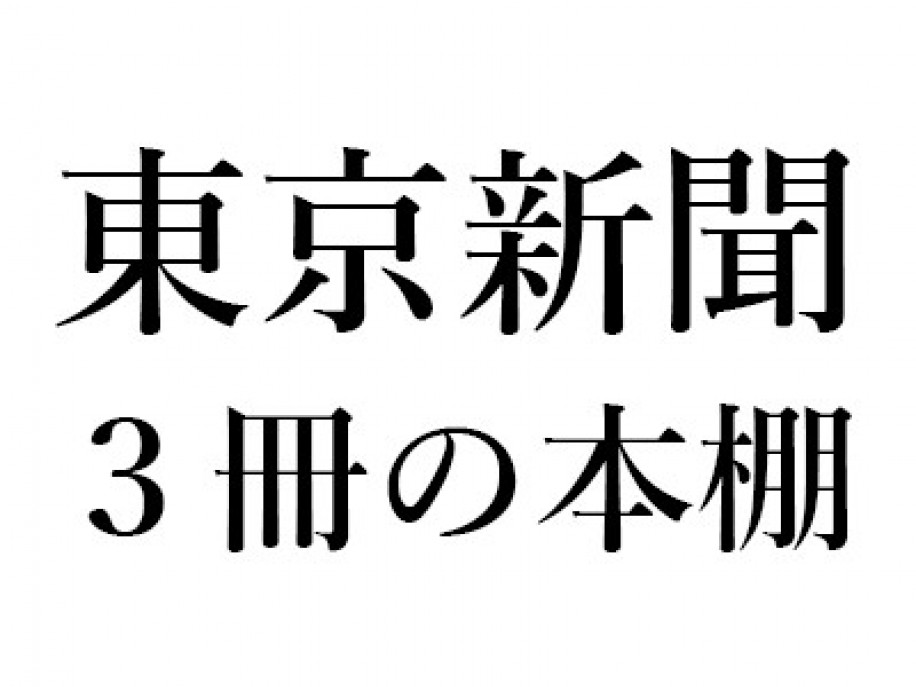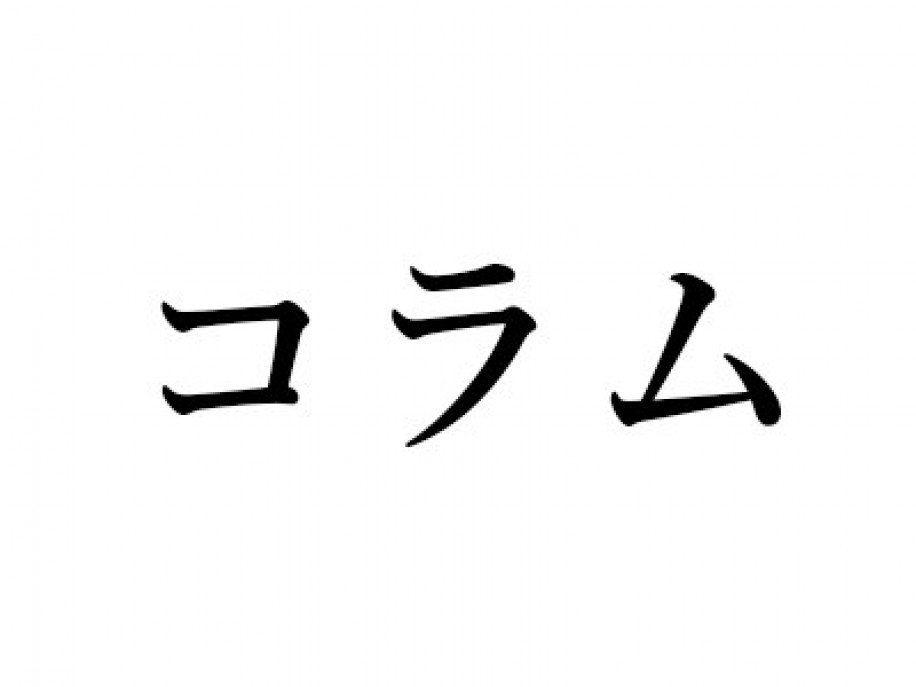書評
『追悼の文学史』(講談社)
時の遠近に整序され、交錯する生と死の風景
ナルホド、こういう本づくりもあったのかと、おもわず膝(ひざ)を打った。日本の文芸誌の慣例だが、著明な作家の死に対して特集を組む。文壇における「格」といったものがはたらいて多少のちがいはあるが、追悼の性格はかわらない。そこから選んで一冊を編む。ここでは死の年の順に、佐藤春夫、高見順、広津和郎、三島由紀夫、志賀直哉、川端康成の六人。追悼文は計五十一篇だが、書き手は吉行淳之介、丹羽文雄、佐多稲子など、何人かがかさなっている。その四十数人もまた、おおかたがのちの死に際して特集を組まれたにちがいない。すべて『群像』から選ばれていて、一九六四年から七二年にかけての六号分が底本になった。
時間の望遠鏡をあてがったぐあいだ。半世紀ちかく前の文学的風景が、くっきりと映っている。佐藤春夫について亀井勝一郎のいう「やや鼻にかかった紀州弁で、咄々(とつとつ)として諧謔(かいぎゃく)を弄(ろう)するその音声」。田村泰次郎が高見順に見た「演技意識」。「大根役者でおわる者の多いなかに、君は天性のすぐれた名優であった」。円地文子も同じように「舞台人の印象」を受けたが、はなやかな光源に「ひどく暗い光」を見てとった。
広津和郎は戦前からの作家として以上に、戦後は松川事件をめぐる裁判批判で知られる人だが、佐多稲子はその人の言葉として、「自分は暇だからできる」を書きとめている。松本清張は追悼文のタイトルを「松川事件の『愉(たの)しみ』」とした。「こういう云(い)い方は悪いかもしれないが、広津氏は松川裁判が終って、その愉しみを奪われたのがよほど淋(さび)しかったのではなかろ
うか」
自決にあたり三島由紀夫がのこした檄文(げきぶん)と二首の辞世を、河野多惠子は「冴(さ)えないものであった」と述べ、しめくくりに語っている。「氏は作家であったからこそ、最期にのぞみ、修練にかけては文よりも遥(はる)かに乏しかった筈(はず)の太刀は使いこなせても、文は使いこなせなかったのだと、私は思う」
志賀直哉はつねづね、そっと死に、弔問客には骨壺(つぼ)にお辞儀をして帰ってもらえばいいと、それを口ぐせにしていた。阿川弘之の「葬送の記」によると、病院の酸素マスクを経て、その死には芸術院からの叙位叙勲、天皇陛下の祭粢料(さいしりょう)、総理大臣の弔電などの問い合わせが殺到した。川端康成に「この頃は銀座に遊びに行きますか」と問われ、勘定が払いきれないのでごぶさただと中村真一郎が答えると、川端康成は言下に言ったそうだ。「勘定なんて払うもんじゃないんですよ」
新聞の追悼文とちがって雑誌の特集には、書き手に時間の余裕がある。だからおもしろいのだ。あらためて死者について考え、心に通りすぎていくことを思い返すなかで、おのずと自分と交錯する。その人にまつわる情景なり感情を整理しなくてはならない。死という厳粛な事実に対する礼節が必要だ。いびつな記憶は捨て、死者が秘めていたかくしごとには用心深く蓋(ふた)をして、いかにもその人を感じさせる言葉をさがし、またひとり記憶の訪問をくり返す。
追悼記の進行に立ち会うなかで、四十年あまりをひとっとび。だが気がつくと昭和の文壇はもはや影もなく、あれほど世に知られていた人も、多くがすっかり忘れられた。現在が過去に、過去が大過去になって現在と結ばれ、ここでは生と死と並んで時の遠近が微妙なバランスをとっている。そんな本に仕立てた功をたたえつつ言うのだが、この表題は誤解を招くのではなかろうか。
ALL REVIEWSをフォローする