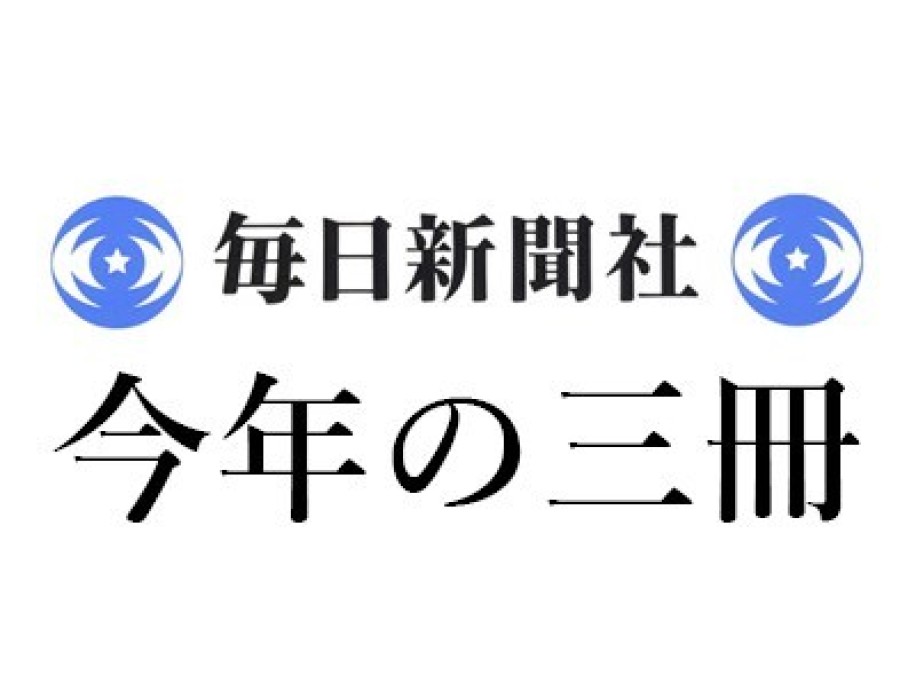書評
『卍どもえ』(中央公論新社)
仕掛け満載の意欲作
瓜生甫(うりゅうはじめ)は東京・青山にオフィスを構え、七人のスタッフを抱える気鋭のデザイナーである。大手広告会社に勤務しているあいだに頭角を現し、やがて独立して数々の実績を積み上げてきた。五十一歳になったいま、同業のなかで名の知れた存在になり、業界組織の会長にも選ばれた。彼は世界陸上大会のエンブレム・コンペの入賞を次の目標に定め、さらなる知名度アップを企んでいる。飛ぶ鳥を落とす勢いだが、家庭生活にはちょっとした亀裂が入っている。倦怠(けんたい)期を迎える夫婦にありがちなことだが、瓜生の妻ちづるが、無聊(ぶりょう)をかこっているあいだにネイリストの塩出可奈子と知り合い、道ならぬ関係に発展した。
ある日、瓜生の前に潮崎久美子という若い女性が突如として現れた。仕事や金銭の絡みが一切ないことは瓜生の警戒心を緩ませ、彼は知らず知らずのうちに蜜の罠に足をとられるようになる。幸い、大事には至らず、何とか危機を脱した。しかし、ほっと一息をついたのも束の間、事務所の有力社員がそろって辞職を申し出て、雲行きは途端に怪しくなった。
物語はここで結末へ向かうのではない。波瀾万丈のドラマはまだ、ほんの始まりに過ぎない。なぜなら、一つの物語の行き着くさきには、もう一つ物語の幕開けが待ち構えているからだ。
瓜生はかつてコマーシャルの現地ロケで旅行会社の毬子(まりこ)に世話になったが、彼女が後に結婚した中子脩(なかごおさむ)という実業家は変わった経歴の持ち主である。彼は非嫡出子として生まれ、父親の木佐貫を知らずに成人した。木佐貫という男の過去をたどっていくと、近代史の秘密が次々と明るみに出てきた。
中子脩はフィリピンで語学学校を開き、事業は順調に拡大している。現地で大物政治家と懇意になったのがきっかけで、やがて彼は思わぬ波乱に巻き込まれていく。
こうして物語の舞台は日本国内から海外へ、現在から過去へと広がり、登場人物は慌ただしく交代しては、また、戻ってくる。複数の物語は互いに絡んでおり、人物関係は幾重にも重なり合っている。もはや二つ巴や三つ巴どころではない。「卍どもえ」はそのような複雑な関係性や偶然性の遍在を示唆している。
十九世紀小説は様式としていまや軽蔑や嘲笑の文脈で語られることが多い。その一方、言語芸術としての小説を追い求めたさきにあるのは、怒涛のような読者離れである。
文学が途方もなく迷走するなかで、この長編が示してくれたのは「ネオリアリズム」とでもいうべき可能性である。複数の物語を並行させ、互いに交差させることで、小説でしか描けない世界を作り出すことができた。
そこには主役も脇役もいない。というより、そのような古典的な分類はもはや意味をなさない。登場人物がかわるがわる主役のように現れたかと思うと、次の場面はたちまち副次的な人物になっていく。
緻密な調査にもとづく細部描写にはさまざまな趣向が凝らされている。音楽、絵画、映画からマリンスポーツ、食べ物や酒の薀蓄(うんちく)にいたるまで、雑学のトリビアが随所にちりばめられており、全編はあたかも現代風俗の壮大な絵巻物のようだ。欧米の名作を下敷きにした設定もあれば、映画の場面を連想させる筋運びもある。さらには、ロサンゼルス、カサブランカやマニラなど海外都市の街頭風景や近代史の知られざるエピソードの数々も披露されている。読み手を興奮させる仕掛けが満載で、小説好きにとって見逃せない意欲作である。
ALL REVIEWSをフォローする