書評
『人情馬鹿物語』(光文社)
今年(一九九四年)は江戸川乱歩とともに徳川夢声の生誕百年に当たる年だそうで、『徳川夢聲の世界I、II』(深夜叢書)という対談集が出版された。
対談の相手は、内田百閒、谷崎潤一郎、久保田万太郎、吉川英治、柳田國男、福田恆存、江戸川乱歩……などそうそうたる顔ぶれである。たぶん、その中で一番若いのは『太陽の季節』を書いてまもなくの石原慎太郎だろう。夢声が「なんと彼の笑い顔は、オードリ・ヘップバーンそっくりなのは意外な発見だった」と書いているのがおかしい。
この二冊の対談集を読んで、一番面白く印象に残ったのは、思いがけずも川口松太郎だった。
私は川口松太郎という作家に関してほとんど何も知らず(川口浩・晶きょうだいのパパあるいは松島トモ子ちゃんのおかあさん役として映画に出ていた三益愛子の夫――ということくらいしか知らなかった)、関心もなかった。有名な作家と言っても何しろ『鶴八鶴次郎』とか『しぐれ茶屋おりく』とか、商業演劇系、いや新派系の芝居になるような小説を書いていた人で、私はそういう世界にほとんど関心がなかったのだ。しかし、夢声との対談を読んでいたら、
「そいつァ大きなリョウケンちがいだよ。“およしよ”たぁいわないがね」
「ぼくはむかしっから、温泉へいって書くとか、山へはいって書くとかってことができねえんだよ。表へ出りゃあすぐ芝居がある、映画館がある、カフェーがある、みんな働いている、そういうとこで書きたいな。精進はするが、陰気くさいこもり方はとてもできねえや」
といった調子の、まるで落語「大工調べ」のイキのいい棟梁のようなしゃべりなので、にわかに親しみを感じてしまったのだ。乱暴で、ズケズケとした、悪態めいた口のきき方の裏に、ばかばかしいほど屈折した羞恥心を感じる。
夢声は「(自分が)俳優不適格のいちばん大きい理由は、ぼくがてれ屋であることだ」「ぼくら、てれないなんてえわけにゃ、とてもいかないな」と語っているが、この二人は、おかしな羞恥心とそこから発生した独得の流儀というもの(それは、大ざっぱに言えば都会の生活文化というものだ)を共有している感じが確かにあって、他の対談にはない、何か暖かく密な感じが漂っているのだ。
というわけで、俄然、川口松太郎に興味を抱いたやさき、うまいぐあいに『人情馬鹿物語』(講談社、昭和四十九年版)と『昭和国民文学集8 川口松太郎』(筑摩書房、昭和四十九年版、『しぐれ茶屋おりく』『古都憂愁』『鶴八鶴次郎』が入っている)を入手した。
川口松太郎という人の個性が一番じかにわかるような気がするので、『人情馬鹿物語』について書いてみる。
川口松太郎は東京の浅草今戸町に生まれ、小学校卒業後、十六歳で久保田万太郎に師事し、はたちの頃から講釈師の悟道軒円玉のもとに住み込んで江戸文芸を学んだ。一般的な意味での学のある人ではないが、江戸文芸あるいは芸能といった面では一種の英才教育を受けた人といっていいと思う。
『人情馬鹿物語』は、講釈師の悟道軒円玉の家に住み、講談速記などを手伝いながら文芸の修業をしていた頃、そこで見聞した下町の人間模様を、虚実おりまぜながら十二の話に仕立てあげた、自伝的な短編集である。
面白い。何が面白いかというと妙な女が続々と出て来るところが面白い。
十二の短編は、ことごとく女が主役である。それも大半は堅気(かたぎ)のではなく、粋すじや芸人などのくろうとの女である。世慣れた女、こなれた女、わけのわかった女である。
子宮がんの手術がきっかけでひょんな男と「品物の試験でもするように」寝て以来仲むつまじく暮らすようになった女(「春情浮世節」)。
店の金を使い込んで逮捕された男のために、知人の間を奔走し、無罪放免にしてもらうが、その男とは夫婦にならず、サッと身を引いてしまった吉原の女「遊女夕霧」)。
自分の経営する待合に泊まった海軍の青年と深夜、浄瑠璃を語り合ううちに、親子ほどの年の違いも忘れ、「不思議な過ちの一夜」を明かしてしまう女(「親なしっ子」)。その後、青年は戦争で死ぬが、実はその青年は女が若い頃に生み、本妻宅に無理やり引き取られ、長い間会わずにいた息子だった――というのが凄い。
そういう、いわば「酸いも甘いもかみわけた」女たちの中で、異色なのが「歌吉心中」の準主役のお孝だ。
唐物商の吉田屋の内儀のお孝は、夫の安兵衛が芸者の歌吉に惚れ、財産をくいつぶすようになると、俄然、自立心に目ざめるようになる。
二人の娘を「残された、ただ一つの資本」と考え、「出世して父親を見返すのだ」という考えを吹き込み、精いっぱいの投資をして、みごと一流の芸者に仕立てあげる。夫への憎しみは、落ちぶれた安兵衛が歌吉と心中すると、「うまく片づけた」と冷たくつぶやいたほど、徹底していた。
のちに、講釈師の猫遊軒伯痴に「あたしと夫婦になりませんか」と「お孝らしくずばりと」申し込み、結婚する。このあたりの描写は、妙におかしい。一流芸者の娘は二人とも玉の輿に乗せ、芸人の妻としてもしっかりと切り盛りする。立派に人生の勝者になってしまうのだ。お孝は非情にして優秀なビジネスマンのような女だ。
母の教えをしっかりと守ってすましこんでいる娘二人が、ある日、継父の伯痴と珍しく破目をはずし、歌ったり踊ったりして楽しむ。
「姉が三味線を妹が唄を、冴え冴えとした修業の果てが、降りしきる秋雨の中で汽車の時間も忘れたように、羽目を外して何時までもつづいた」。その一瞬を伯痴は、「これが人生の姿だ」と思う。
川口松太郎の、芸および芸人にたいする敬愛の気持がにじみ出ている一節である。「歌吉心中」の最後は、こんな言葉で終わっている。
「人生の姿」から隔てられたところで立派におさまっている人間にたいする憫笑。利口者のお孝よりも、「死んでも好いな」「思い残りはありませんか」「何もない」と言って死んで行った安兵衛と歌吉のほうが、愚かしいかもしれないが幸せに思える。
おっと、いけない、紙数が尽きてきてしまった。
【この書評が収録されている書籍】
対談の相手は、内田百閒、谷崎潤一郎、久保田万太郎、吉川英治、柳田國男、福田恆存、江戸川乱歩……などそうそうたる顔ぶれである。たぶん、その中で一番若いのは『太陽の季節』を書いてまもなくの石原慎太郎だろう。夢声が「なんと彼の笑い顔は、オードリ・ヘップバーンそっくりなのは意外な発見だった」と書いているのがおかしい。
この二冊の対談集を読んで、一番面白く印象に残ったのは、思いがけずも川口松太郎だった。
私は川口松太郎という作家に関してほとんど何も知らず(川口浩・晶きょうだいのパパあるいは松島トモ子ちゃんのおかあさん役として映画に出ていた三益愛子の夫――ということくらいしか知らなかった)、関心もなかった。有名な作家と言っても何しろ『鶴八鶴次郎』とか『しぐれ茶屋おりく』とか、商業演劇系、いや新派系の芝居になるような小説を書いていた人で、私はそういう世界にほとんど関心がなかったのだ。しかし、夢声との対談を読んでいたら、
「そいつァ大きなリョウケンちがいだよ。“およしよ”たぁいわないがね」
「ぼくはむかしっから、温泉へいって書くとか、山へはいって書くとかってことができねえんだよ。表へ出りゃあすぐ芝居がある、映画館がある、カフェーがある、みんな働いている、そういうとこで書きたいな。精進はするが、陰気くさいこもり方はとてもできねえや」
といった調子の、まるで落語「大工調べ」のイキのいい棟梁のようなしゃべりなので、にわかに親しみを感じてしまったのだ。乱暴で、ズケズケとした、悪態めいた口のきき方の裏に、ばかばかしいほど屈折した羞恥心を感じる。
夢声は「(自分が)俳優不適格のいちばん大きい理由は、ぼくがてれ屋であることだ」「ぼくら、てれないなんてえわけにゃ、とてもいかないな」と語っているが、この二人は、おかしな羞恥心とそこから発生した独得の流儀というもの(それは、大ざっぱに言えば都会の生活文化というものだ)を共有している感じが確かにあって、他の対談にはない、何か暖かく密な感じが漂っているのだ。
というわけで、俄然、川口松太郎に興味を抱いたやさき、うまいぐあいに『人情馬鹿物語』(講談社、昭和四十九年版)と『昭和国民文学集8 川口松太郎』(筑摩書房、昭和四十九年版、『しぐれ茶屋おりく』『古都憂愁』『鶴八鶴次郎』が入っている)を入手した。
川口松太郎という人の個性が一番じかにわかるような気がするので、『人情馬鹿物語』について書いてみる。
川口松太郎は東京の浅草今戸町に生まれ、小学校卒業後、十六歳で久保田万太郎に師事し、はたちの頃から講釈師の悟道軒円玉のもとに住み込んで江戸文芸を学んだ。一般的な意味での学のある人ではないが、江戸文芸あるいは芸能といった面では一種の英才教育を受けた人といっていいと思う。
『人情馬鹿物語』は、講釈師の悟道軒円玉の家に住み、講談速記などを手伝いながら文芸の修業をしていた頃、そこで見聞した下町の人間模様を、虚実おりまぜながら十二の話に仕立てあげた、自伝的な短編集である。
面白い。何が面白いかというと妙な女が続々と出て来るところが面白い。
十二の短編は、ことごとく女が主役である。それも大半は堅気(かたぎ)のではなく、粋すじや芸人などのくろうとの女である。世慣れた女、こなれた女、わけのわかった女である。
子宮がんの手術がきっかけでひょんな男と「品物の試験でもするように」寝て以来仲むつまじく暮らすようになった女(「春情浮世節」)。
店の金を使い込んで逮捕された男のために、知人の間を奔走し、無罪放免にしてもらうが、その男とは夫婦にならず、サッと身を引いてしまった吉原の女「遊女夕霧」)。
自分の経営する待合に泊まった海軍の青年と深夜、浄瑠璃を語り合ううちに、親子ほどの年の違いも忘れ、「不思議な過ちの一夜」を明かしてしまう女(「親なしっ子」)。その後、青年は戦争で死ぬが、実はその青年は女が若い頃に生み、本妻宅に無理やり引き取られ、長い間会わずにいた息子だった――というのが凄い。
そういう、いわば「酸いも甘いもかみわけた」女たちの中で、異色なのが「歌吉心中」の準主役のお孝だ。
唐物商の吉田屋の内儀のお孝は、夫の安兵衛が芸者の歌吉に惚れ、財産をくいつぶすようになると、俄然、自立心に目ざめるようになる。
二人の娘を「残された、ただ一つの資本」と考え、「出世して父親を見返すのだ」という考えを吹き込み、精いっぱいの投資をして、みごと一流の芸者に仕立てあげる。夫への憎しみは、落ちぶれた安兵衛が歌吉と心中すると、「うまく片づけた」と冷たくつぶやいたほど、徹底していた。
のちに、講釈師の猫遊軒伯痴に「あたしと夫婦になりませんか」と「お孝らしくずばりと」申し込み、結婚する。このあたりの描写は、妙におかしい。一流芸者の娘は二人とも玉の輿に乗せ、芸人の妻としてもしっかりと切り盛りする。立派に人生の勝者になってしまうのだ。お孝は非情にして優秀なビジネスマンのような女だ。
母の教えをしっかりと守ってすましこんでいる娘二人が、ある日、継父の伯痴と珍しく破目をはずし、歌ったり踊ったりして楽しむ。
「姉が三味線を妹が唄を、冴え冴えとした修業の果てが、降りしきる秋雨の中で汽車の時間も忘れたように、羽目を外して何時までもつづいた」。その一瞬を伯痴は、「これが人生の姿だ」と思う。
川口松太郎の、芸および芸人にたいする敬愛の気持がにじみ出ている一節である。「歌吉心中」の最後は、こんな言葉で終わっている。
衰残の老伯痴はお孝よりも先に世を去ったが、その最後の瞬間に、“お前の生涯は成功ではなかったよ”と、笑ってささやいて死んで行った。
「人生の姿」から隔てられたところで立派におさまっている人間にたいする憫笑。利口者のお孝よりも、「死んでも好いな」「思い残りはありませんか」「何もない」と言って死んで行った安兵衛と歌吉のほうが、愚かしいかもしれないが幸せに思える。
おっと、いけない、紙数が尽きてきてしまった。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
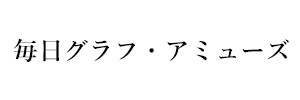
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1994年11月9日号
ALL REVIEWSをフォローする





































