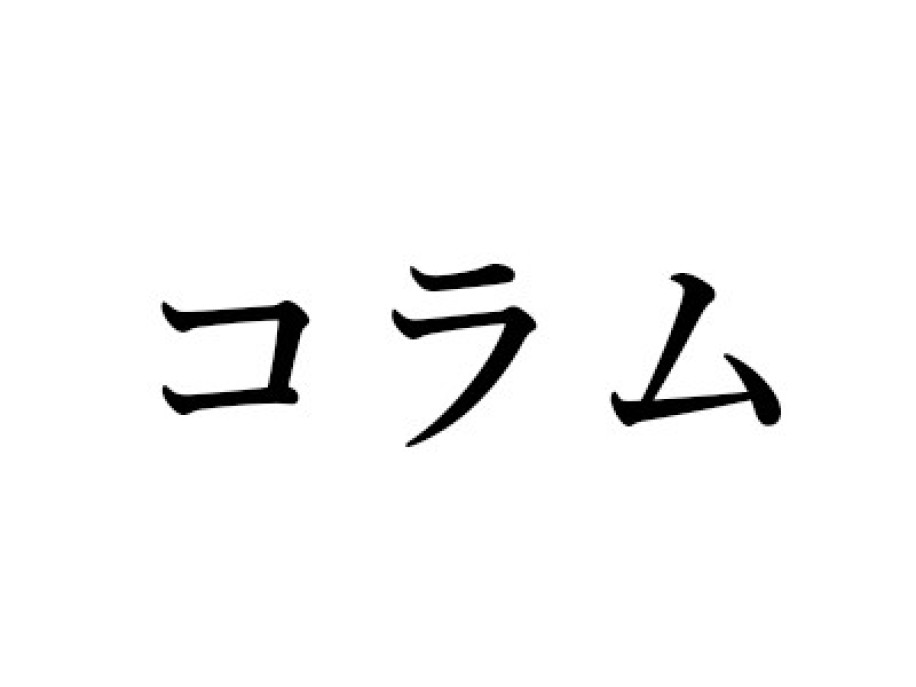書評
『一葉のポルトレ』(みすず書房)
奇蹟の文学を生み出した「習作」をめぐる人々
「ポルトレ」はフランス語でポートレートのこと。肖像(画)、また人物描写の意味もある。樋口一葉を生前に見知った人たちが、死後に思い出を書きのこした。それを集めたものだが、たのしい工夫がほどこされている。薄田泣菫(すすきだきゅうきん)、戸川秋骨(しゅうこつ)、平田禿木(とくぼく)、馬場孤蝶(こちょう)、半井桃水(なからいとうすい)……。先に筆者を短く紹介し、あわせて一葉の日記から、当の筆者について記述された個所(かしょ)の引用がつく。のちの英文学者戸川秋骨は東京帝大在学中に、友人の孤蝶、禿木らとひんぱんに一葉宅を訪れた。一葉の「水のうへ日記」明治二十八年十月のくだり。「秋骨も、幾度わがもとをとひけん。大方土曜日の夜ごとには訪ひ来る。来れば、やがて十一時すぎずして帰りし事なし。母も国子も厭(いと)ふは此(この)人なれど、いかがはせん……」
その秋骨によると、一葉は「調子のいい上に話上手聞上手」だったから「ツイツイお邪魔をしていた」という。「ともかく私共は教えるというより教えられるという方が多かったので、一寸若い叔母さんという感じがありました」
平田禿木がはじめて会ったときは、つつましやかで言葉少なかったが、二度目のときは十年の知己のように打ちとけて、「万丈の気焔(きえん)を上げる」ふぜいだった。「色浅黒く、髪は薄く少し赤味がかっていて、それをぎゅっとひっつめに結ってい、盛装などとても似合う柄ではなく、ただ興に乗じ、熱し切って談じるという際は、その眼がとても美しく、魅するように輝くだけであった」
一葉の日記に見る「平田ぬし」は、ある夜、酒気をおびてやってきて、友人にうながされても帰ろうとせず、「雨気をふくみし風、ひやゝかに酔ひたるおもてをなでゆけば、平田ぬし、あはれよき夜やと、かうべをめぐらしてはたゝへぬ……」。
この本のたのしさがおわかりだろうか。タイトルに二つの意味がこめられている。一つは見かけどおり、生前に一葉を見知っていた人たちによる一葉の肖像。もう一つは、その人々についての「一葉の」人物描写。むろん、こちらのポルトレこそが断然おもしろい。
要するに「人間」のちがいである。身近に一葉を見知った人たちは、おおかたが親のすねかじりの学生や華族の娘、文士たちだった。いっぽう一葉は小学校を中退させられてのち猛烈に勉強して、十代ですでに歌塾の代行として歌や古典を講じていた。貧しい町筋の小商いで母と妹の一家を支えようとした。死の前の二年ちかくは、果敢にも日本で初めて文筆で生きた女性だった。死の床で書きつづったのは、原稿料ほしさに引き受けた「手紙の書き方」。そして二十四年と半年あまりの若さで死んだ。
にわかに文才の上がるのを見すまして、灯に集まる虫のように男たちがやってくる。ノーテンキなお坊ちゃん帝大生を一葉がどんな目で見ていたか、どんなふうにあしらったか。文士半井桃水を知ったのは十九歳のときである。小説の手ほどきを受けた。それが小説にとどまらなかったのは一気に恋歌が生まれたことからもあきらかだ。断念をこめて日記につづった。
……我が恋は行雲のうはの空に消ゆべし
のちに日記の公刊によって友人にヒヤかされた桃水が書いている。「この節は冷かされ脅かされ、イヤハヤさんざんの仕合せである」
ヤニ下がった五十男を尻目にかけて、愛するものをもった女の強みである。日記にはすでに創作がはじまっており、その「習作」を足場にして奇蹟(きせき)のような文学が生まれた。
ALL REVIEWSをフォローする