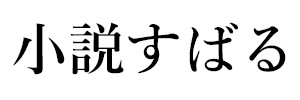選評
『笑う招き猫』(集英社)
小説すばる新人賞(第16回)
受賞作=山本幸久「笑う招き猫」(「アカコとヒトミと」改題)/他の候補作=須郷哲「プラチナガーデン」、藪淳一「虹のかかる街」/他の選考委員=阿刀田高、五木寛之、北方謙三、宮部みゆき/主催=集英社/後援=一ツ橋綜合財団/発表=「小説すばる」二〇〇三年十二月号「世田谷線はね」には勝てなかった
『虹のかかる街』(藪淳一)は、六つの短篇を列ねているが、作者はこの六篇を串刺しにする趣向を用意した。それは、赤、黄、緑など、一篇ずつ「色」を主題にすること、そして各篇にそれぞれ色のついたモノ(赤い手袋、黄色いれもんパイ、緑の野球帽など)を配し、それを通して、人生の時間の流れを物語のかたちで切り取ること、この二つ。すばらしい趣向である。とりわけ、「れもんパイ(黄)」は、冒頭にいきなりレシピを掲げて読者の心を掴む。そして幻のれもんパイを求めて、時の流れを探る女主人公の行動もおもしろく、すべて間断のない展開で、これは傑作の名に値する。しかし、あとの五篇は、人と人の出会い方が安易だったり、あまりにも調子がよすぎたり、どうもうまく行っていない。それに題名に「虹」と打った以上は、七篇は揃えたい。「れもんパイ」のような佳篇を、もう三つくらい読ませてください。『プラチナガーデン』(須郷哲)は、それとなく、そして、さりげなく、近未来小説を書いているところが出色である。おや、おや、おやと、読者に違和感を与えながら、やがて、「そうか、これは団塊世代が老人介護施設に収容される時代、いまより十年先の物語なんだな」と気づかせる手順に、才能がある。また、物語の主人公で、沼のほとりで自死を試みる少女がいるが、彼女とおじいさん人形との対話にも魅力がある。おじいさん人形はこんなことをいうのだ。
「無意味の奥の奥を、ずーっと、目を皿のようにして見続けるんだ。苦しさも甘さもとことんかみしめて、味わうんだ。……そこから一時も目をそらすんじゃない。それを忘れたときに、すべてはアタリマエに成り下がる」
自死と正面から取り組んでいるからこそ出てくる台詞で、破綻は多いものの、この凝視力は高く買いたい。
最高点を得た『笑う招き猫』(山本幸久)は、類型人物たちによる類型的な成長物語である。しかし、作者が偉かったのは、最初から最後まで類型を徹底したことである。類型を貫いた末に顕れたのは奇跡、まったく新しい人間たちだった。なによりも、展開と対話にリズムがある。作者の乗りが読む側の快感になるという幸せ、それがここに成就している。そして、挿入歌が、みんな傑作だ。わたしは初め、『プラチナガーデン』を推していたが、やはり、「世田谷線はね、ほんとは新幹線になりたいの」というバカバカしいほどの傑作歌には勝てなかった。この歌を読まないと、それは一生の損になる。
【この選評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする