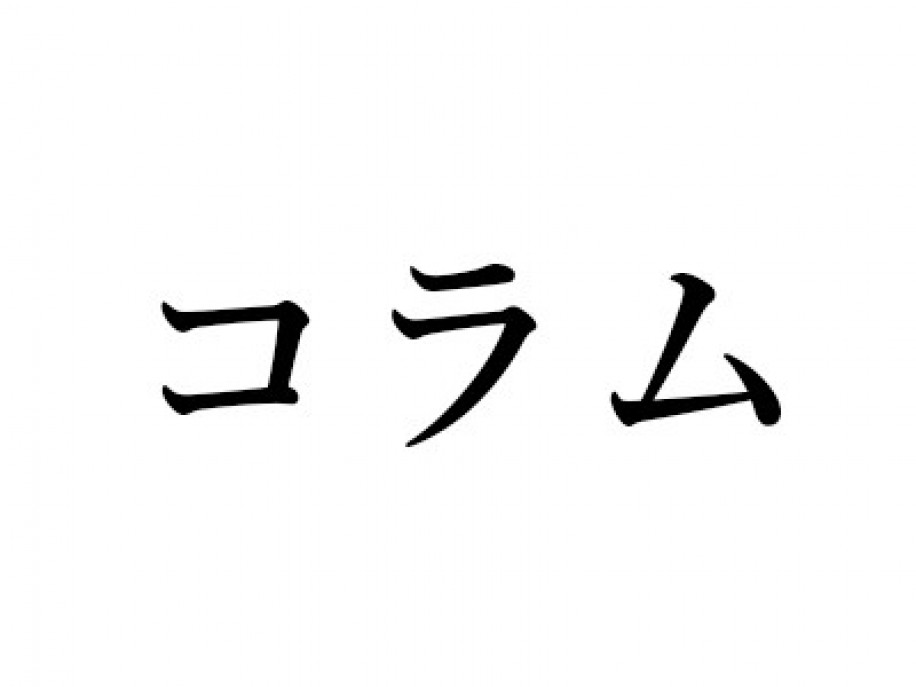書評
『三十歳』(岩波書店)
詩人の流儀による喪失の遍歴譚
インゲボルク・バッハマン(一九二六~七三)はギュンター・グラス(一九二七~二○一五)とならび戦後ドイツ文学の並外れた才能だった。グラスはかつてのドイツ語圏の北端にあたるダンツィヒ(現ポーランド・グダニスク)に生まれた。バッハマンは南端にあたるオーストリアのクラーゲンフルトの生まれ。ともに言語的辺境に育った。まず詩人として出発した点でも共通している。ついで小説にうつった。グラスは一九五九年、長篇小説『ブリキの太鼓』を発表。ベストセラー作家として躍り出た。バッハマンは一九六一年、短篇集『三十歳』によって表現世界に衝撃を与えた。以後、グラスはたくましい散文作家として半世紀にわたって書きつづけ、ノーベル賞作家となった。バッハマンの長篇三部作は「さまざまな死に方」をモチーフにして、第一部は書き上げられたが、二部・三部は草稿にとどまり、四十七歳で謎めいた死をとげた。
もの心ついたころ、カギ十字のマークをつけた褐色の制服が町にあらわれ、みるまにその数がふえていった。ヒトラーが政権につき、オーストリアはナチス・ドイツに併合され、少年、少女はヒトラー・ユーゲントに組みこまれた。ユダヤ人が追い立てられ、密告が奨励され、戦争が起こり、国中がガレキの山となって独裁国家が消滅。
二人とも鋭敏な十代のまなざしで、大人たちの実態をながめていた。「よき市民」たちのズルさ、小心ぶり、無責任。彼らはいつも強い方ににじり寄る。凡庸な悪の根源を正確に見つめていた。凡庸だからこそ、それはいかなる体制の下でも、くり返し芽を出すだろう。
グラスでは小説の主人公は三歳で成長を拒み、その視点から人と社会を語っていった。バッハマンでは三十歳だった。「彼は落ち着かなくなった。スーツケースに荷物を詰め、部屋を解約し、周りの環境や自分の過去に別れを告げずにはいられなくなった」。すべてにケリをつけ、身軽になる。そして最期には「何の痕跡も残さず」姿を消す。
表題作のほか六篇を収め、ゆるやかな連作として読める。語り手は「ぼく」「わたし」「彼」「ぼくたち」とさまざまだが、つねに喪失がテーマになっている。失って、もはやもどらないもの。幼年期ですらあやしいのだ。「オーストリアの町での子ども時代」に述べてある。「彼らは全世界を恐れている。彼らには世界のイメージがなく、敵と味方の区別があるだけ」
若さは行方知れずで、成熟は訪れない。戦後十年のウィーンの群像は「人殺しと狂人たちのなかで」と題されている。誰もが秘密警察の盗聴を恐れるかのように「隠れ簑(みの)を身につけてほほえみ、たくさんのことをまだ克服できずにいる」からだ。
清新な新訳で、早くに逝った異才を読んで気がつく。なんと現代的な心理状況が印象深く語られていることだろう。つまりは微妙な欠落感であって、誰もがいつも抱いているのに、これをめぐって書かれることはきわめて少ない。もともと言葉にならないもの。バッハマンはそれを喪失の遍歴譚として書きつづけた。いかにも詩人の流儀である。言葉にならないものを表現の美学とし、飛躍のための足場にして、運命的な時の流れを書きとめようとした。語り手は三十歳にして末期の目をもち、すべてが過去の残像風景と似てくる。単文を主としたキレのいい文体は、音楽でいうモルト・エスプレシーヴォ、「もっとも表現ゆたかに」。そんなふうに作者は書き、そんなふうに訳者は訳した。
ALL REVIEWSをフォローする