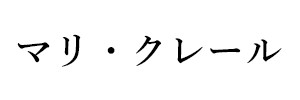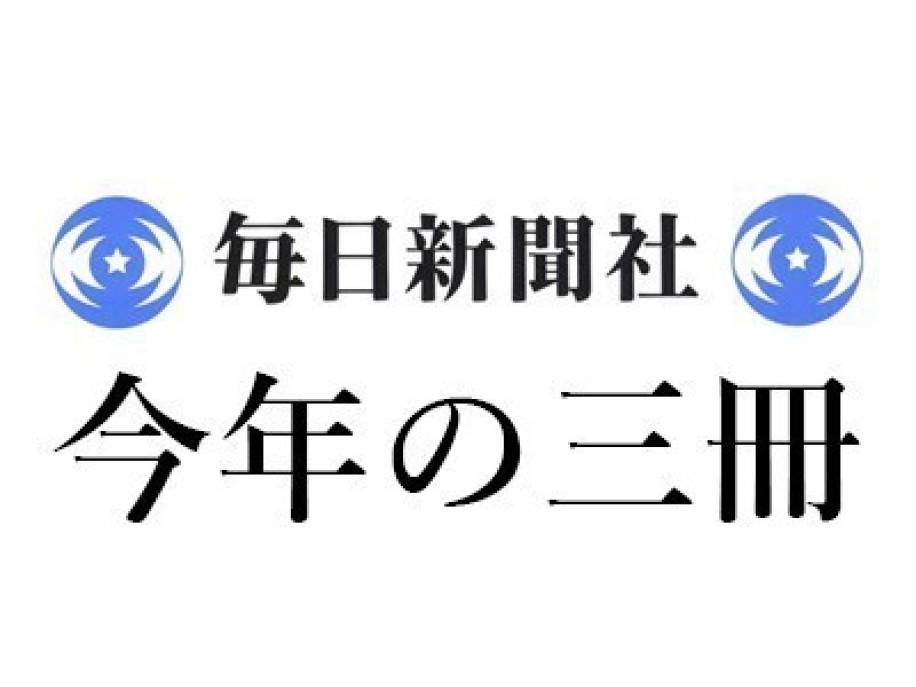書評
『名誉の戦場』(新潮社)
雨の匂い立つ小説
パリのキオスクで新聞・雑誌の売り子をしていた中年男がはじめて小説を書き、最も注目度の高い文学賞を獲得して一躍文壇の寵児となる。そんな十九世紀的成功譚が現実のものとなったのは、一九九〇年秋のことだった。ジャン・ルオー『名誉の戦場』。第一次世界大戦の記憶を引きずった語り手の親族を静かに回顧していくこの小説は、あまたのフランス人が味わった悲劇の一端にすぎない地方の家族の不幸から、どの国の、どんな時代の、どんな人間にも通用する普遍を引き出してみせた、美しい散文の達成である。魅力のひとつは、舞台となる下ロワール地方を湿らす雨だ。雨の匂い立つ小説と言ったらいいのか、この物語では本当によく雨が降る。それもロマネスクな小道具としての退屈な雨ではなく、いくつもの微細な階調に染まった雨が描きわけられ、読み手の鼻孔と皮膚に訴えかける。霧雨、雷雨、驟雨にこぬか雨。ときには土砂降りとなり、ときには北西風をともなって冷たく吹きつける雨は、この地に暮らす人々にとって、「人生のパートナー」なのである。複雑な雨の諸相の描写には、作者みずからその影響を認めるクロード・シモンに倣った息のながい文章が効率よく使われ、シモンの小説に漂う風や干し草の匂いとも通じた、陰湿でない独特の質感を保つ雨の肌触りが再現されている。
雨についてひとしきり論じたあとで、まさにその雨の降り方に我慢のならない「おばあさん」の話を持ち出すのは、だから、きめこまかな観察眼と大陸ではめずらしい英国風ユーモアに恵まれたルオーの計算なのだ。彼女は飄々とした生きざまを貫く一歳年下の夫、すなわち「おじいさん」が、雨にこのうえなく不向きな幌屋根式シトロエン2C――「2CVは霊長類の頭蓋に似ていた」というさりげない一句がいい――を駆って走ることにも我慢がならない。生活の規格である雨を拒むことで、親同士の話し合いが生んだ自身の結婚とその後の人生をも暗に否定しているのではないか、と解釈する話者の眼はやさしくかつ残酷なものだが、このふたりを柱とする登場人物たちはみな、雨がその強弱を変化させるときに似た、予測不可能な、しかし滑らかにはちがいない語りのなかで、クロノロジーを無視して入れ替わり立ち替わり顔を出し、いつのまにか読者と旧知の間柄になっている。
なかでも忘れがたい印象を残すのが、使徒のごとく教育に打ち込む老教師の「ちいおばちゃん」ことマリーの存在だ。二十六歳で生理が止まってしまった原罪なきオールドミス。なぜ無月経に見舞われたのか、その痛ましい理由は、物語の後半、曇り空から不意にのぞいた陽光さながらちらりと説明されている。悪魔的な強風が吹き荒れ、フロベールばりの喜劇にしたてあげられてしまう彼女の葬儀の場面はもとより、ルオーの最良の部分が、この不遇な叔母の扱い方と、彼女に向けられた、同情とはまた異質の、いたわりに満ちた視線に顕われている。
祖母や叔母にくらべると、両親の影が奇妙に薄い。それが意図的な操作だったことは、一九九三年に刊行された続篇『偉人たち』を一読すれば明らかになるだろう。内気な父親を主人公に押し立て、変わらぬ繊細な語り口でふたたびルオーの世界を楽しませてくれるこの第二作も、いずれ日本語に移されることを期待したい。
【新版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする