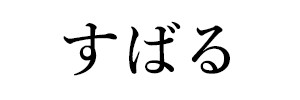書評
『火炎樹』(国書刊行会)
蜂鳥式脱糞の美学
おなじ世代の作家でおなじ名を持ちながら、寡黙きわまりない、ほとんど故意の言い落としの洗練に走ったモディアノとは対照的な世界を描きつづけているグランヴィルの小説が、ついに邦訳された(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1998年)。一九七六年のゴンクール賞を受賞した、作者二十九歳の出世作『火炎樹』。若さと奔放華麗な想像力が最も有機的にむすびついた本書の紹介は、刊行年度の新しさと作品の鮮度が混同されがちな翻訳小説の世界に、遅蒔きながらひとつの希望を与えてくれる快挙だろう。とりわけ一九七〇年代の小説はその後の思想ブームに押されて日本ではほぼ抹殺された感があり、今回のグランヴィル紹介は、近年のフランス小説輸入史のなかでも、かなり勇気ある試みとして評価したい。グランヴィルの世界の大枠は、「神話的自伝」と名づけられた初期の三部作『毛皮』(一九七二)、『縁』(一九七三)、『深淵』(一九七四)で、すでにいちおうの形をなしている。饒舌を通り越した形容詞の奔流が生み出すエロティックな文体、過度にデフォルメされた登場人物、それが正鵠を得ているかどうかはべつとして「バロック的」と称される、均整を無視した夢のようなヴィジョン。時代を経るにつれていくらか読みやすい文体が採用されるようにはなるものの、日常生活の彼方にある、もしくは人間の底にひそむ神話的な原質を圧倒的な筆力で追う作風に大きな変化は見られない。すべての小説の核が出そろったこの絢爛たる『火炎樹』に着目すべきなのはそのためである。
狂気の国王トコール・ヤリ・ユルマタが数十年にわたって専制政治を敷いてきたヤリ族の国。豪奢な宮殿のある首都マンドゥカと、貧民街のムルマコの対比には、近代都市とスラム、ミラージュ戦闘機を配備した軍隊と原色の跳梁する未開の保護地区、一国のまつりごとを司る独裁者の冷静沈着と突拍子もない振る舞いの共存が重ね合わされている。物語は、ブラック・アフリカに設定されたこの架空の王国へ、ウィリアム・イリガルというひとりの白人青年が派遣されてくるところからはじまるのだが、いきなり紙面を占拠するのは、猛烈な嵐に襲われた破壊と生成の映像であり、その映像にまったくひけをとらない「壮大な醜悪さ」の権化たるトコールの姿だ。「何とも言い様のない行儀の悪さを遥かな高みに持ち上げて、それを変質させる」国王にウィリアムは魅了され、蛮行のかぎりをつぶさに目撃する。
荒唐無稽な小説的興趣の最たるものは、トコールが色鮮やかな蜂鳥をつぎつぎに呑みくだし、強烈な腹痛に見舞われて極彩色の下痢に煩悶する場面だ。「ルビーやサファイアの洗いなおされたリボンが色とりどりの数珠になって吹き出し」てくる一場をもって、聖と俗、純と不純をあわせもつ主人公から、読者はもう目が離せなくなる。常軌を逸した人物が君臨する王国を転覆できるのは、「未知の世界から抜け出してきた不思議なディオルル族」だけだ。蜂鳥式の脱糞にも似たグランヴィルの言葉を数百頁にわたって読み継ぎ、そのディオルル族の力に触れたとき、読者は文字どおりの炎となって混沌とした世界を焼きつくす火炎樹の、鮮やかな顕現を目のあたりにするだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする