書評
『グロテスク 上』(文藝春秋)
作家・桐野夏生の人間洞察力の凄みを、過剰なまでに味わわせてくれるのが話題の最新刊『グロテスク』だ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は2003年)。昼は一流企業の総合職OLで、夜は「立ちんぼう」と呼ばれる最下層の娼婦。二つの貌(かお)を持つ慶大卒のエリート女性が外国人労働者に殺されて――。この小説は「東電OL殺人事件」として有名な、あの事件を下敷きにしている。でも、単なるモデル小説ではない。桐野さんはそれを物語に昇華するため、現実の事件の被害者を彷彿させるキャラクター和恵以外に、幾つかの仕掛けを用意しているのだ。
そのひとつが、怖ろしいほどの美貌の持ち主ユリコと、凡庸な容姿にしか生まれてこなかったユリコの姉にして、この物語の主な語部(かたりべ)となっている〈わたし〉の存在。物語は、新宿の安アパートの一室で半裸の死体となって発見されたユリコと自分の半生を語る〈わたし〉の声で立ち上がる。妹のことを「ひと言で言うなら怪物でした」と非難する〈わたし〉。吝嗇(りんしょく)な父と、ユリコを生んだとはとても思えない貧相な容貌の母を軽蔑する〈わたし〉。家族に向ける黒い意志が淡々と語り起こされていく、この導入部からして鳥肌ものなんである。
そうした姉妹の確執を描くに加え、作者は名門大学の附属学校という“階級社会”の内実を明らかにしていく。そのことで裕福でもなく、美人でもなく、才能もない女子がさらされる、世間という名の暴力を暴き出し、〈わたし〉とユリコと和恵の物語に圧倒的なリアリティーを与えることに成功しているのだ。
「女の子にとって、外見は他人をかなり圧倒できること」
「個性だの、才能だの、そんなものは、凡庸な種族が何とか競争社会を生き延びるために備えて磨く武器でしかない」
妹に対抗するために、競争社会を生き延びるために、“悪意”という才能を磨き上げていく〈わたし〉。初等部から入学した家柄もセンスもよい「内部生」と中学や高校から入ってきた「外部生」、非凡と凡庸、強者と弱者。その残酷な現実を受け入れず、じたばたあがいては同級生たちの冷笑の的となる和恵。そして、「男に欲されることによって、初めて存在する意味を持てた」ユリコは、生まれついての娼婦であることを自覚し、嬉々としてその道に入っていく。
その三人に、ずば抜けた頭脳によって苛酷な階級社会に居場所を見つけたものの、後にオウム真理教を彷彿させるカルト宗教に入信し、刑務所に入れられることになるミツルを加えた、四者四様の青春時代を綴った前半部がもたらす、重い衝撃と悪意の横溢(おういつ)による嫌悪感たるや凄まじい限りなのである。
そして、もうひとつの仕掛けが、和恵とユリコ殺しの容疑者チャンによる上申書。生まれた場所で一生が決まってしまうと言われる中国で、最下層の家に生まれ、艱難辛苦(かんなんしんく)の末、日本に密入国した彼の半生を追うことで、桐野さんは階級社会と差別の構造をさらに深く露(あらわ)にしていくのだ。
語りの視点を、〈わたし〉、ユリコの手記、チャンの上申書、和恵の日記などに切り替える仕掛けも巧妙だ。共通する出来事にまつわる各々の言い分にズレが生じるため、読み手は一体誰の言葉が本当なのかという疑いを抱かざるを得ない。まさに真相は“藪の中”ならぬ、人の心の“闇の中”なのである。
登場人物の誰にも心を寄り添わせず、一切の同情や共感を排して、彼女らの心の闇を暴き出す桐野さんの苛烈な作家魂こそが、まさにグロテスク。どこにも救いのない現実を、千四百枚もかけて描き通した桐野夏生こそが怪物だとわたしは思う。男子はこの際どうでもいい。女子必読! これは女子の女子による女子のためのノワール小説なのだから。
【下巻】
【この書評が収録されている書籍】
そのひとつが、怖ろしいほどの美貌の持ち主ユリコと、凡庸な容姿にしか生まれてこなかったユリコの姉にして、この物語の主な語部(かたりべ)となっている〈わたし〉の存在。物語は、新宿の安アパートの一室で半裸の死体となって発見されたユリコと自分の半生を語る〈わたし〉の声で立ち上がる。妹のことを「ひと言で言うなら怪物でした」と非難する〈わたし〉。吝嗇(りんしょく)な父と、ユリコを生んだとはとても思えない貧相な容貌の母を軽蔑する〈わたし〉。家族に向ける黒い意志が淡々と語り起こされていく、この導入部からして鳥肌ものなんである。
そうした姉妹の確執を描くに加え、作者は名門大学の附属学校という“階級社会”の内実を明らかにしていく。そのことで裕福でもなく、美人でもなく、才能もない女子がさらされる、世間という名の暴力を暴き出し、〈わたし〉とユリコと和恵の物語に圧倒的なリアリティーを与えることに成功しているのだ。
「女の子にとって、外見は他人をかなり圧倒できること」
「個性だの、才能だの、そんなものは、凡庸な種族が何とか競争社会を生き延びるために備えて磨く武器でしかない」
妹に対抗するために、競争社会を生き延びるために、“悪意”という才能を磨き上げていく〈わたし〉。初等部から入学した家柄もセンスもよい「内部生」と中学や高校から入ってきた「外部生」、非凡と凡庸、強者と弱者。その残酷な現実を受け入れず、じたばたあがいては同級生たちの冷笑の的となる和恵。そして、「男に欲されることによって、初めて存在する意味を持てた」ユリコは、生まれついての娼婦であることを自覚し、嬉々としてその道に入っていく。
その三人に、ずば抜けた頭脳によって苛酷な階級社会に居場所を見つけたものの、後にオウム真理教を彷彿させるカルト宗教に入信し、刑務所に入れられることになるミツルを加えた、四者四様の青春時代を綴った前半部がもたらす、重い衝撃と悪意の横溢(おういつ)による嫌悪感たるや凄まじい限りなのである。
そして、もうひとつの仕掛けが、和恵とユリコ殺しの容疑者チャンによる上申書。生まれた場所で一生が決まってしまうと言われる中国で、最下層の家に生まれ、艱難辛苦(かんなんしんく)の末、日本に密入国した彼の半生を追うことで、桐野さんは階級社会と差別の構造をさらに深く露(あらわ)にしていくのだ。
語りの視点を、〈わたし〉、ユリコの手記、チャンの上申書、和恵の日記などに切り替える仕掛けも巧妙だ。共通する出来事にまつわる各々の言い分にズレが生じるため、読み手は一体誰の言葉が本当なのかという疑いを抱かざるを得ない。まさに真相は“藪の中”ならぬ、人の心の“闇の中”なのである。
登場人物の誰にも心を寄り添わせず、一切の同情や共感を排して、彼女らの心の闇を暴き出す桐野さんの苛烈な作家魂こそが、まさにグロテスク。どこにも救いのない現実を、千四百枚もかけて描き通した桐野夏生こそが怪物だとわたしは思う。男子はこの際どうでもいい。女子必読! これは女子の女子による女子のためのノワール小説なのだから。
【下巻】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
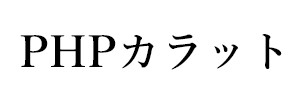
PHPカラット(終刊) 2003年11月号
ALL REVIEWSをフォローする








































