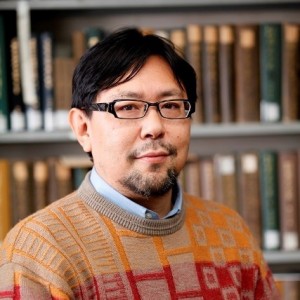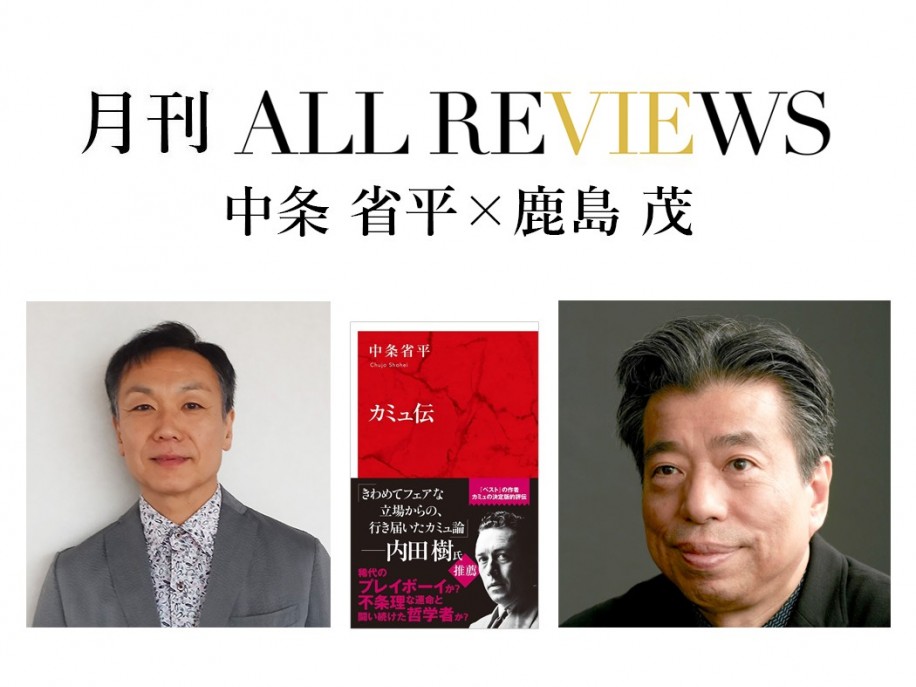書評
『戦国、まずい飯!』(集英社インターナショナル)
まずいをうまいに変えた たかが塩、されど塩
徳川家康と配下の諸将が、酒を飲みながら「一番うまいもの」について語り合っていた。こう調理した鳥だ、あの海で取れた魚だと盛り上がったところで、家康は傍らに侍(はべ)る年若いお勝の方(のち水戸徳川家・准母となる)にも聞いてみた。すると聡明で聞こえた彼女はすまして「塩でございます」と言った。塩がなければどんな食材の味も引き立たない。だから一番は塩だ、と。ちなみに一番まずいのも、入れすぎると味を壊すのでこれまた塩、と指摘した。ぼくはこのエピソードを読んだとき、こざかしい、と嫌な気分になった。主君の愛を受ける彼女が言うことには、「おお、これは一本取られましたな」と歴戦の武将たちもお追従を言うに相違ない。これしきのことで「私は賢い女です」とは笑わせる。
だが! この本を読んでみると、それが見当はずれの感想だったのでは、と思わずにはいられなくなる。戦国時代、いかに武士たちは、ということは農民はもっと、まずい飯を食べていたか。味がうすい、あるいはしないところに塩を適量入れると、格段にうまくなる。家康と部下たちの食生活のリアルを知ると、お勝の方の指摘は実に正鵠(せいこく)を射ているのが分かる。
武士は平安時代、狩りに熟達する人として登場してきた。だが、その獲物たる鹿や猪をどう調理したか、は語られない。肉食のタブーを、私はずっと不思議に思っていた。この疑問に答えてくれたのも本書である。著者の説明に接したとき、私はとても納得した。この著者は実に信頼できる、と感服した。
その信頼できる著者が、戦国時代のまずい飯のありようを克明に説き明かしてくれる。比べものにならぬくらいうまい肴をつまみながら、500年前に思いを馳せてみよう。
ALL REVIEWSをフォローする