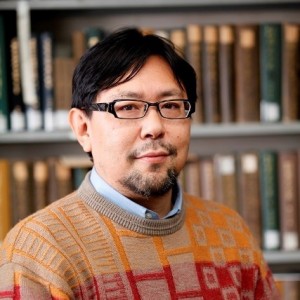書評
『図典「大和名所図会」を読む: 奈良名所むかし案内』(創元社)
江戸の“旅行ガイド”で旅気分を味わうもよし
このコラムは歴史絵画を好んで取り上げてきた。その理由は「百聞は一見にしかず」。どんなに言葉を尽くして説明するより、視覚的に「こうです」と訴えた方が効果的、ということが多いからだ。だが、今回はちょっと様子が異なる点がある。江戸時代になると、庶民は旅行を楽しむようになった。道路は整備され、警察機構が設置され、道中はかなり安全になった。人々は名所旧跡を旅して、見聞を広めた。観光の誕生である。
この趨勢を後押ししたのが、多く出版された名所案内記だった。本書はその白眉『大和名所図会』(1791年刊行。以下、『図会』と呼ぶ)に基づく。『図会』の著者は秋里籬島(りとう)、絵師は竹原春朝斎。二人は『都名所図会』でもヒットを飛ばした名コンビで、とくに秋里は時代を代表する名所図会作者の一人だった。
『図会』には現在の奈良県各所の社寺境内の鳥瞰図、自然や旧跡の風景図、習俗や名産、年中行事の描写、故事・伝承をもとにした絵物語など、さまざまに趣向を凝らした絵画が収録される。秋里と竹原は徹底的な現地主義を採り、綿密な打ち合わせを経て、『図会』を世に送り出した。
ところが、このうち「故事・伝承をもとにした絵物語」に落とし穴があった。大和地方は長い歴史を有している。そのため、故事や伝承は遥か昔、古代のもの。過去の世を秋里も竹原もよく知らない。そのため、古代人の姿かたちが江戸時代人と同じように描かれる。これが何ともユーモラスである。
特筆すべきは本書の著者、本渡章氏の文章のうまさと濃さ。『図会』の時代考証の欠点を補ってあまりある見事な解説を詳細に叙述してくれる。こんな時節だけに、本書をじっくり眺め、私たち日本人のルーツともいうべき大和に、思いを馳せてみたい。
ALL REVIEWSをフォローする