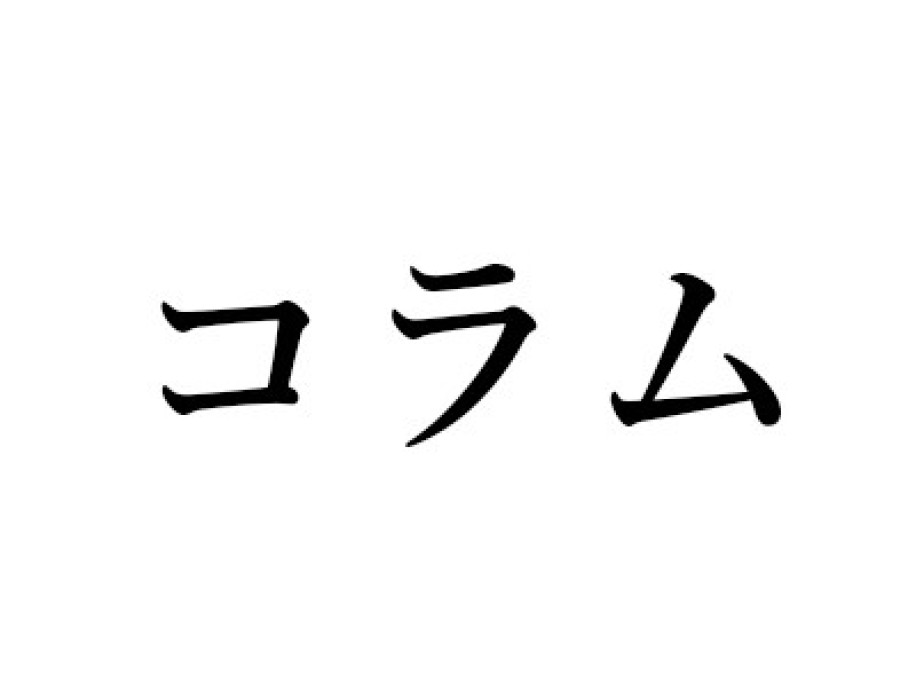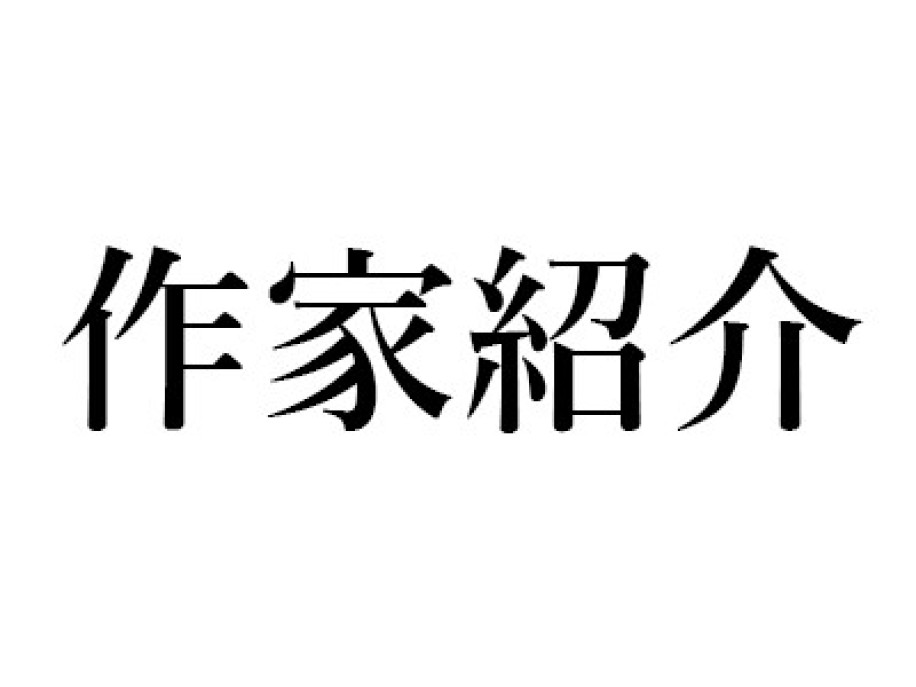解説
『マリアの気紛れ書き 森茉莉全集 第5巻』(筑摩書房)
ナラノシカノカズハ――父の娘、茉莉
高校のころ、森茉莉の『枯葉の寝床』や『恋人たちの森』に入れ込んだ時期がある。正直にいうと友人の影響だ。貴族趣味のキタバタケミキは、廃園で詩集をひもといているかと思えば、イギリスの少年のような半ズボンで捕虫網を握っていた。オスカア・ワイルド、ビアズレエ、ボオドレエル、黙阿弥がわれらが太陽で、森茉莉にならってセエヌやボオトといった表記で手紙をかわした。香水のサンプルを集めたり、今日は歌舞伎座、明日は国立劇場と、安い学生券で見歩いたものである。最近、森茉莉を再読しているのは、地誌として千駄木町で育った彼女のエッセイが役に立つからである。じつに邪(よこしま)な動機なのについ面白くてひきずり込まれる。自ら「なめくじ書き」というように、話はどんどん飛躍して、同じ頁に長嶋選手の引退とバスチイユのマリ・アントワネットが出てきたりする。才気があり、テンポがあり、美しい言葉に満ちている。話がずれていって面白い点ではまあ、『気まぐれ美術館』の洲之内徹と双璧だろう。
そして「出るぞ出るぞ」と思っていると、案の定、鷗外が出る。「そら出た」とこれはちょっとくすぐったい快楽である。「ひともする古都巡礼を」というエッセイでもついに京都に行かず、父への懐旧の情で押し通してしまった。
しかし、森茉莉は「鷗外を鼻先にぶらさげた女」という評は当らない。そうした人間関係のバランス感覚はむしろ欠如している。つまり人や自分を世間相場の名声や富で測ることは根っからできないのだ。パーティでの身の置き所に迷うように、文豪鷗外の娘だから自分はしかるべく遇されるべきだ、とは思わない。ただ、人間として失礼なヤツは許さないだけである。
父への手放しの礼賛は、権威主義ではなく愛情によるもので、彼女の黄金時代(ゴールデンエイジ)への無邪気な追憶にすぎない。そこは鷗外の妹、小金井喜美子の回想記とは趣きを異にする。
森茉莉は嫁ぐ十六歳の日まで、鷗外の膝に乗っていた。そこには「抱いて背中を軽く叩く父親とその柔(やさ)しさの中に体ごと入りこむ娘との、きれいな情緒のある、白い花の香ひのする関係」があった。これも一つの「性」である。何をしても、たとえば叔父の部屋から菓子を盗んでも、「泥棒もお茉莉がすれば上等よ」と父は許した。
それは森茉莉に、すくすく育った女性だけに許される自己肯定意識を与えた。忍従、卑屈、陰湿、愚痴っぽさと縁のない、日本女性には稀な楽天性とユウモアを彼女は身につけた。同性にモテるのも、近頃、若い女性に人気があるのもこのせいだろう。
読んでいて、やはり怖いものしらずのお嬢さんナンシー・キュナードを思い出す。あの人も「躍進するお嬢さん芸」がいま見ると尊い。森茉莉の場合も、美意識や好き嫌いに頼った物言いは戦時中、ややあやういところがあったが、『マリアの気紛れ書き』中の政治談義や辛口の文学批評は直観が効いている。たとえば室生犀星は意地悪な目で女を見ても心に痛みがあり、川端康成の目は乾いている。異常な《非情》であるというのも当りだろう。網野菊は「私にとって心を静かにしてくれる小説を書く人であった」という言葉はなつかしい。森茉莉のナルシシズムはやんちゃでかわいい。ねじれて一めぐりして元に戻ったような純情はいっそ美しい。
こんなところを楽しみながら、私は結局、その随筆から、千駄木町の生き生きした明治・大正の生活を読みとる。「父の居た場所――思い出の中の散歩道」はことに素直に書かれている。
私が生れてから結婚するまでの十六年間、父と住んでいた家は、本郷区駒込千駄木町二十一番地にあって、その場所をわかりやすいように言うと、昔菊人形で名高かった団子坂の上である。
団子坂はいまでも夕方登るときは西日がまぶしい。まるで人が地べたから生えてくるように急だ。降りるときは自然、誰かに押されるように足が前に出る。この坂には森邸、通称、観潮楼の裏門が面していた。一方、
表門の前は崖で、そこに立って向うを見ると、上野の山と、本郷台と呼ばれていた高台との谷間を埋めている町々の、無数の瓦屋根の群が、海の波のように見え、その屋根の波の向うに上野の森が霞んでいて、春には五重塔を取り巻く森の緑の中に、桜が薄白く烟っていた。
谷中の、露伴の五重塔である。この団子坂を横切る尾根道を通称「藪下」といい『日和下駄』で永井荷風が絶賛している。鷗外邸の前は「見晴し」とよび、町の人々は両国の花火や気球船ツェッペリン伯号もここから眺めた。
観潮楼とは、ここから品川沖の白帆が見えたからというのだが、あるとき鷗外は二階に妻を呼び、「海が見えるか」と聞いた。「見えません」と妻志げはいった。このエピソードは別の本で読んだが、こんな「正直と善良」を父は愛したと森茉莉は書いている。
茉莉の生活は、旧本郷区を中心に回っていた。上野の森の展覧会、精養軒の食事、仲町のたしがらやや宝丹などの老舗。夕方の散歩では本郷の青木堂でビスケットやマカロンを買った。団子坂下から三田行の市電に乗り、銀座に出て、資生堂のレストランに寄る。鷗外を鼻先にぶらさげてはいない森茉莉であるが、階級意識や零落意識の方はそこはかとない翳りとなって、黄金の日々を「静かに揺らぐ蠟燭の光」のように輝かせる。その楽しい日々の裏に「罅割れて赤く膨らんだ女中たちの労苦」があることも知っていたけれども。
観潮楼のあとは現在、文京区立の鷗外記念本郷図書館である。森茉莉のコーナーには、「麦酒のジョッキイと葉巻切り」のいかにも癖のつよい字の生原稿と、ベルリンから鷗外が持って帰った当のジョッキイや葉巻切りが並んでいる。毎年、奈良正倉院の調査に出張した鷗外の「コドモノミナニ」宛てた手紙もあった。
ナラノシカノカズハ六百ダサウデス。ソノクラヰ ヰルカラ山(ヤマ)ヤコウエンデ シバノキレイナトコロデ ヤスマウトシテモ シカノウンコガアルノデスワレマセン。シカハ大(オホ)キクテモミナ、小(チヒ)サイウンコヲシマス。チヤウドクロマメノヤウデス(大正七年十一月十六日)
ルビまで振られた片仮名の手紙。どれだけ鷗外が茉莉を愛していたか。どれだけ茉莉が愛されていたか。愛されすぎると人は大人になるのを拒む。森茉莉が自分を「婆さん子供」といっているように……。
【初出】『森茉莉全集5』月報
【再録】
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする