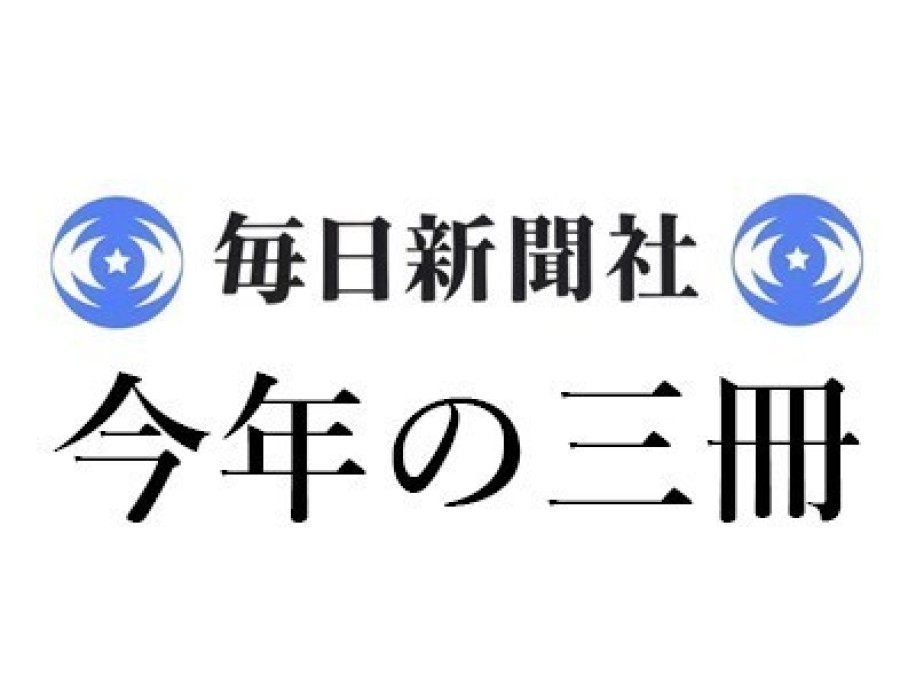書評
『あとを継ぐひと』(光文社)
不可欠でなくても必要なこと
タイトルそのままに、家業のあとを継ぐ人たちを描いた短編集である。と、タイトルと同様にシンプルに説明することもできてしまうが、たんなるあと継ぎ問題だけが描かれているのではない。おさめられた短編小説の舞台となるのは、客の入らない理容店、四世代続く麩(ふ)菓子製造会社、知的障碍(しょうがい)者の社員の多い事務用品の製造工場、老夫婦が酪農を営む牧場、性同一性障害の息子が女将(おかみ)をめざす老舗旅館、それから、ごくごくふつうのサラリーマン家庭、とさまざまだ。
オサダ理容店の店主である哲治は、息子の誠がまだ幼いころに離婚して以来、男手ひとつで誠を育ててきた。その息子は高校を出ると東京の相撲部屋に入門するも、怪我(けが)で引退を余儀なくされ、けれども実家には帰らず介護職に就く。二十九歳になった誠が、三年ぶりに実家の理容店に帰ってくるところから第一話がはじまるのだが、離婚の理由、その後の父と息子の暮らし、父親の意地、近所とのつきあい、じつに濃密なそれぞれの人生の断片が、みごとな手さばきであぶり出されていく。短い文章のなかにたちあがるのは、地方の町の、歴史に名を残しはしないが、確実にそこで歴史を刻んだ一軒の理容店であり、そこを支えたひとりの男の意地と葛藤であり、ひとつの家族のありかたである。無骨な父親にだいじにされ、近所の人やお客さんにかわいがられて育ったちいさな子どもが、がたいがよくて気持ちのやさしい男に成長し、そうしてゆっくり父親を追い抜いていく、その瞬間に読み手は立ち合うことになる。
そんなふうに、一編一編、短い枚数のなかに、ある仕事とその従事者、それをとりまく人間関係、家族関係がこまかくていねいに描き出されていく。華々しい職業は登場しない。同様に、大義を背負った人物も登場しない。作者の目は一貫して、見過ごしてしまいがちな目立たないものに向けられている。今のように、家業を継ぐことが宿命ではなく、進学も仕事も生まれ故郷を出ることも比較的選べる時代であっても、親の職業を継がないことに罪悪感を持ち続ける場合もあれば、代々続く家業を、先祖たちの思いとともにすんなり受け入れる場合もある。
小説に登場するその仕事について、著者は非常に綿密な取材を重ねていると思うのだが、それをたんなる資料にはせず、生き生きと小説に根づかせていて、そのことに感銘を受ける。菓子製造なら菓子製造、酪農なら酪農、ひとつの仕事の細部にわたるリアリティが、その職種への深い敬意を読み手に自然に抱かせ、小説全体にすがすがしい清潔感を漂わせている。
それで、思うのである。これらの仕事は、私たちが生きることに絶対的に不可欠ではないにしても、でもいつの時代も必要とされてきたものだ。不可欠ではない、ということと、必要ない、ということはイコールにはならない。これらの仕事が、絶対不可欠でないにもかかわらず今日まで続いているのは、もちろんあとを継ぐ人たち、その職を支える人たちがあってこそだが、市井の人たちもまた、それを必要とすることで、時代のあとを継いできたからなのかもしれない。何も継ぐものがないと言う娘と、その父親を描く「サラリーマンの父と娘」を読んで、「継ぐ」ことの意味の大きさについて考える。
ALL REVIEWSをフォローする