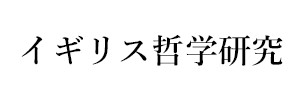書評
『リヴァイアサンと空気ポンプ―ホッブズ、ボイル、実験的生活―』(名古屋大学出版会)
現代における科学史研究の古典――「テクノロジー」によって巧みに管理される事実と仮説の境界線
本書は、1985年の刊行以来賛否両方向からの反響を喚起し、クーンの『科学革命の構造』以後最も影響力をもったとさえ評されてきた科学史研究である。原著刊行から30年余り経て、ようやく日本の一般読者に紹介される運びとなった本訳書は2011年の新版からの翻訳であり、これには初版執筆時に作用した文化的環境を回顧し、本書への批評を概観した長大な序文が付されている。本書は極めて豊富な論点を含み、限られた字数で満遍なく内容を紹介することは到底不可能である。各章の要約は第1章末尾にあるので、ここでは本書の中心的テーゼ、及び評者が関心を喚起された若干の事柄を述べることにしたい。1660年代に、イギリス王政復古体制が政治的安定を模索していた同じ頃、空気ポンプという新しく考案された実験装置が生み出す知識の正当性を巡って、ボイルとホッブズの間で論争が交わされた。自然認識の科学的方法を巡るこの局地的な論争に焦点を当て、著者シェイピンとシャッファーは、一見狭い知的世界の嵐に見えるこの論争が、実はそれを取り巻く政治的、社会的秩序の問題関心と緊密に結びついていたことを示そうとする。本書を貫く中心テーマは、「知識の問題に対する解決策は社会秩序の問題に対する解決策である」というものであり、したがって著者らは本書を、歴史的な事例研究を通した科学知識の社会学を実践する企てとして位置付ける。
科学が制度化された今日では、実験は知識のための信頼に値する手段として一般に受け入れられている。しかし現代の科学的営みの淵源に当たる17世紀の自然哲学では、事情が異なる。自然認識のあり方が大きく変貌を遂げたこの転換期、機械論的自然観が登場し自然哲学の数学化が進められた。これと並んで実験的方法が誕生し、様々な実験機器が開発、改良されるが、自然探求における実験の地位は、新しい自然哲学の賛同者たちの間で広く承認されていたわけではなく、また実験手続きについて一様な共通了解があったわけでもなかった。ホッブズは機械論哲学の旗手であるが、ボイルの実験プログラムの有効性を否定し、実験装置である空気ポンプの物理的欠陥を指摘して、「実験」の正当性に強力な反論を展開した哲学者だった。
シェイピンとシャッファーは、ホッブズにあえて寛大な解釈を取り、その批判的議論にも十分な注意を払いつつボイルとホッブズの論争を追うことで、実験が公認の地位をもつ現代の視点から離れ、実験的文化の「よそ者の視点」に身を置こうとする。それによって見えてくるのは、ボイルが推進した実験主義プログラムがホッブズの反論を斥け勝利したのは、そうなるのが自明で不可避であったからではなく、むしろ偶然的な歴史的環境の力がそこに働いたということである。ボイルの実験主義が自然哲学において地歩を確立したのは、実験的「事実」を生み出す知識生産の様式と、そこでの論争を律する一定の規則を備えた実験コミュニティの理想が、王政復古体制における政府や教会を担う体制エリートたちが求めていた社会秩序とうまく合致したからであると論じられる。つまり、本書の著者らによれば、実験的知識の真理や客観性、及び実験的方法の正当性は、ある歴史的状況の中で達成された結果なのである。
本書のこうした議論は、いわゆる科学革命の正典的理解とは一線を画しており(著者らは科学革命という概念に懐疑的である)、また科学に関する「社会構成主義」を標榜すると見なされ、その観点から批判されてもきた。しかし、本書は極めて興味深い論点を数多く含み、全体的結論に対する賛否に関わりなく、読者の関心に応じて刺激を受け多様な示唆を引き出すことができるであろう。
本書の議論で一つの中心になっているのは、「実験的生活」の中核をなす「事実(matter of fact)」を巡る考察である。ボイルの実験的な知識生産を特徴づけるのは、実験によって確立される事実と原因に関する仮説との間に厳格な境界線を引くことであるが、著者らはこの境界線がいかにボイルによって三つの「テクノロジー」(空気ポンプという機械装置、実験を記述する著作や論文、王立協会という実験家たちの共同体)を用いて巧みに管理されていたかを説明し、またそこで管理される事実と仮説の間の線引きが、明示的な規則によってではなく、実験家たちの実践を通じた暗黙の同意、社会的慣習によって支えられていたことを強調する。そこにホッブズを始め他の論敵たちがどんな問題点を見出したかは、第4章から第6章で詳述される。論争の的となったのは、ボイルが事実と見なす内容だけではない。実験が生み出すとされる「事実」というカテゴリー自体が問題であった。
著者らは、ボイルの「事実」とは社会的なカテゴリーであり、それが上記の「テクノロジー」を用いて集合的な「目撃」を作り出すことによって確立されると論じる。しかし、バーバラ・シャピロの研究(A Culture of Fact: England 1550-1720)の示すところでは、実はボイルには参照すべきモデルが存在した。「事実」はコモン・ローに基づくイングランドの法的実践で既に確立されており(‘fact’は行為者によって過去に為された業を指す)、それがベイコンを通じて自然哲学に転用され、観察された、あるいは実験的に生み出された、自然の業を意味するようになった。ボイルが「事実」カテゴリーを実験プログラムの基礎に置きえたのも、イングランドでは既にそれが社会的に流通していたからであるという。この指摘はシェイピンらの議論にも影響するし、ホッブズとボイルの論争を評価するにも重要な視点であろう。また、本書では第5章で短く触れられるだけだが、コモン・ローの法学者であり王座裁判所の首席判事であったマシュー・ヘイルが空気ポンプの実験に関与し、ボイルとモアの論争にも参戦して自身の見解を述べたというのは興味深い。
本書の訳文は全体として正確、明晰である。この書がボイルやイングランドの実験哲学について日本の幅広い読者層の関心を喚起するきっかけになれば喜ばしいことであろう。
[書き手]中野安章(哲学・科学思想史)
ALL REVIEWSをフォローする